.png)
足の悩みを、靴で解決する───出向起業というスキームで事業を始めた清水が目指すのは、「靴に足を合わせる」という世の中の当たり前を180度変えること。
2025.10.17 公開
.png)
2025.10.17 公開
株式会社DIFF. 代表取締役社長 清水 雄一
設立:2022年
事業内容:足の機能を守る3Dプリントシューズ事業

池田泉州キャピタル株式会社 投資部 部長
「自分に合ったシューズを簡単に手に入れられる」という「次世代の当たり前」を創る取組みは、アントレプレナー清水氏と、何よりも靴が大好きなDIFF.のチームだからこそ成し遂げる事ができると確信しております。 目指すべきMissionに向けて、試行錯誤しつつも確固たる意志を持ち、着実に前進を進めるDIFF. 。そこから波及する共創の輪は、大企業発スタートアップとしての成功事例になるものとも期待しております。「足が喜ぶ、あしたをつくる。」仲間として、是非、DIFF.の取組をご覧下さい。
株式会社DIFF.(ディフ)の代表をしている清水と申します。三重県の出身で、サッカーをやることとプラモデルをつくることが好きな子どもでした。
何かをつくることが好きだったので、高専に進学しました。もともとは「これをつくりたい!」という対象はなかったのですが、ずっとサッカーを続けていたこと�もあり、次第に「自分でサッカー用のスパイクをつくるのはおもしろそうだ」と思うようになったんです。そして、18歳とか19歳のときに、明確に自分の目標になりました。

私は機械工学の専攻で、図面を引いたり、旋盤を回したりして、高専ではモノをつくる工程を学んでいました。「将来はサッカー用スパイクをつくる」という目標を考えたときに、「モノづくりの基礎に加えて、人の体の動きも勉強したい」と考えるようになったんです。
そこで大学に編入するために勉強することにしたのですが、高専からの編入の場合、大学の工学部に行くのがメジャーなルートでした。ただ、私は、教育学部の体育学科に編入しようと考えていたので、高専の体育の先生のところに相談に行ったりして、みんなとは違うマイナーな動きを取っていたと思います(笑)。
高専だったので、そこまで本気ではなくて。インターハイに行くぞ!とかJリーガーを目指すぞ!という感じではなかったです。でも、いろん�なスポーツのなかでサッカーをやっているときが一番楽しくて、好きでずっと続けていました。サッカーを足元から支えるものとしてスパイクに興味を持ったという流れですね。
高専の体育の先生にサポートしてもらい、体育系の勉強をして、たまたま試験にも合格し、神戸大学の発達科学部に編入しました。そこから体の構造や、どういう理屈で体が動くのかなどを学んでいきました。
大学卒業のタイミングでスポーツメーカーの就職試験を受けたのですがうまくいかなくて、大学院に進むことにしました。大学院で研究していたのは、切り返しの動作についてです。いわゆる「ターン」ですね。
ターンするときに、人の体がどのように使われるのか。地面と足があって、その間に靴があるんですけど、接地面が大きい場合と小さい場合で、人の行動はどのように変わるのか。そういうマニアックな研究をしていました。
裸足でターンをするときと、靴を履いてするときと、体の使い方が違っていて、そういうのをデータを集めて検証していくというものです。地面に伝えられる力を計測する高性能の体重計みたいなものが埋まっていて、その上でターンをしてもらう。体にはたくさんのセンサーを貼り付けて、いろんな部位の動きを計測するみたいな。プロのアスリートが研究施設で解析しているところをテレビのニュースで見たことがあるかも��しれませんが、そういうことをやっていました。「重心がどうなっているか?」とか「股関節の使い方に差が出るね」とか、そういう研究をして、論文にまとめていました。
そうです。大学院を卒業後、総合スポーツ用品メーカーのミズノに就職しました。技術職として入社して、研究開発部という部署への配属でした。採用試験や面接のときから「サッカー用のスパイクをつくりたいです」としか言っていなかったのですが、入社してみると、いろんなアイテムがつくられる前の要素技術をつくっていく部署でした。

研究開発部では、いろんなプロダクトの部門と一緒に仕事をさせてもらいました。多かったのがゴルフクラブで、ゴルフボールを打ったときにいかに気持ち良い打球音になるかという研究開発の仕事が特に印象に残っています。
仕事の�中身としては少し専門的な話になるのですが、打球音を研究して、「特定の周波数帯がこうなるようにクラブをつくっていくのはどうでしょうか?」みたいなことをプロダクト側と意見交換して、方向性が決まったら基礎技術の開発に進むという感じです。
ゴルフクラブ以外の仕事でいうと、野球のバットのアプリケーション開発があります。加速度センサーやジャイロセンサーなど人の動きを計測できるセンサーがあるのですが、それをバットのグリップエンドに貼り付けるんです。その状態でバットを振ると、センサーが軌道を計測し、スマホのアプリで自分のスイングの軌道を見ることができる。そういうアプリケーションをつくっていきたいというプロジェクトで、私はセンサーで取得できた生のデータをアプリ上でどのように処理して「動き」を表現するかといった裏側のアルゴリズムを検討する仕事をしていました。
ミズノには2012年に入社したのですが、最初の4年間くらいが研究開発の仕事です。次の4年間で、念願が叶ってサッカー用のスパイクづくりに携わることができました。そして2020年からは、社内の新規事業プログラムの事務局をしていました。

現場社員から新規事業のアイデアが挙がってきて�、それを3ヶ月かけて事業プランにブラッシュアップしていき、最終的には役員にプレゼンするというプログラムです。私は事務局としてアイデアの取りまとめをしたり、ブラッシュアップをサポートしたりしながら、自分でもアイデアを出していました。自分のアイデアから事業化までいったものもあります。
視覚障がいをお持ちの方が使う杖があるのですが、あれのミズノ版をつくりました。「白杖(はくじょう)」と呼ばれるもので、杖先を滑らせて路面の情報を得たり、杖先で路面を叩きながら障害物がないかを確認するといった使い方をします。白杖を使っている方にお話を聞くと、杖自体に満足していない方がけっこう多いことがわかりました。常に杖を振りながら歩くので、手首が痛くなってしまうという声が多かったです。
ミズノには、ゴルフクラブに代表されるように、軽くて丈夫な長いものをつくる技術があります。その技術を使うことでお役に立てるのではないかと考え、有志でチームをつくって事業プランにしたんです。
スポーツ用品をつくる上で、「軽い」というのは常にトップクラスに入る要求性能です。ゴルフクラブ、野球のバット、テニスのラケット、いろいろありますが重くてずっしり��したものはほとんどありません。そのため、社内に蓄積されたノウハウと技術を活かせると考えました。商品化まで持っていけたことは、私にとって非常に良い経験になりましたね。
外部のビジネスコンテストに参加したのが、起業のきっかけだと思います。元々、ミズノの新規事業プログラムの事務局をしていたときに、先ほどの杖以外にもいくつか事業アイデアを出していたんです。その中には現在の事業に近いものもありました。
靴を選ぶときって、他の人とは足の大きさや形が異なるので、足を入れたときにうまくフィットする感じを誰かと共有するのが難しいと思っていたんです。そんな中で、自分と同じ足の人から「この靴を履いたら気持ち良かった」と情報交換ができるプラットフォームがあればおもしろいんじゃないかと考えました。
このアイデアはミズノ内での選考では良い評価を得られなかったんですけど(苦笑)。「他のコンテストだったら違う結果になるかもしれない」と思い、靴に関する事業アイデアはずっと考え続けていたんです。
それまでは、ビジネスコンテストやアクセラレーションプログラムは東京で開催されることがほとんどでした。しかしコロナになったことで場所の制約がなくなり、私が住んでいる大阪からでもフルリモートで参加できるようになりました。
応募しようと思い、いろんな人に「靴を買うときに何か悩んでいることはありますか?」と聞いて回りました。すると、「左右で足の大きさが違うので困っています」という声がけっこう多いことに気がついたんです。
いろいろ調べていくと、世の中には左右で別サイズの靴を履いた方が良い人がいて、その目安として足の大きさが3ミリ違う場合は、それぞれに合った別サイズの靴を履いた方が良いということでした。ミズノの社内にある足形のデータをひっくり返してみると、保有しているデータのうち、約5%の人が足の大きさが5ミリ以上違うことがわかりました。
左右で足の大きさが違ったとしても、お店に売ってるのは両足で同じサイズです。「靴は左右同じサイズ」という当たり前があり、その前提の上で市場が成り立っている。じゃあ、足の大きさが異なる人は、我慢せざるを得ない。この問題を解決できたら面白そうだなと思い、事業アイデアを組み立てていきました。

このアイデアを、一般社団法人ONE JAPANが主催している大企業挑戦者プログラム「CHANGE」に応募したところ、上位5名に選んでいただくことができました。ちょっと大きな場所でプレゼンするチャンスを手にしたので、ミズノの所属部署の役員の方に「プレゼンを見に来てくれませんか?」とお願いに行き、見に来てもらえることになったんです。
そのときのアイデアは「左右で別サイズの靴が買えるサービス」というものだったのですが、優勝はできなかったものの、見に来てくれた役員からは「対外的に評価されているんだったら良いサービスになるかもしれない。やりたいなら自分で進めてみなさい」と言ってもらえました。ミズノのシューズ部門の役員にもつないでいただき、ミズノの中の新規事業候補として進めて良いという扱いになったんです。
ただ、ミズノの中で事業化しようとすると、なかなか思い通りに進みませんでした。というのも、商品の品番をどうするか?という問題がついて回るんです。普通、靴に品番をつける際は、左右合わせて一足として品番をつけます。右足品番、左足品番というつけ方はしないので、商品を管理する既存の仕組みをすべて変えるか、まったく新しい仕組みをつくるかしかありませんでした。
私自身にそんなリソースはなかったですし、ミズノとしても経済合理性がないのでそのような意思決定はしません。「前に進めてみなさい」と応援してもらったものの、少しも前進しませんでした。本業というか、本来の事務局運営の仕事もありますし、「いよいよやばいな」という感じでした。
前に進まないまま時間だけが過ぎていくので、違う動きを取ろうと思い、また外部のコンテストに出してみたんです。そのときに応募したのは経済産業省が主催するアクセラレータープログラムです。応募者のうち100名ほどが採択されて、上位20名に入ると研修でシリコンバレーに連れて行ってもらえるという特典がありました。
ありがたいことに上位20名に選んでいただき、事業計画のブラッシュアップをサポートしてもらいつつ、シリコンバレーに行くことができました。2022年の7月のことなのですが、そこで大きな衝撃を受けたんです。
現地に行って感じたのは、シリコンバレーの空気感というか、雰囲気みたいなものです。「FOMO(※)」という言葉があるのですが、みんなその言葉をまとっている感じがしました。
(※)FOMO:Fear of Missing Outの略。最新の情報に触れ続けていないと取��り残されてしまう、成功のチャンスを逃してしまうという意味。
話を聞いてみると、この「FOMO」がシリコンバレーの精神ということでした。知ってさえいれば機会を得ることができたのに、知らないためにチャンスをものにできない。それって、一度しかない人生の中で最も恐るべきことで、みんな機会を得るためになんでも勉強するし、チャンスを得たなら何回失敗したとしてもモノにできるようにチャレンジし続ける。こういう考えをベースに生きているということでした。そういう話を聞きつつ、「果たして自分はどうだろう?」と自問したりして過ごしていました。
同じカリフォルニアにあるスタンフォード大学の話も印象的でした。スタンフォード大学のビジネススクールには「Change Lives, Change Organizations, Change the World」というポリシーがあるということで、シリコンバレーのイノベーションにも大きな影響を与えているそうです。
そのときの私は、ミズノで新規事業プログラムの運営をしていたこともあり、ミズノという会社自体が新しいことにチャレンジすることはとても価値があるし、チャレンジする人を増やしていくことを通じて、組織を変えていく必要がある。そういうことを強く思ったんです。
ただ、スタンフォードのポリシーの話をよくよく聞いてみると、「Change Lives」が最も大事だということでした。「いまの立ち位置や軸足を変えて、まず自分自身が変わること。それを持って、組織を変えていく。この順番じゃないとダメだ!」という話で、けっこうガツンと来ましたね。
新規事業プログラムの運営として、みんなが挑戦できる風土づくりとか一生懸命やってきたつもりだったんですが、まず私自身がもっと深く踏み込んで、やりたいことに全力で取り組むことが重要だなって思ったんです。

自分で考えた事業アイデアは前に進んでいない。本業があるので中途半端になっているかもしれない。「コミットできていない」と反省しました。まずはこの状況を抜け出すために、環境を変えなきゃいけない。そう思って、日本に帰る飛行機の中で「これまでとは違うことをやろう」と決めたんです。そのための具体策として、出向起業の仕組みを使って起業するという案がありました。
出向起業の促進は経済産業省の政策�プログラムで、簡単に言うとスタートアップ創出を加速させるためのものです。
大企業の社員が籍を残しながら起業することで、給与や社会保険などが保証され、経済的なリスクを抑えてチャレンジができます。それに、申請をすれば経済産業省から補助金が出るので、起業後の事業資金にあてることができます。
出向元の大企業にとっては、起業した社員が成功すれば事業上のシナジーがうまれるかもしれません。仮に起業がうまくいかなった場合でも、引き続き社員として雇用ができます。その場合、戻ってくるのは、自ら起業し、経営を経験してきた社員です。既存の育成スキームでは育たなかったような人材になっているので、社内に大きな刺激を与え、組織風土の活性化が見込めます。
私はミズノという会社が好きでした。だから、退職して独立するよりも、関係性を維持できる出向起業のほうが良いと考えたんです。
そこで、経済産業省の出向起業用の補助金相談窓口に「やりたいのですが、どうすればいいですか?」と相談に行きました。すると、「出向起業するにはいまの会社の許可が必要になります。許可を取るにあたっては下から意見をあげていってうまくいった事例を見たことがありません。まずはあなたが知っている社内で一番偉い人に相談することをおすすめします」とアドバイスをくれました。
偶然にも、私が事務局をやっていたミズノの新規事業プログラムのオーナーが社長で、数ヶ月に一度、進捗の報告をかねて面談の時間をいただいていました。面談のアジェンダはすべて私が決めていたので、そこに差し込もうと思ったんです。

面談ではいつものように新規事業プログラムの進捗を報告し、最後に「後日、別件で1時間だけお時間をいただけませんか。出向起業を考えていて、当日は経済産業省の方や補助金の事務局の方にも同席してもらいます。私のやりたいことを聞いていただきたいです」とお願いしたんです。
社長は快諾してくださり、後日、改めて自分のやりたいことと出向起業の詳細を説明しました。すると、「そこまでやりたいなら、チャレンジしてみればいい」と言っていただけました。
社長の了承が取れたので、すぐに私の部署の役員のところに行きました。「事後で申し訳ないのですが、、、社長とこういう話になりまして、どうにかなりますか?」と相談すると、「いろいろ手続きが必要になりそうだから、人事の役員のところに行こう。一緒に来い」と。どんどん話が進んで行き、「今度の役員会で承認を取るから」となって、すぐに出向して起業することが決まったんです。
シリコンバレーから帰ってきたのが2022年の7月。そこから経済産業省に出向起業の相談に行き、社長にお時間をいただいたのが8月です。その場で社長の了承を取り、その7日後の役員会で出向の承認がおりました。そこから起業の準備を始め、10月の終わりには法人登記が完了しています。
ミズノとしても、社内で新しいチャレンジが出てくることを促進したかったのだと思いますが、異例だと思います。私のやりたいことを聞いてくださり、すごいスピードで前に進めてくださったことには感謝しかありません。
ただ、起業にあたってはいろいろな申請や手続きがあって本当に大変でした。経済産業省に出す補助金の申請書類をつくりつつ、法人登記の作業を進めながら創業融資を得るために金融機関をまわる日々でした。なんとか融資が決まっても、「法人口��座がないので振り込めません」と言われてしまい、そのときはミズノの経理に相談して銀行さんを紹介してもらって、なんとか法人口座をつくるみたいな(笑)。
バタバタだったのですが、さまざまな手続きを終えて、2022年10月26日に株式会社DIFF.を設立したんです。
左右別サイズで靴を売る。そして、ECという形でWebで売る。これは決めていました。しかし、自分でWebサイトを作れるかと言うと、つくれない。なので、仲間が必要だと考えていました。ただし、立ち上げたばかりの自分一人の会社で採用するには、どうすればいいかわかりませんでした。
とはいえ、悩んでいるだけでは何も変わらないので、発信することにしたんです。「こういう課題を解決したくて会社を立ち上げました」と、当時フォロワーゼロのXアカウントにポストしました。それをたまたま拾ってくれた人がいたんです。
その人は「なんかおもしろいことをやっていますね」とリアクションを返してくれました。興味を持ってもらえた�ことが嬉しくて私からもメッセージを返してやり取りしてみると、京都に住んでいることがわかりました。そこで、「私は大阪なのですが、近いので食事でも行きませんか?」と誘ってみたんです。
食事しながら話していると、彼が新卒で入社したのがアシックス商事だということがわかりました。靴を扱っていた経験があるし、流通についての知識も持っていたんです。そこから転職して、Webのコンサルティングを経験していて、「いまはデザイン会社で働いている」ということでした。
彼の経歴を聞いて、「要件が揃った!」と思いました(笑)。彼も私がやろうとしていることに興味を持ってくれていたので、「一緒にやりませんか?」とお誘いして、最初は副業で手伝ってもらうところから始めたんです。その彼が、現在のCOOの高橋です。

初めて会ったのが11月で、「12月の頭からは一緒に動けるようにしましょう」という話になり、ネックだったWebサイトづくりが動き出しました。
おっしゃる通りで、個人的にも運が良かったと思います。その流れで年末にはベンダーを決め、2023年の年明けからECサイトづくりを始めました。
並行して検討したのが、オペレーションです。たとえば25cmと26cmの靴を仕入れ、片方ずつを組み合わせて販売するとしても、そのオペレーションをどうするのか。市場に出ているものはすべて両足セットで管理されているので、左右それぞれに品番を振り直すのか。ECで受注を受けようとすると、どうしても個別に品番を振る必要があります。それをどう進めていくのか。そういった細かいですがとても重要なテーマを、COOと一緒に詰めていきました。
オペレーションの検討が終われば、次は集客です。左右別サイズの靴を履くこと自体が世の中的には認知されていません。加えて、私たちは立ち上げたばかりの会社なので知名度もありません。だから、告知用のランディングページをつくっても、ほとんど反応がありませんでした。
ECで商品を買うときは、クチコミを参考にしたりしますよね。そんな中で、私たちのサービスは知名度ゼロ・実績ゼロだったので、怪しく見えていたと思います。「本当にちゃんと商品を送ってくれるの?この会社大丈夫?」という感じで。最初に買ってくださった方にヒアリングしたのですが、「最初は詐欺サイトかもしれないと思いました」と言っていましたから(笑)。
2023年にECサイトをつくり始め、ランディングページで告知を出し、スポットで小売店さんと連携した「足のサイズ計測イベント」をやったりしながら、2024年の2月ごろにECサイトをオープンし、『D!FF.ONE』というネーミングで片方ずつ靴を買えるサービスとして展開し始めました。
2024年10月ごろからは、並行して3Dプリンターを使ったシューズ事業の構想も始めていきました。以前、『MAKERS』という本を読んだことがあるのですが、その本には「すべてのモノづくりは個別最適化されていきます」ということが書かれていました。この内容は、新卒のころからずっと頭の片隅に残り続けていました。
技術の進化に伴って、従来の金型と製造ラインを使った同一規格を大量生産するモノづくりから、デジタル技術を活用した個別最適化されたモノづくりへ変わっていく。たとえば、3Dプリント技術を使うことで、その人の足の大きさはもちろん、足幅や甲の高さを正確に計測し、自分の足にピッタリ合った靴をつくることもできます。
「モノづくりが個別最適化されていく世界になっていくんだろうな」とは思っていたものの、最初のユーザーはどういう人だろう?と考えたときに、なかなか具体的なイメージを持つことができなくて、関心ごとのひとつとしてずっとストックしていたんです。

その後、起業後に知り合った方のなかに足の課題に詳しい方がいらっしゃいました。糖尿病患者の方々の靴事情について教えてもらう機会があり、詳しく話を聞いてみると「整形靴」という足のトラブルを抱える人のために医療目的で作られる靴があり、職人さんがフルオーダーメイドでつくっているとのことでした。15万〜20万円くらいの非常に高価なもので、保険が適用されるということでしたが、それでもけっこう高いですよね。この課題を、デジタル技術を活用して解決できるんじゃないかと考えたんです。
足の形をスキャンし、3Dプリンターで出力する。そういう自動設計技術をつくることができれば、これまでよりも安価に、足のサイズや個人の状況にあった靴を提供することが可能になります。
大量生産するための設備であれば大きな生産拠点が必要ですが、いまは3Dプリンターも進化していますから、大きくてもコンビニくらいのスペース、小さければ6畳ほどのスペースで靴の製造が可能です。
靴は「ソール」などいろんな部材があり、それらを組み合わせていきますが、すべての素材をひとつの場所で設計する必要はありません。素材データを別々の場所でつくり、そのデータを出力用のマシンで受け取れば、靴はつくれます。このように「靴のつくり方」を変えることで、新しい価値を提供できると考えているんです。DIFF.でもテスト用に3Dプリンターを購入し、いろいろと試行錯誤をはじめました。
そうですね。『D!FF.3D』というもので、足の機能を守る3Dプリントシューズ事業です。資金調達を実施し、医療分野への新規参入を発表しました。
そして、左右別サイズの靴販売事業は、いったんこれ以上拡大を目指さないという意思決定をしたんです。事業そのものをなくすのではなく、3Dプリントシューズ事業にリソースを集中させるということです。
これは本当に悩みました。左右別サイズの靴販売は、ニーズはあるものの事業としてスケールするのに時間がかかりそうでした。大規模なプロモーションを行ない、認知度を上げればいまよりも売上を伸ばすことができる。しかし、プロモーション予算を準備するのは簡単ではありません。
また、今後、靴が個別最適化された時代がくると信じていますが、一般の消費者がすぐに3Dプリンターでシューズをつくりはじめる流れは予想しにくいです。「3Dプリントシューズの世界市場は拡大傾向にあり、成長角度が高い」という予測があるものの、日本で一般的になるまでは時間がかかりそうでした。つまり、多くの一般消費者の中には「自分の足のサイズにピッタリと合う靴じゃなければいけない明確な理由がない」と考えたんです。
これらの状況を踏まえて、3Dプリントシューズ事業にリソースを集中させる意思決定をしました。そして、段階的な事業推進方針を立てたんです。
この事業の出発点は医療分野への参入でした。一方で、これまでは一般の方の足の悩みや課題に目を向け続けてきました。これらを包含した結果、改めて一般消費者向けに3Dプリントシューズを提供するところから始めようと考えました。
創業当時は「足の形の左右差」に着目し、左右別サイズの靴が買えるソリューションを提供していました。足と靴に悩みを抱える方々と直接会話し、足型を計測していくうちに、形の左右差だけではなく、特徴的な形を持つ方とお会いする機会も多くありました。具体的には標準よりも足の幅が狭いとか、甲が高いというケースです。そういった方々は自分に合う靴がなかなか見つからずに悩んでいらっしゃいました。
まずは、そんな方々に向けて3Dプリントシューズを提供していきます。コンセプトは『パーソナルメイドシューズ』で、足型計測データから左右の違いや形の特徴を捉え、左右別に0.1mm単位で調整を行なって独自開発するものです。足長、足幅、甲の高さなどを5項目を調整でき、今後も調整項目を増やしていく予定です。
特徴は一度つくった靴を履いて過ごしていただいた後、得られた所感やデータをもとに2足目を開発できることです。これにより、1足目よりも2足目、2足目よりも3足目という具合に、どんどんフィット度があがっていき、靴を育てていく楽しみを提供できると考えています。これまでは人が靴に合わせることが当たり前でしたが、これからは靴が人に寄り添ってくれる感覚を得られるようになるはずです。3Dプリント技術を活用しますから、整形靴の1/5くらいの価格で自分に合った靴を手にいれることができます。
2026年2月のβ版提供開始を目指していて、予約受付を開始したところです。一般消費者の中でも足に悩みがあり、自分に合った靴と出会えていない方に向けてソリューションを提供し、ゆくゆくは医療分野にも進出していく方針です。

この方針に沿って、社内では3Dプリントシューズの試作を重ね、並行して開発チームづくりを進めています。義肢装具士という資格があるのですが、その資格を取るための教員をしている方に開発顧問で入っていただいたり、整形靴職人の方にも業務委託でジョインいただいていて、設計の自動化に向けて抑えるべきポイントの洗い出しを進めています。
医療分野に限らず、「自分に合った靴がない」という悩みを抱える人は多世代にいると思っています。そういう方々の声にしっかりと耳を傾けながら、事業開発を進めていく考えです。「こんなことに困っている」という方がいたら、ぜひ声を聞かせていただきたいですし、協力いただける方がいたら力を貸していただけるとありがたいですね。
そうですね。これまでの当たり前を変えていくことで、新たな価値を生んでいく。その活動自体に大きなやり甲斐があると思いますし、全身でやり甲斐を感じながら当事者の一人としてチャレンジを続けていく。そういう経営者でありたいと思っています。
靴の選び方、買い方にも、「これまでの当たり前」があると思って�います。シューズショップに行き、壁面に並んでいるなかから、自分の足にあっているであろうものを選ぶのが常識です。ただ、完全にフィットするものを見つけることは難しく、足が救われない人も多いと思います。
個人の足の形を起点にして、1対1で靴がつくられていく。デザインや機能が自分の好みに合うことに加えて、フィット感までも自分に合う靴が手元に届く。そんな世界にしたいと考えています。
もちろん私たちはまだまだ本当に小さな存在なので、自分たちだけで当たり前を変えることは難しいです。シューズの産業は非常に大きいですから、産業全体に影響力を持つためにも、同じ船に乗ってくれる仲間を少しずつ増やしていく必要があると考えています。
そのために大事なのは、「この領域でチャレンジするんだ!」というフォーカスを決めて、きちんと示すこと。そうすることで、DIFF.という会社に興味を持ってくださる方が増えていくと思いますし、今回の資金調達のように力を貸してくださる方が増えてくると思っています。
共感や共創を積み重ねていくことで、やがて大きなインパクトになり、それが新しい価値になっていくと考えています。いつになるかわかりませんが、靴の選び方が変わったり、個別最適化された靴づくりが当たり前になったときに、その中心にDIFF.という会社がいたらうれしいですし、そうなれる��ように挑戦し続けていきたいと思っています。


株式会社ディプコア ThinkD編集長
同社の社名には「DIFF」のあとに「.(ピリオド)」があります。これは、「身体的な特徴の違い(Different)から生まれる�悩みを解決し、終止符を打つこと」を意味しているそうです。これまでの当たり前を変えることに対する同社の強い意気込みが表れていると感じます。 シリコンバレーからの帰りの飛行機で自身を変える決心をし、そこから数ヶ月で起業まで持っていった清水社長。インタビューでは非常におだやかな語り口でしたが、決めたことは必ずやり抜く芯の強さをお持ちなのだと思いました。また、COOの方との出会いや、『D!FF.3D』の開発チームづくりにおいて各分野のエキスパートが続々とジョインしている事実をみると、他者を惹きつける強い磁力もお持ちなのだと感じます。 同社の取り組みは、いまはまだ小さな動きなのかもしれません。しかし、もしかしたら10年後には、左右別サイズの靴を履いていることが当たり前の世の中になっているかもしれません。
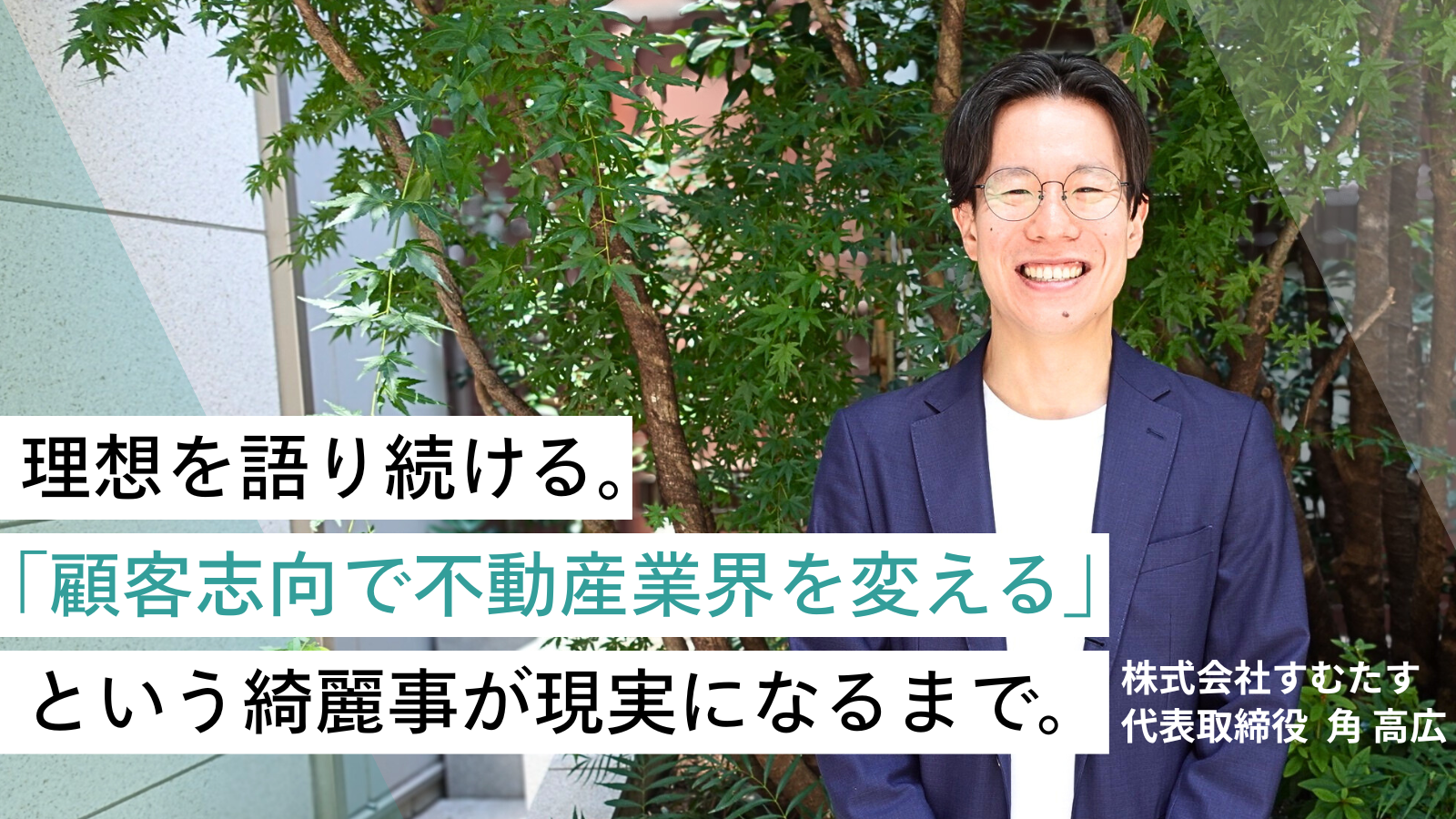
2025.09.22 公開

2025.06.30 公開

2024.08.01 公開

