
もう逃げよう───諦めかけたiCARE山田は、事業を立て直し、データを軸に新たな挑戦を続けている。彼を支えた信念と、彼が実現したい未来とは。
2025.09.30 公開

2025.09.30 公開
株式会社iCARE 代表取締役CEO 山田 洋太
設立:2011年
事業内容:産業保健・健康経営ソリューションサービスの開発・提供

インキュベントファンド株式会社 代表パートナー
山田氏は、人生�を賭け「働くひとの健康を世界中に創る」というPurposeに挑む起業家であり、社会に不可欠なインフラを創りうる革命家だと信じています。約10年前の投資当初、まだ「健康経営」という常識は存在しませんでした。革命前夜にある産業保健市場で、変化を楽しみ、一緒に未来を創る「同志」として、iCAREの扉を叩いてください。
日本の労働安全衛生市場は、働き方改革の進展や健康経営への注目度向上により拡大を続けている。厚生労働省の統計によると、2024年の労働災害による死亡者数は年間約800名、休業4日以上の労働災害は年間約13万件発生しており、働くひとの健康を守ることは喫緊の課題となっている。特に産業保健領域では、従来の事後対応型から予防重視型へのシフトが求められており、データとテクノロジーを活用した新たなアプローチが注目されている。
株式会社iCAREは、働くひとの健康をテクノロジーと専門家の力を掛け合わせて支援する産業保健領域のリーディングカンパニーだ。同社が提供するソリューションサービス『Carely』は、健康診断結果やストレスチェックなどの健康データを一元管理し、産業医や保健師などの専門家とともに企業の健康づくりを包括的にサポートしている。現在700社以上の企業で導入され、多くの働くひとの健康を支えている。
今回はそんな株式会社iCAREの山田洋太さんに、ThinkD単独でじっくりお話を伺った。
金沢大学の医学部を卒業して、沖縄県立中部病院で研修医として働き始めました。そして、3年目のときに院長と喧嘩になったんです。
当時は20名くらいの同期を合わせて40名ほどの研修医がいたと思うのですが、私たちは研修医の扱いが雑だと感じていたんですよね。みんな不満がたまっていて、たまたま私のところにみんなの不満が集まってきたので、私から病院長に話しに行ったのですが、うまく伝えられなくて。
当時は若かったこともあって、組織のトップが何を考えているのかよくわからないじゃない�ですか。それに対する反発心というのもあって、現場の文句というか意見を伝えに行ったら喧嘩になってしまって。「こんな病院出て行ってやる!」と仲間と一緒に久米島の病院に移ったんです。

ちょうど久米島にいた7名の医者のうち6名が辞めるというニュースを見ていたので、「ニーズがあるだろう」と思い、4〜5名の仲間と一緒に久米島に行きました。
当時は飲酒運転の罰則がいまほど厳しくない時代だったので、けっこうな頻度で事故が起きていたんです。飲酒運転の事故が起きて、その救急患者がどんどん運ばれてくるみたいな感じでした。
あと、久米島では毎年10月に久米島マラソンというのが開催されるのですが、10月でも沖縄は暑いんですよ。ただ、それを知らない島外から来た人たちがマラソンに参加して、熱中症でどんどん運ばれて来ていました。そこに混ざって、おじいやおばあが心筋梗塞で倒れて運ばれてきたりして、イベントのときはもうカオスでしたね。そんな環境で2年くらい働いていました。
同時に、医師としてのやり甲斐を実感できたのも久米島でした。久米島町で肺炎の予防を進めたことがあったんです。助成金を活用して、おじいとおばあを中心にワクチンを接種してもらったんですけど、やり始めた次の年からはちゃんと肺炎が減ったんですよね。予防をすれば、ちゃんと成果につながるんだってことを実感できた出来事でした。
改めて「予防って大事だな」と思うようになり、体の具合が悪くなってからそれを治すのではなくて、具合が悪くならないように日々の生活から見直せばいいと考えるようになったんです。そこからは、病院に来た患者さんを診察する以上に、みんなの普段の暮らしを見に行くようになりました。
まずは久米島での経験が大きいと思います。健康って、日々の生活の積み重ねなので、生活に問題があったら結局病気になるんですよ。そういう人って、治療して退院しても、やっぱり戻ってくるんです。それを繰り返していると、だんだん虚しくなってくるんですね。
その虚しさの根っこは何だろう?と考えていくと、その人の生活を変えられなかったことなんです。おこがましいかもしれませんが、普段の生活に潜んでいる病気の種みたいなものを、私たちは見つけることができると思っているので、生活を変えないとずっと同じことの繰り返しじゃないですか。だから、�予防に力を入れているんだと思います。
あとは、関東に戻ってきてから、心療内科を始めたことも理由のひとつだと思います。もともと私は内科が専門なのですが、内科をやっているときにうつ病の患者さんがたくさん来ていたんですね。多くは仕事を持ち、働いている人たちでした。

みなさんが口に出すキーワードが「産業医」だったんです。「産業医の先生に言われて」とか、何度も何度も産業医という言葉を聞きました。なかにはけっこうひどい症状になっている方もいたので、「ここまで放っておくなんて産業医の先生は何をやってるんだよ。全然予防できてないじゃん。ちゃんとやれよ!」って感じていたんです。
そこから産業医に興味を持ちました。いろいろ勉強していくと、うつ病という病気がその人のプライベートの生活とは別の場所で発生していることがわかりました。つまり会社です。だったら「会社での様子をちゃんと見ておくことで、働くひとの心の健康が守れるんじゃないか」と考えるようになったんです。
怒りというよりも、不思議さなのかもしれません。純粋に「なんでそうなるの?」と思いますし、その理由が知りたくなるんです。私は物事の根本がどうなっているのかを確認しに行って、問題があるならどうにかして解決したいタイプなんだと思います。
久米島から関東に戻った後、経営のことを勉強するために慶應大学ビジネス・スクール(KBS)に通い始めました。なぜかというと、離島僻地の医療にはたくさん問題があって、その原因を知りたいと考えたからです。
わかりやすいのが病院経営の問題です。私が勤めていたのは、島民のためにつくられた公立の病院でしたが、島民の75%くらいは沖縄本島の病院に行くんです。医師の人数も確保しているのに、私たちでもできるのに、久米島の人たちはより良い医療が受けられると思って、わざわざ25分かけて那覇まで行くんです。
久米島の病院はどんどん経営が苦しくなっていきます。すると、久米島町から病院に億単位の調整金が来るんです。これってすごく不健全だと思ったし、何かおかしなことになっていると思いました。だから経営を学ぼうとビジネス・スクールに通い始めたんです。
心療内科医のときは、うつ病の患者さんが口にする産業医の先生が、なぜうつ病を予防できないのか原因を知りたくなったんです。
私は、文句や愚痴は言うけど自分では何もしないというのがものすごく嫌いなタイプです。だから自分でも勉強して、産業医になりました。働くひとの健康が損なわれていると感じましたし、それを解決したいと思ったからです。

だから、問題が起きていることに怒りを覚えるというよりも、問題が起きた背景が気になりますし、どうすれば問題を解決できるのかをとことん突き詰めていきたい。そういう性分なんだと思います。
ビジネス・スクールで学び、心療内科の医師としても働きながら、働くひとの健康を守りたいと考え、2011年に創業したのが株式会社iCAREになります。ビジネス・スクールでMBAを取得することと並行して、浦安にある病院の経営再建に取り組みつつ、サービスづくりの準備を進めていきました。
健康は価値観なんだと思っています。人生観や死生観、それにその人の生き様と言っても良いかもしれません。「こうありたい」と本人が望む状態でいることが、その人にとっての健康なのではないでしょうか。
たとえばですけど、じゃがいもが大好きで、「毎日じゃがいもを食べたい」と本人が望むなら、太りすぎで体重が120kgだったとしても私は止めないです。じゃがいもをおいしく食べる毎日がその人にとっての幸せな日常だと思いますから。
一方で、突然の心筋梗塞で胸が苦しくてしょうがない、生きるか死ぬかというときは、申し訳ないですがその人の価値観なんて関係ありません。心筋梗塞になった時点でその人が大切にしたい日常ではなく非日常に突入しているので、どんな状況であっても助けに行きます。
手術が必要な場合、同意は取りますが、たとえ同意が取れなくてもその人を救うためであれば手術をする可能性があります。身体にメスを入れるってすごい行為ですけど、命を救うためならその行為が許されているのが、医師という職業なんです。
これは、働くひとに対してもまったく同じだと思っています。心療内科で働いていたとき、私は「クリニックに来たその人」のことしか知らないんです。
具合が悪くても、本人は「いまの仕事をがんばりたい」「弱音を吐いちゃいけない」と思っているかもしれません。毎日仕事をがんばることや、できるまで素直にやり続けることも大切ですが、本人の価値観なんて関係ない緊急事態が会社で起きていたら、それは健康を損なう要因になります。
どのように生きるかはその人の価値観なので好きにすれば良いです。仮に、太りすぎで健康を害したとしても、ある人にとっては大好きなじゃがいもをたくさん食べることができて幸せだと思いますし、ほとんどの医者がそれで良いと言うはずです。
しかし、唯一否定されることがあります。それは、仕事で健康を損ねることです。「仕事を通して健康を損ねることは良いことですか?」と質問したら、世界中の医者が口を揃えて「NO!」と答えると思います。「健康はその人の価値観です」というベースの認識がありますが、その中で唯一の例外が仕事で健康を損ねることなんです。
ちなみに、世界中で、どれくらいの方が、何を理由に亡くなっているかご存じですか?WHOやILOの2023年報告から、公表値をもとにまとめてみたところ��、最も多いのが心筋梗塞で約910万人、脳卒中が約680万人、慢性閉塞性肺疾患が約360万人、それらに対して労働災害や職業性疾病が約293万人です。仕事を通じて健康を損ね、世界中で毎年数百万人が亡くなっています。働くことって危険を伴うことであり、だからこそ世界中の医者が仕事で健康を損ねることに対して「NO!」と言うんです。

産業医として働いていたときに、企業のアナログな健康管理業務を目の当たりにしました。従業員の方の健康情報もブラックボックス化していて、仮に不調が起きても、すぐに気づくことは難しい。人事担当者は日々の業務に追われていて、データを活用した施策なんか考える余裕がない。そんな状態に危機感を持ったんです。
そこで、産業医や産業保健看護職といった働くひとの健康を支える専門家の方々に対して情報を一元化できる電子カルテのようなサービス『Catchball』を開発しました。
簡単に言うと、働いている人の状態を可視化するものです。仕事をがんばっているときって、自分では気が付かないうちにやりすぎていることがあります。本人は��「まだまだいける!」と思っていても、客観的に見たら「ちょっとがんばりすぎ」という状態です。本人はわからないので、誰かが止めてあげなきゃいけない。
ボクシングだと、選手は「まだいける!勝つぞ!」とファイティングポーズを取り続けるんですけど、セコンドがタオルを投げ入れたりしますよね。あれは、そのまま試合を続けると危険だからです。セコンドは長年の経験からタオルを投げる判断をするわけですが、働いている人に対してその判断をしやすくするための仕組みとして開発したのが『Catchball』です。
従業員の健康状態を可視化し、異常値が出れば自動的に産業医にアラートを出すというもので、産業医の業務支援クラウドサービスとして2013年にリリースしました。
ただ、これがまったく売れませんでした。最初の半年で売れたのは1社だけ。覚えているのは、共同創業者と赤坂の交差点で「もうやめようかな」と言ったことです。せっかくリリースしたのに売れないと虚しいじゃないですか。会社の通帳からどんどんお金がなくなっていって、残高がもう数万円しかない状態でしたし、「もう終わりにしよう」と思ったんですよね。
でも、ビジネス・スクール時代の同級生が「俺も手伝うからもう一度やってみようぜ」と言ってくれて。それでなんとか持ちこたえたという感じです。
理由はいくつかあって、たとえば開発力です。プロダクトをつくる際に、十分な開発力を確保することができませんでした。それに、プロダクトアウトでつくってしまったことも理由のひとつだと思います。私が「良い」と思っているものを形にしてしまったんです。本来なら、顧客のニーズをつかんで課題を解決していくものじゃないといけません。
あとは、ちょっと早すぎた、ということもあると思います。リリースした当時はまだ「働き方改革」という言葉が出てくる前で、世の中的にも長時間労働とか過度な残業が散見されているころでした。
これらの反省を踏まえて、リベンジしていくことになります。まずは、資金調達をして、仲間を増やしていきました。そして、働くひとの健康を守るというコンセプトはそのままで、テクノロジーと専門性を掛け合わせるサービスをつくっていったんです。
『Catchball』はクラウドで従業員の健康状態を可視化するものでした。それぞれの従業員の情報を収集する手間を省略し、異変に気づきやすい仕組みをサービスとして提供していました。でも、顧客が本当に実現したいことって、��従業員の健康を守ることなんです。
なので、情報の収集や整理といったデータ領域をクラウドが担い、得られたデータを活用する部分は専門家がサポートする。そういうコンセプトでサービスづくりを進めて行きました。
その後、2016年に提供開始したのが『Carely』です。最初はSMB向けの健康相談サービスとしてリリースしました。従業員が保健師や心理職(※)にチャットで相談できるという形式です。
(※)心理職:心理学の専門知識や技術などを用いて、心の健康を支援する専門職の総称。
ストレスチェックや健康診断のシーズンには、投稿される相談の量がすごく増えてしまって、対応する私たちがどんどん疲弊していくという感じでした。でも、従業員の方の健康に関する不安とか、職場での悩みに直に触れることができたので、やりたいことに向かって前進している実感はありましたね。

ところが、産業保健関連市場と呼ばれる「働くひとの健康を支える」という市場に、大手が参入してきたんです。SMBの領域で価格破壊が始まり、別軸で進めていた産業医の紹介事業は半年間新規案件ゼロになりました。「��やばい、このままじゃ生き残れない」ということで、今度はエンタープライズ向けに一気に舵切りをしたんです。
エンジニアチームを組織再編して、エンタープライズ向けにSaaS主体のサービスに切り替えていきました。2019年ごろだったと思いますが、当時はSaaSがブームでしたし、テクノロジーを活かしたSaaSをメインサービスにして、その上にオプションで産業医紹介や専門家のヒューマンなサービスを置いたんです。
そうですね。UI/UXを評価してもらったり、「テクノロジーに加えて専門家のヒューマンなサービスがあるのは安心」と言ってもらえたり、ある程度うまく行ったとは思っています。でも、SaaSサービスなので、最終的にはコモディティ化していくんですよ。
スペックの強みなんて、どんどん薄まっていきます。「この機能がある・ない」なんて、なんの差別化にもなりません。顧客体験がどう変わるかが差別化になるはずで、機能の違いなんてほんとに微々たる違いですから。
そういうことに気づかず、私たちは大失敗をすることになります。というのも、顧客の課題を解決することが目的なのに、SaaSサー��ビスを売ることを目的化してしまうんです。ここから暗黒時代に突入していきます。
時期でいうと2020年から2022年くらいで、世の中的にもSaaSの市場が一気に大きくなったころです。資金調達も、この3年で35億円くらい調達しました。そこで、ベンチャーキャピタルに対する考え方も変わりましたし、経営者としての強烈な反省もあったんです。
資金調達をすると、投資家たちは「ふたつのことに金を使え」と言います。ひとつ目は広告宣伝費です。SaaSブームなので、ひたすらアクセルを踏めと。当時年間で数億円くらい使っていたと思います。メディアにもたくさん出ていたのがこの頃です。
ふたつ目は人の採用です。SaaSのビジネスモデルはアメリカ式なので、細かくチームを分けて、それぞれの生産性を高めようというコンセプトなんですよね。その代わり、KPIはシンプルになるから、それぞれの評価はしやすい。すごくアメリカっぽいじゃないですか。
さらに言うと、チームを細分化すると、各チームに多くの人員が必要になります。これがSaaSビジネスモデルのマイナスポイントだと思います。2022年のピーク時までは毎年2倍近いペースで従業員や業務�委託が増えていったんです。
そのころにアメリカでSaaSバブルが崩壊するんです。
「ITやSaaSって、思ったよりも利益でなくないか?」とか、「Jカーブ(※)なんて、実はまやかしじゃないか?」とか、アメリカの投資家たちが言い始めるんですよね。
(※)Jカーブ:時間の経過とともに「一時的には低下し、その後急速に回復・上昇する」という現象や理論のこと。アルファベットの「J」に似ているため。スタートアップ企業が初期の赤字から急成長を遂げる成長パターンなどで使われる。
アメリカでSaaSバブルが弾けて、その影響が日本にもバーっと押し寄せるわけです。すると投資家は「従業員が多くないですか?なんでこんなに大きな組織なんですか?」って言うんですよ。
組織を大きくすることも、ましてや小さくすることも簡単じゃない、雇用している私の立場として怒りを覚えました。
ただ、そういうときって事業もうまく行っていないんですよね。数字に追われて押し売りが目立ちはじめるとお客様がどんどん離れていき、結果として事業の成長率が5分の1以下に落ち込みました。
社内に目を向けると、従業員同士ですれ違う人の�ことを知らないことが増え、とにかくKPIを達成しよう!ばかりを言われて、何のために仕事をがんばっているのかが見えなくなる。いろんな問題が起きて、それぞれの問題がどんどん大きくなって、すさまじい勢いで社内が混乱していきました。

すると今度は、投資家から「山田さん、どうやってこの責任を取るんですか?」と言われるようになりました。ただ、そのときの私は目の前で起きているさまざまな問題に対して、どう対処すれば良いのかわかっていなかったんです。偉大な経営者の本を引っ張り出してきて、あわてて答えを求めるものの、本に書いてあるのは多くの修羅場を乗り越えてたどりついた経営者としての境地です。修羅場に直面していた私にとってのヒントを見つけることはできませんでした。シンプルに、実力不足だと思いました。
もう最悪の状況でした。いまでも覚えていますが、2022年12月16日の夜、家で布団に入ろうとしたときに「もう逃げよう」と思ったんです。ちゃんと考えられないというか、とにかく目の前の状況から逃げ出したかった。いま思うとメンタル不調だったと思います。
そこからどうなるかと言うと、頭の右後ろくらいから声が聞こえてきたんです。「最後くらいワガママ言ってから辞めなよ」って。それで「ハッ!」としたんです。
確かに、理想に向けて私はいろんなことを抑制していたんです。経営の本に権限委譲が大事と書いてあったから、みんなに任せたりしていましたし、社員とご飯に行きたくても一部の人だけだと不平等になってしまうからがまんしていました。自分のワガママは押し殺して、そういった王道の経営にできるだけ忠実にやっていたんです。
でも、「ワガママ言ってから辞めなよ」という声が聞こえてきたので、次の日にさっそく社員に声をかけて、飲みに行ったんです(笑)。
これで吹っ切れた私は、社内に有事宣言を出しました。
「お客様が離れていて、成長率も鈍化している。なので、いまこの会社は有事です」ということをみんなに宣言しました。あわせて、「状況を変えるために私は現場に降りていきます。組織も変えます。KPIも変えます。みんなと一緒に会社を良くするために一生懸命がんばるのでよろしくお願いします」と伝えたんです。そして、2023年1月から大改革を始めました。
まずは社内にたくさんあった部署を、できるだけシンプルにしたんです。セクショナリズムが発生していたので、まずはそれを壊してやろうと思ったんです。
次にKPIの見直しです。たとえばインサイドセールスのKPIを変えました。それまでは商談設定数が重要指標でしたが、それを捨てて、代わりに「お客様にもう一度話を聞きたいと思ってもらえるような架電件数」にしたんです。
インサイドセールスの仕事の定義を、「商談を設定すること」から「良好な顧客関係をつくること」に変えたんです。なので、お客様に架電したら「また電話してもいいですか?」と聞いて、「いいですよ」と言ってもらえた割合を取って欲しいと現場にお願いしたんです。
そうしたら、ありがたいことに、離れて行ったお客様がだんだん戻ってきてくれたんですよね。それを成功体験にして、次はこれ、その次はこれ、という具合にどんどん変えていきました。結局1年半くらいかかりましたが、組織の体質を改善することができたんです。
ちょっと定性的ですが、すごくわかりやすいのは、お客様からの評価ですね。私たちのSlackには『社外からのありがとう』というチャンネルがあるのですが、取引先でも、一個人の方でも、私たちの価値観に沿った形でお客様から感謝の言葉をいただいたら、どんなものでもいいから投稿しようという取り組みをしているんですね。エンジニアのみんなは普段お客様と接点がなかったりするので、「この機能最高でしたよ」とか言ってもらえたらすごくうれしいじゃないですか。そういうのをちゃんと見える化して、みんなで分かち合いたいと思ってつくったチャンネルがあるんです。
以前はお叱りの言葉が含まれていたりしましたが、少しずつ、少しずつ「こういう声をいただきました」とか感謝の声の割合が増えて行ったんです。
それを見ていて、やっぱり顧客と向き合い続けることが大事だなと思いましたし、お客様と良い関係性をつくることに軸足を寄せて良かったなと思いましたね。お客様の課題解決につながる提案をしていれば、それがちゃんと受注につながり、売上に返ってきます。改めて、「何のために事業をしているのか」をブラさないことが大切なのだと思いましたね。

いろんな方の支えと、社員みんなのがんばりがあり、なんとか事業を立て直すことができました。主力サービスの『Carely』は健康経営銘柄を含む700社以上に利用されています。お客様が抱える健康課題を解決するための仕組みを提供し、健康管理クラウドや産業医紹介、健康診断業務支援、コンサルティングなど、ラインナップも充実してきました。
テクノロジーと専門性を掛け合わせて顧客の課題解決に向き合う姿勢も崩していません。産業保健師は10名ほど、産業医は400名ほどが稼働しています。顧客の健康課題を解決し、それを企業の力に変えていくという取り組みを、今後も続けていこうと思っています。
まだ途中なんだと思います。私たちは同じ事業に取り組んでいるものの、従業員同士の業務や思考の違いを完全に混ぜ合わせることには、まだ難しさを感じているんです。たとえばクラウド開発している部門と保健師や心理職の部門とでは、その働き方も価値観も水と油のように異なっていると思います。
私たちはテクノロジーと専門性を掛け合わせることで顧客の課題解決と向き合おうとしていますが、その前提は水と油のように異なる専門性を持っている従業員同士が��ドレッシングのように混ざり切ることです。足し算ではなく相乗的なバリューアップになるように、どうにかうまいやり方はないかと、模索を続けている感覚が強いです。
リブランドです。サービスブランドを作り直したりとか、カルチャーやバリューを見直したりしています。
たとえば、カスタマーサクセスと呼ばれるチームは、クラウドサービスがメインでヒューマンサービスがオプションであると思いがちです。でも本当はそうじゃない。顧客の課題を解決するためには、業務効率を向上させるクラウドサービスは大切ですし、そこで得られるデータも非常に重要です。そして、得られたデータを活用する専門家たちがいるので、どのようにうまく連携して、データが活用できている状態を作り出すかに目線を持っていきたいんです。
そのためには、そもそも私たちの勝ち筋って何なのか?強みって何なのか?を改めて定義する必要があると考えました。だからリブランドなんです。
おっしゃる通りです。クラウドサービスがコモディティ化するのは決定事項なので、他社とは違う形で価値を提供するにはどうしますか?を考えなきゃいけません。そのためには、やはり水と油をうまくミックスしていくしかないと考えています。
たとえば、社員が健康を害してしまった企業に対しては、どうすれば同じことが起きないかを提案することが価値じゃないですか。私たちであれば、その企業の健康管理ルールを確認し、ルールを見直すことから着手します。アラートが出たときにどの手順で誰がチェックをするのか、就業判断の責任者は誰なのかといった仕組みづくりを最初にやります。それこそが私たちが提供できる最大の強みだからです。
課題を解決したいお客様にとっては、業務を効率的に進めるためのITサービスではなく、問題が起きない、あるいは起きにくい業務フローの提案こそが価値なんです。どういう仕組みだったら働くひとの健康被害を防ぐことができるのか。上流の企画設計が重要であり、そこにこそ私たちの強みがあると考えています。
サポートというよりはコンサルティングに近いので、顧客のニーズごとに専門的な人材を当てていく感覚に近いと考えています。ただ、難しいのが、専門性を獲得するのに3〜6ヶ月くらいかかることです。そのため、未来のニーズに合うように従業員の育成をしていくことの難しさが課題だと思っています。
自分たちができる工夫としては、専門性の学習をどうやって効率化していくかです。生成AIを活用し、学習の質をさげることなく期間を縮めるにはどうすればいいかを社内で検討しているところになります。
この取り組みを進めることで、社内に専門性を持った人材を増やし、いまよりも多くのお客様のニーズに対応できるようになります。お客様には課題の解決につながる提案ができますし、私たちにも売上として返ってくるはずです。

いろんなパターンがあります。常駐もあれば、週に数回とか、あるいはすべてオンラインとか。そこは、お客様が解決したい課題に合わせることになると思います。
もうちょっと詳細をお伝えすると、エンタープライズ企業に対しては、だいたい1社あたり2〜3名で担当することが多いです。これは個人の負担を分散させたいことはもちろん、分野における得意・不得意があるのでその凸凹をならすことが目的です。
専門家といっても保健師や産業医といった有資格者だけではありませんよ。業務オペレーションの企画設計が得意な人もいれば、休職・復職の実務遂行が得意な人もいます。ちなみに、休職・復職に関するルールがない会社もありますし、ルールはあるんだけれども運用がすごく雑な会社もあります。
たとえば、休職していた社員から復職可の診断書が提出されたら、会社としてのチェックなしで「OK、復職して良いですよ」と判断してしまう会社さんとかあるんですよ。そういう場合は、たいてい失敗します。復職した社員がすぐに再休職に入ってしまったり、十分に成果が出せず配置転換を余儀なくされてしまう。こうした事態を防ぐためにも、まずはしっかりとルールとフローを決めることが大事です。
「こういうときは、この診断書を出させてください」「ここから人事はこういう動きをしてください」「ここで産業医と�の面談を入れます」という具合に、しかるべきルールがあり、それを業務フローに組み込んでいくんです。
ルールの詳細に詳しい専門家もいれば、仕組みに落とし込むのが得意な専門家もいます。体調を崩した従業員の方と面談を行なって評価をすることが得意な専門家もいますし、お客様の人事と一緒になって施策を推進するのが得意な専門家もいます。私たちの強みである専門性を組み合わせて、サービスとして提供しているという感じですね。
前提として、ちょっと大きな話になりますが、日本はピープルアナリティクス(※)が本当に遅れていますよね。
(※)ピープルアナリティクス:従業員の属性やパフォーマンスなどのデータを収集・分析して、人事戦略の企画立案や意思決定に役立てる手法のこと。
たとえば、数年前にLinkedInで海外のHRの人たちの経歴を見ていたことがあったのですが、みんなピープルアナリティクスについてプロフィールに書いてるんです。「分析がで��きる」とか「データに基づいた戦略立案ができる」とか。一方で日本の人事はほぼ経験がない。時間的な余裕がないということもあるでしょうし、苦手意識があるのかもしれません。とにかく、ピープルアナリティクスがすごく出遅れているのが現状だと思います。
ここが出遅れると、社員の健康に関する分析とか、課題に対して先回りで策を打つとか、予防のための取り組みがどんどん遅れていきます。今後大きな伸びしろになるだろうとポジティブに考えつつも、まあ課題が多いと思うんです。なぜなら、データで物事を語らない限り、本当の組織戦略なんてできないはずで、ましてや施策の有効性を検証しようにもできないじゃないですか。
そのため、データをどのようにお客様にお届けし、そのデータが持つ力を活用して健康施策に使っていただくか。ここに私たちは注力していくべきだと考えています。だからiCAREの専門家にはデータアナリストがいますし、クラウドを利用する・しないに関わらずお客様にデータを活用していただくためのサービスも持っています。
未来を予測するという観点からは少しズレてしまうかもしれませんが、私たちがやりたいことのひとつとして、仕事と健康障害を紐づけることがあるんです。それぞれの仕事には、その仕事特有の健康障害があります。たとえば人間関係に悩みやすいとか、ハラスメントを受けやすいとか。
そういった仕事と健康障害を紐づけ、お客様に提供することで、人事部長やマネージャーは「こういうところに注目しておけば、この部署の健康トラブルを未然に防げるかもしれない」とわかりますよね。そういうデータを提供していきたいと思っています。
それはやるとしても相当遠い話だと思います。10年くらい先でしょうか。私たちはやはりBtoBで事業をしていますし、個人に健康を押し付けることはしたくないという考えを持っています。なので、プライベートと職場の両方のデータを活用して、個人に健康を提供したいとは考えていません。
ただ、他の企業とのコラボレーションという意味では、オムロン社が買収したJMDC社が保有している医療ビッグデータとiCAREが保有するデータとの親和性は高いかもしれません。彼らは健康保険組合などの健康増進を支援するためのデータサービス企業であり、私たちは働くひとの健康を守りたい企業なので、価値観が合うことに加え、シナジーが見込めるんじゃないかと思います。
さきほど成長率を最優先にした結果、会社がうまくいかなくなった話をしましたが、とは言いつつ、売上がすべてを癒すことも事実だと思っています。やっぱり事業が伸びることこそが、関わるすべての人を幸せにすると思うんです。
やはり事業を大きくしていかないと、『働くひとの健康を世界中に創る』というパーパスを実現できませんし、これが実現できないと自分たちの存在意義を失ってしまいます。それに世の中にはルールや仕組みがないから起きてしまう職場での事件や事故も、まだまだ残っています。それらを減らし、なくしていくことが、創業当時から変わらない私たちが果たすべきミッションのひとつでもあると思っています。
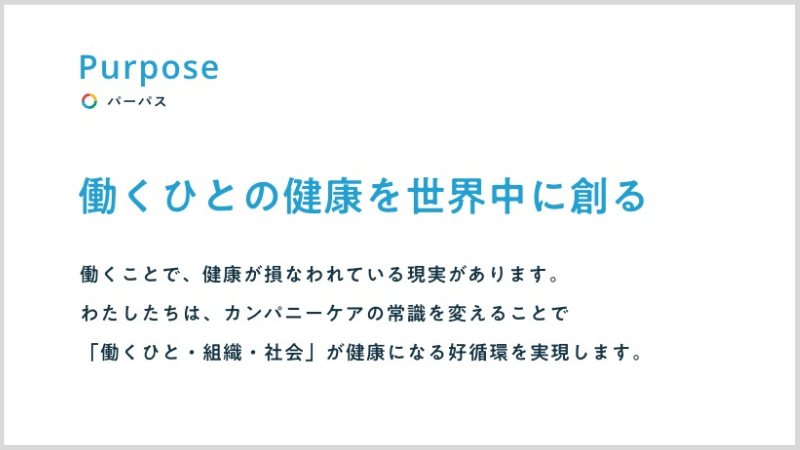
そう考えていくと、既存の事業を大きく伸ばしていくことに加えて、新規の事業を生み出し、育てていくことが重要です。経営者としては、もっともっと会社を成長させるためにがんばらないといけないなと思っています。
簡単に言えば、質に振り切るということでしょうか。2〜3ヶ月前から会社のみんなには「人は増やさない」と伝えています。なぜかというと、生成AIの力が圧倒的に強いからです。しかし、もちろんピンポイントでの採用は行なうつもりで、ここのクオリティにめちゃくちゃこだわりたいんです。
2022年まではたくさん採用する方針でしたが、同じ方針は一切掲げません。やっぱり新しい変化や新しい挑戦を好む人たちを、全力で採用していきたいと考えています。
たとえばインターネットがビジネスの現場に現れた頃には、「インターネットは使えない」と言っていた人たちがどんどん活躍できなくなっていきました。それと同じことが、AIにおいても発生していると思います。「AIは使わない」とか「AIは良くわからないからこれまでのやり方でがんばります」とか、そういう人は申し訳ないですけど、採用しません。少なくとも、これからのiCAREには必要ないです。なぜかというと、iCAREは、新しいことも含めて“顧客の課題をどうやって解決していくか”に取り組む会社なので。
もちろん簡単じゃないと思っています。聞いていると、どの会社さんもそういう�人材を求めているので、けっこう苦戦すると思いますし、難しいと思っています。でも、ここに本気でこだわりたいですし、そのためには条件面の魅力ももっともっと上げていくつもりです。
企業フェーズ的には、先行投資時期を終えて、投資の回収時期に入っていると思います。実際どうかと言うと、黒字化は進んでいますし、やり方次第ではさらに利益を出すことも可能という状況です。少し言い方を変えると、前のめりで「とにかく売上のトップラインを伸ばすぞ!」という時期から、効率良く、健全に事業を伸ばしていく時期に入っているということです。
そのため、働き方としても、とにかく目の前の業務を処理していくよりも、頭を使って、計画的・戦略的にムダをなるべく省きながら、少しずつ仕事の質を高めていく。そういうタイプの人がフィットする環境なのかと思います。
わかりやすい例のひとつがAIの活用ですね。ちなみにいま、取締役を中心に社内で生成AIの活用プロジェクトが着実に進んでいますし、「業務に落とし込めなかったら部長の評価を下げる」と伝えてあります。ピンポイントで外部から採用する人にだけいろんなことを求めるのではなく、自分たちもこれからのiCAREに求め�られる人材になれるように変わって行こうということです。
既存事業は効率良く、健全に伸ばしていきたい一方で、新規事業で新しい柱を立てていきたいと考えています。そのため事業開発に一緒に取り組んでくれる方も採用したいと考えています。お客様の課題もどんどん変化していきますから、これからもお客様の課題を解決する存在であるためにも、常に新しいサービスの検討を進めていくつもりです。


株式会社ディプコア 代表取締役CEO
働くひとの健康を支える同社のインタビューでは、いろんな話を聞くことができました。 働きすぎで体調を崩す方がいる一方で、働くことを規制され強いストレスを感じる方がいること。職種によって起きやすい健康障害があり、データを見ることでその傾向をつかめること。ただ、日本ではまだまだ労働関連データの活用が進んでいないことや、逆にこれからの伸びしろが大きいこと。 労働生産性の向上はこれからの日本に欠かせないテーマだと思いますが、ただガムシャラに仕事をすればいいということではありません。同社のような企業が提供するサービスを活用しながら、個々人や組織の状況を理解・把握しながら、正しく生産性を高めていくことが必要なのだと思います。 プレイヤーとしてがんばっている方はもちろん、多くの管理職の方に読んでいただきたいインタビューです。

2024.12.23 公開

2025.11.26 公開
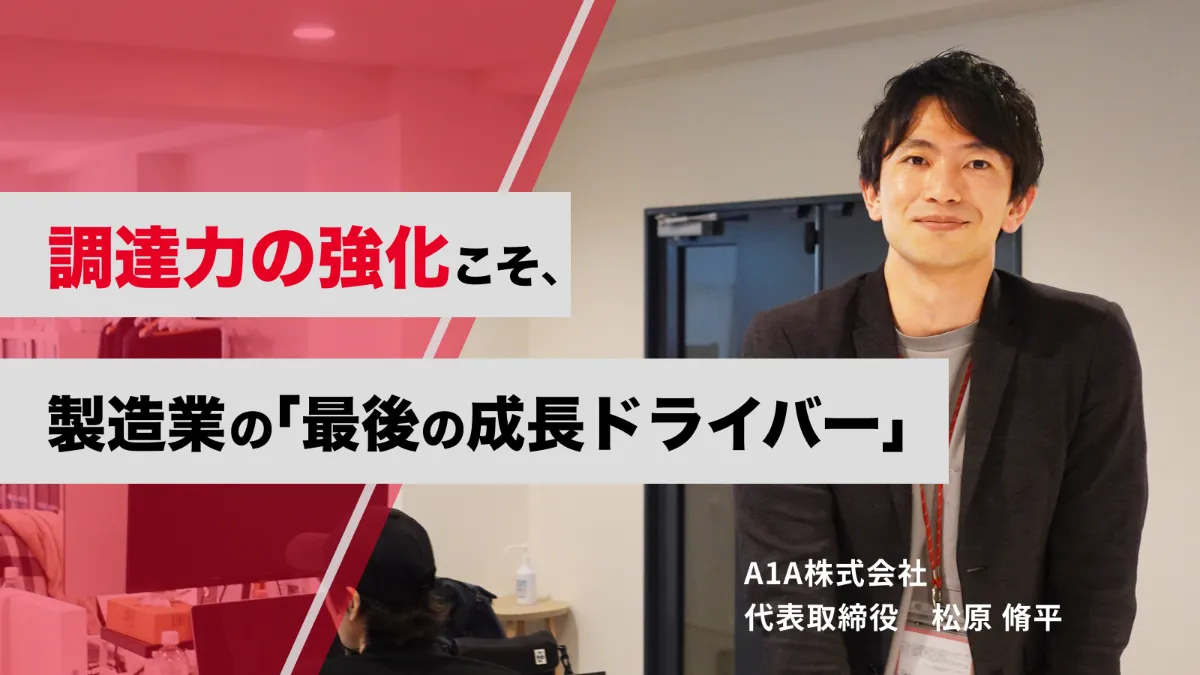
2024.08.05 公開
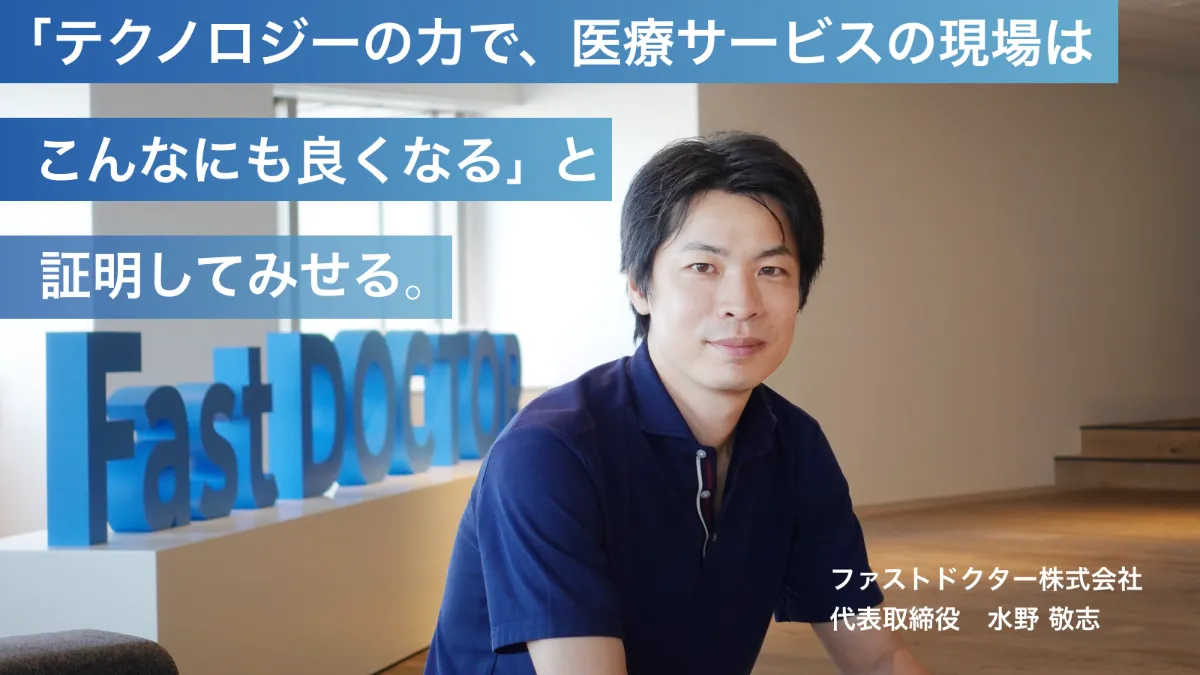
2024.08.01 公開

