
実感した「こんなはずじゃなかった」という子育ての現実を「やって良かった」に変えたい。テクノロジーを活用して子育ての不便解消を目指す逢澤の挑戦。
2025.04.04 公開

2025.04.04 公開
株式会社iiba 代表取締役CEO 逢澤 奈菜
設立:2022年
事業内容:子育て特化のマップ型プラットフォーム「iiba」の開発・運営

株式会社Nature Innovation Group 代表取締役
逢澤さんと作られているiibaというサービス含めて、"作りたい世界・未来"を信じて大事にしているからこそ生まれさらに発展していっていると感じております。その日々の改善の中にあるのはユーザーとの向き合い方で、逢澤さんが熱狂して向き合い、より良くされているのがとても伝わってきて推したい起業家でありサービスです!
京都で生まれて、関西で育ちました。大学では情報メディアについて学びましたが、新卒で就職したのは全然関係ないブライダルの会社になります。
大学を卒業してすぐ、22歳のときに結婚し、そのままブライダルの会社で営業職としてキャリアをスタートしました。24歳で長男を出産し、子育��てをしながらWebデザインのスクールに通ったりしていました。26歳のときに長女を出産して、その後リクルートに入社し、ホットペッパーの営業として働いていました。
子育てをしながら「こういうサービスがあったらいいのに」と感じることがたくさんありました。自分が欲しかったサービスをつくり始めて、それが会社になったという感じです。
そうですね。実際に子育てをやってみると、「思っていたのと違う」と感じることがたくさんありました。そもそも、私は子育てというものにすごく良いイメージを持っていたんです。これは、学生のときの病気の経験が関係していると思います。

私は20歳のときにギラン・バレー症候群という病気になり、重症化してしまいました。全身が麻痺して、自力で呼吸できない状態だったんです。2ヶ月間ずっと集中治療室にいて、身体は動かせないものの、意識はあって、音だけは聞こえるという状態でした。
生死の瀬戸際になると、私の場合は聴覚が研ぎ澄まされて、普段は聞こえないような音も聞こえるようになりました。視線は動かせないので見ることはできないのですが、病室の中の音から、「誰かにお見舞いが来ている」「今日の機械音は少し違う」などがわかるんです。お正月だったんですが、お餅をのどに詰まらせてしまったおばあちゃんがいて、ご家族の方がお見舞いに来ていました。
医療機器の機械音から、「この音だともう厳しいだろうな」ということまでわかるようになっていたので、その時の音から、おばあちゃんはかなり難しいだろうと思っていました。その後、お子さんとかお孫さんとかたくさんのご家族・ご親族であろう方々が次から次にお見舞いに来て、おばあちゃんに話しかけていました。すると少しずつ音が変わって、おばあちゃんの状態がどんどん良くなったんです。驚きました。
そのときに「人の価値ってこれだな」「大切にしあえる家族がいることはなんて素晴らしいんだ」と思ったんです。地位とか名声とかお金とか、仕事で大きなプロジェクトを成功させたとか、そういうものも大切ですが、結局最後に残るのは家族なんだなと、そのとき強く実感しました。
その後、本当なら参加するはずだった成人の日も、私は集中治療室のベッドの上にいました。全身が麻痺しているから動けないし、しゃべれないのですが、看護師さんはたくさん話しかけてくれるんです。その日も、「逢澤さん、今日は成人の日ですね。病気が治ったら何がしたいですか?」と話しかけてくれました。一生懸命考えて、私は「母親になりたい」と思ったんです。病気が治ったら、子供を産んで、家族で幸せに暮らしたいって。
いま思えば、当時の私にとって、子供と幸せに暮らしている自分は、一番遠い存在だったんだと思います。病気が治れば大学にも復帰できるはずだし、就職して、仕事をがんばることもできるはず。でも、子供を産んで、母親として生きている私自身の未来の姿は、あのタイミングからはかなり遠い未来でした。だから、当時の私は、そこまで行けたらこの病気を克服しているんだろうなと考えたんだと思います。自力で呼吸ができない状態で、「母親になりたい」と思ったのは、いまでもすごくハッキリ覚えています。

その後、集中治療室を出ることができて、半年間のリハビリをして、病気は完治しました。そして私は結婚して、24歳と26歳で子供を授かって、あのとき思い描いていた母親になれたんです。病気も治って、母親にもなれて、これからとても幸せな日々が待っていると思いました。ものすごく楽しみにしていたのですが、現実は想像通りにはいきませんでした。
子育てがものすごく大変で、「病気と闘っているほうがマシだ」と思うくらいしんどくて、「思っていたのと全然違う。どういうこと?」と腹が立つくらいでした(笑)。ただ、誰に文句を言えばいいかもわからないですし、誰かが文句を聞いてくれたとしてもこの現実は変わらない。じゃあ、私ができる範囲で子育ての課題を解決しようと思ったんです。
こういう経験があったから、「子育ての課題を解決するサービスをやろう」とか、「生きている間に社会に対して何か貢献したい」と考え始めたんだと思います。
私は特に外出時のハードルが高いと感じていました。そもそも、産後1ヶ月とかはずっと家にいるじゃないですか。1ヶ月検診が終わるまでは家の中にいて、そこから少しずつ外に出るパターンが多いと思うんです。久しぶりにコンビニに行って、買い物して、「久しぶりに外で買い物した。社会と接した。やったぞ。」みたいな(笑)。
私の場合は、夫の仕事が忙しくて、朝会社に行って夜遅くに帰ってくるというタイプでした。そのため、最初の数年間は完全にワンオペみたいな感じでした。そうなると、大人とも喋らないですし、ずっと泣いている赤ちゃんと一緒という日々が続いていました。「あれ?私、日本語話せなくなってない?」みたいな感覚になることもあって、「孤独に育てる」と書いて「孤育て」という言葉もありますけど、そういう環境で育児をしていました。
そして、家の中にいると精神的にもやばいな、と感じてきたんです。「3人に1人が産後うつ」みたいなデータもありますが、私もだんだん塞ぎ込んでいく自覚があって、無理にでも外に出ようと思いました。小さな子供を連れて、近くのカフェに行って帰ってくるだけなんですが、「カフェに行けた!私がんばった!」みたいな達成感がありました。だから、無理にでも外に出かけようと決めたんです。
次は、子供の成長とともに「どこに出かける?」というのが問題になってくるんです。子供が赤ちゃんのときはベビーカーに乗せたり、抱っこしてカフェに行けば良かったんですが、大きくなってくると状況が変わってきます。ハイハイしたり、よちよち歩きする頃には、「安全に遊べる場所はどこ?」になってくるんです。

いろいろ検索して、見つけた公園に行くんですけど、ウチの子はトンネルのすべり台がとても苦手なんですね。普通のすべり台は問題ないのに、トンネルだと「ぜったいイヤだ!」となってしまって。「せっかくここまできたのに、、、」と身体から力が抜けてしまうことが何回もあり、それで「公園の場所だけじゃなくて、どんな遊具があるのかも事前にわかれば良いのに」と思うようになったんです。
ほかにも、「ベンチが集まっていて気軽に座れる場所がすぐわかったらいいのに」とかもありますね。街中で抱っこしていて、疲れたのでどこかに座りたいと思っても、ちょっと休める場所があまりないんですよね。あったとしても、検索に出てこなくて。
丸の内に出かけたときも、検索したら「子連れOK」だったレストランに行ったら、「ベビーカーのお客様にはご遠慮いただいています」と言われて入れなかったこともありました。「そんなのどこにも書いてなかったのに!」と思いながら、仕方ないので違うお店を探したりとか。
こんな感じで、子供とお出かけしたときにちょっと役立つ情報がまとまっていたらすごく使えるのにな、と思っていました。だから日常の中で「こうだったらいいな」という小さな課題のようなものをメモに書き溜めていたんです。そして、そのメモを見返したときに、いろんな情報をマップ上で探すことができたらとても便利かも!と思ったんです。
たとえば近所の公園を探す場合、まずは公園の名前を調べていました。公園の名前がわかると、次は名前で検索していたんです。いろんなSNSでキーワード検索して、どこかの誰かの投稿を見つけて、「すべり台について書いてないかな」とチェックしたりしていました。
いろんなアプリを行き来する必要があって、目当ての情報に辿り着くまでが大変だった経験から、いろんな情報をマップ上で探せると便利だと考えました。公園も、遊具も、ベンチも、ベビーカーOKなレストランも、ひとつのアプリでわかる。そういうサービスがあれば、子育ての大変さが少し軽くなるかもしれない。そう思って、サービスを考え始めたんです。
そのときは子育てとホットペッパーの営業を同時並行していました。「子育て関連の情報がマップ上でわかるサービス」というアイデアがあって、じゃあどうやってカタチにするか、というフェーズでした。
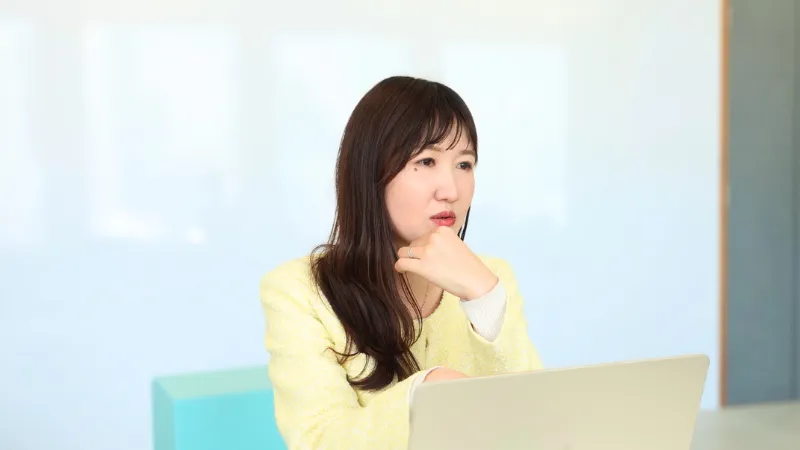
当時、『スタートアップ』という海外ドラマがあって私も見ていたのですが、その中にあるメンターが出てくるんですね。それを見て、「このメンターという制度、すごく良い」と思いました。知見のある人に相談しながら、適切な判断をしていくプロセスはとても大事だと思って、私もメンターを探そうと思ったんです。メンターとつながれるアプリを見つけたので、「子育て関連の情報がわかるアプリをつくろうと思っている」みたいな投稿をしたら、「コードで書くとお金も時間もかかるから、最初はノーコードでつくってみればいいんじゃない?」といったアドバイスをもらったんです。
次はいろんなSNSで「ノーコード」で検索をかけていきました。その中で「ノーコードコミュニティを立ち上げます」という投稿を見つけたので、私もそのコミュニティに入って、ノーコード開発について学んでいき、ひとりでアプリをつくり始めたんです。
当時、0歳と2歳とかですね。夜の7時くらいから寝かしつけをして、8時半とか9時ごろに寝てくれて。そこから起き上がって、リビングに行き、パソコンに向かうんです。最初の頃は「リビングに行ってパソコンに向かうこと」を目標にしていました。寝かしつけが終わってから起き上がるのが本当に大変で(笑)。慣れるまでに1ヶ月くらいかかりましたね。
夜泣きもするので、そのたびに作業を止めてまた寝かしつけして。それを何度かくり返して、少しずつアプリ開発を進めていきました。わからないことが出てきたら、コミュニティで質問して、ときには手伝ってもらったり、どうしてもわからないところはつくってもらったりしながら、少しずつという感じです。
サービスについていろいろと調べたりする中で、「個人でつくりあげるのはちょっと厳しいな」と思うようになりました。たくさんの人に使ってもらうには資金調達もしないといけないですし、ゆくゆくは会社化も�視野に入れたほうが良いんだろうな、と思っていました。
決め手になったのは、東京都のビジネスコンテストで1,000人中10人のファイナリストに選ばれたことです。ビジネスアイデアが評価されるコンテストだったのですが、法人であれば事業資金として100万円いただけるということでした。もともと会社化を考えていたこともあって、これは良いきっかけだなと思い、働いていたリクルートを退職して起業することにしたんです。そして、2022年5月に株式会社iibaを創業しました。
「子育てに役立つ情報がマップで見つかる」というコンセプトはあったのですが、私個人の体験や感情によるものでした。そのため、アプリづくりと並行して、このコンセプトの検証を進めていきました。
アプリづくりについては、あらゆるサービスの良いところを参考�にして、自分のサービスに持ってくる感覚です。「このUIはわかりやすい」とか「この階層のつくり方だと、ユーザー目線で操作しやすい」とか、海外のものも含めていろんなサービスを触りにいって、「良いな」と思ったらすぐにスクショを撮ってストックする。そういうことをひたすらくり返していきました。本当にたくさんのサービスを見たので、アプリのUI・UXを見るのはオタクレベルだと思います(笑)。

コンセプトの検証のほうは、まずはSNSを使いました。「遊び場」や「子供 公園」といったキーワードで検索すると、お出かけについての投稿がランダムに出てきますよね。そしたら、上から100人に「アンケートのお願いです」とか「Zoomでヒアリングさせてください」とDMを送っていきました。その結果、私と同じように困っている人がたくさんいて、すごく反応が良かったんです。私が課題だと感じていたことはレアケースではないとわかり、安心しました。
アンケートやヒアリングの結果を持って、今度はビジネスとして成立するかの検証のために投資家の方や起業経験をお持ちの方とコンタクトを取っていきました。お時間をいただいて、ペインがあることを伝え、壁打ちをしたのですが、最初のほうはいつもボコボコにやられてしまって(笑)。「ビジネスモデルとして厳しい」とか「サービスのクオリティが低い」とか、たくさんのフィードバックをいただき、そこからまたブラッシュアップする。事業とプロダクトの壁打ちを同時並行で進めていくという感じでした。
最初はInstagramを伸ばすという動きをとっていました。私がiibaのアカウントをつくり、試行錯誤を重ねていきました。
定期的にコンテンツを投稿したり、「マップのアプリをつくっています」「アプリがリリースされたらこんなことができるようになります」とかいろんな情報を発信していきました。最初の1ヶ月くらいでフォロワーが1,000人くらいになって、そこからもコツコツとSNS運用を続けていきました。アプリのβ版を2023年の10月にリリースしたのですが、そのころには、フォロワー数を1万人ぐらいまで伸ばすことができました。
正式版をリリースしたときにフォロワーがいれば、その方々がアプリを使ってくれるので、良い関係性をつくるにはどうすればいいかを考えて運用していました。「なぜiibaを始めようと思ったのか」や「このアカウントは何を教えてくれるのか」といったことをできるだけ明確にして、アプ��リのユーザー候補を少しずつ増やしていったんです。
iibaは子育て関連サービスの検索や店舗情報、利用ユーザーの評価をマップ上で閲覧できるサービスです。特徴のひとつがUGC(User Generated Contentsの略。一般ユーザーによって制作されたコンテンツのことで、ユーザーのリアルな声などが反映されるもの)で、全国各地のお出かけスポットの情報や施設、店舗などの評価コメントが閲覧できます。

当初は、UGCの多くがインフルエンサーさんが投稿してくれたものでした。このインフルエンサーさんは、私がInstagramを始めた初期のころから相互フォロワーになっていた方々で、iibaがやりたいことやiibaではどんな情報が手に入るのかを理解してくれています。そのため、正式版がリリースされてからはサービスを盛り上げるために協力してくれているんです。
みなさんがそれぞれSNSのフォロワーをお持ちなので、インフルエンサーさ��んを介してiibaにもアクセスがあります。Instagramはフロー型で情報が流れてしまうことに対して、iibaはストック型です。Instagramで見かけて気になった情報を、iibaで詳しく見るといった相互補完的な使われ方をしています。
閲覧するだけではなく、ユーザーさんがご自身で見つけたスポットや評価コメントを投稿してシェアすることもできます。子育てに便利な情報のやり取りはもちろんですが、私たちにとっても発見だったのが「家族の記録用として使っています」というユーザーさんの声があったことです。
声を聞かせてくれた方は、ご自身で700件くらい投稿しているヘビーユーザーさんでした。その方は仕事ばかりの旦那様に対して普段から不満を持っていたそうです。ただ、ある日、iibaの中に残っているこれまでの投稿を見返していたときに、全国のいろんなところにお出かけの記録があり、それらはすべて旦那様が連れていってくれたということに改めて気づいたそうです。それ以来、「仕事が忙しいなかいろんなところに連れていってくれてありがとう」という感謝の気持ちが出てきて、「たくさんの思い出がつまったこのアプリは絶対に消せません」というものでした。
子育てをサポートする目的でつくったサービスですが、確かに「家族の軌跡が残る」という一面もあります。すごく良い使われ方をしていて、ちょっと温かい気持ちになり、とてもうれしく感じたことを覚えています。

一般のユーザーさん向け以外にも、事業者の方向けのサービスもあります。これは、iibaのマップ上にピンを刺せるもので、子育て中のママ・パパ向けに訴求できるというものです。
加えて、自治体向けのサービスでは子育て支援パスポートの認知拡大や、自治体が運営している子育て支援マップのDX支援などを行なっています。すでに京都府や広島県とお仕事をしているのですが、自治体が配布している子育てマップや子育て向けクーポンなどは、従来の紙の形式のものが多く、現在の子育て世帯にとっては活用しづらいです。
私たちが間に入ることで、マップデータとの連携を通じて子育て支援サービスの認知向上をお手伝いしたり、口コミや評価も反映することでサービスのブラッシュアップにつなげたりしています。
他にも、インフルエンサーマーケティング事業もあります。これは子育て世帯向けのマーケティングを引き受けるというもので、全国にいるiibaのインフルエンサーがアンバサダーとなり、SNSで子育て世帯向��けのPRを行なうというものです。
正式版のリリースから約1年がたち、iibaは現在、UGCのスポット数が全国各地に2万件以上、総フォロワー350万人、月間総再生数5,000万回以上というサービスになりました。
2025年の3月には、『AIの子供診断』という新しい機能もリリースしました。ありがたいことにたくさんの方に使っていただいているので、結構な量のデータが溜まってきています。それを活用して、お子さまの特性に合わせてレコメンドを出すという機能です。
「外で遊ぶのが好き」とか「おままごとが好き」とか、15個くらいの質問に答えていただくと、お子さまの特性が出ます。特性は「元気いっぱいチャレンジャータイプ」や「ひらめきクリエイタータイプ」「わくわく大好きエンジニアタイプ」など25パターンあり、特性に合わせておすすめのスポットがレコメンドされます。

「子供の好きを伸ばしてあげたい」といったママ・パパの気持ちに寄り添うことができる機能だと思いますし、お子さまとのコミュニケーションのきっかけにもなると思います。似た特性のお子さま同士で遊ばせることで、お互いの興味関心がさらに伸びるかもしれませ�んし、いろんな使い方ができると思います。
『AIの子供診断』のようにテクノロジーを使ったサービスは今後も積極的に検討していきたいと思っています。子育てって、めちゃくちゃアナログでレガシーな領域だと思っているので、テクノロジーでの課題解決にはどんどん挑戦していくつもりです。
そういう意味では、自治体向けのサービスはさらに拡充していきたいと思っています。ほかにもインバウンド対応に向けた多言語化も進めたいですし、ママさん向けのスポットワークサービスなども相性が良いのではないかと考えています。
街づくりという観点ではディベロッパーさんとも協業したいと思っていますし、鉄道会社さんも私たちのユーザーさんと相性が良いと思います。子育てを「成人するまで」と捉えると、小学校や中学校、高校で必要なさまざまな備品の購入だったり、習い事や塾、予備校などの教育関��連ニーズもあると思います。
いまフルタイムの社員は5名で、業務委託のメンバーも含めると10名強。そして、インフルエンサーさんが300人という体制です。事業拡大の可能性がたくさんあるので組織強化をしたいのですが、「とにかく人数を増やす」というのは考えていません。
一人当たりの売上が大きい会社にしたくて、良いメンバーを揃えて、丁寧に事業をつくっていきたいです。この「良いメンバーを揃える」というのが難しいと考えていて、課題だと思っています。

実は、いまも毎日のようにコンタクトフォームに応募の連絡をいただいています。これは本当に幸せなことだと思うのですが、だからといって、すぐに「採用!」とはなりません。
私たちの会社は2022年にできたばかりの新しい会社ですから、本当に毎日いろんなことが起きます。うれしいこともありますし、そうじゃないこともたくさんあります。そんなカオスな状態に対する耐性がないと、がんばり続けるのは難しいと思っています。そのため、良い方からの応募を待つのではなく、私が自らサーチして、口説きにいくことが大事だと思っています。
基本的には、1年以上かけてやり取りして、信頼関係をつくりながら口説いていったという感じです。たとえばいまプロダクトを任せているCPOは、創業するずっと前にノーコードのコミュニティで知り合いました。
ひとりでアプリづくりを始めたころから私のことを知っていて、途中から「iibaのこと少し手伝いたいと思ってきた」と言ってくれたんです。コミュニティでのやり取りを通じて相手がどういう人かもわかっていたので、私からも「一緒にやりたい」と伝え、知り合ってから2〜3年後に晴れてジョインしてくれることになりました。
基本的にいまがんばってくれている社員は、向こうからコンタクトを取ってくれた人が多いです。「iibaの事業に興味がある」と声をかけてくれて、そこからやり取りが始まり、長くコミュニケーションを取った上で、「じゃあ一緒にやろう」という流れですね。
業務委託のメンバーは、SNSがきっかけになることが多いです。エンジニアさんやデザイナーさんは初期のころからフォローしていて、私もこの事業のことについて投稿していくなかで興味を持っていただき、相互フォロワーになっていたんです。
投稿の中身でどういうタイプの人かわかりますし、近況もわかるじゃないですか。「いまはどういう仕事をしていて、近いアプリをやっているからゆくゆくは一緒にやるのもいいかも」という人のストックがあるんですけど、その人が「大きなプロジェクトが終わります」みたいなタイミングで声をかけて、口説いています。
反応が良ければ面談して、「こういうことをお任せしたいです」とミッションをお伝えして、「まずはこれを一緒にやっていこう」という感じです。
そうなんです。子育て関連の仕事に興味を持ってくださる方はけっこう多いのですが、事業やサービスに落とし込むのが大変ですし、それで収益をあげて会社を存続させることはもっと大変です。アプリの動作を少しでもスムーズにするためにたくさんのテストを重ねますし、ユーザーさんが気づかないような小さなところにもめちゃくちゃ泥臭くこだわったりするので。
「こういうことがしたい」といったエゴを押し付けると良いことがないので、ユーザーさんや事業者の方など、相手が何を望んでいるのかをしっかり理解したうえで、その期待を超えるアウトプットを出すことが重要だと考えています。すごく当たり前のことなんですけど。
だから、いつも「相手のニーズは?」「相手の課題は何だろうね?」とか「課題を解決できる根拠は?」みたいなやり取りをたくさんします。思考と仮説を積み上げていって、サービスに反映されたときに初めて、ユーザーさんにとってこのサービスを使う理由ができると思うので。

ちなみに、会社の中では「ワオ!」という�言葉がよく使われています。チャットのスタンプもつくりましたし、私も口うるさく言っています。これは、日々のすべての業務で驚きや感動を出せるようにしようという私たちのバリューであり、仕事の目的や目標でもあります。
当たり前のことをやっていてもインパクトを出せないですし、私たちのようなスタートアップは、やっぱり周囲からの期待値を超えていかないとダメだと考えています。期待値を超えたときに出るのが「ワオ!」です。だから社内では「それってワオ!はどこにあるんだっけ?」とか「なんか、ワオ!が足りないよね。もう一回考えよう」というやり取りがたくさんあります。
「相手の期待値を超えるにはどうすればいいだろう?」ということを常に考えながら仕事をしているのですが、これってけっこうしんどいんですよね。並の資料や提案はつくれるけれど、そこからもう1段階、できれば2段階、クオリティを上げることにこだわるので。ただ、クオリティを上げるための方法を考え出せるし、そのプロセスを楽しめるメンバーが揃っているので、この価値観は薄めたくないと考えています。ちょうどプレシリーズAの資金調達が終わったので、今後は組織強化にもアクセルを踏んでいきます。
いつも考えているのは、「親を笑顔にしたい」ということです。私たちは自分たちのことを「PARENT TECH(ペアレント テック)」と呼んでいるのですが、これは、テクノロジーを活用して、子育ての課題や不便を解決し、いまよりも子育てしやすい社会をつくりたいという想いを込めています。
私の家庭がそうなのですが、親である私が笑顔だと家の中が明るくなると思うんです。私も自分の親に対して、笑顔でいてくれたらそれだけでいいと思ったりします。仕事とか人間関係とかいろいろありますけど、親がニコニコしていたら、子供としてはそれだけでうれしいみたいな。
親が笑顔だと子供が幸せになるし、幸せな子供が増えれば増えるほど、その次の世代も明るくなると思っていて。世の中を明るくするには、親であるみなさんを笑顔にすることがポイントなんじゃないかって、ちょっと抽象的ですけど、そういうイメージを持っているんです。とにかく親が楽しく子供と時間を過ごせたり、親の負担や不便を減らして、空いた時間で子供と向き合えるようにする。そんな状況をつくっていきたいと考えています。
子育てに関しては、大変だとかつらいとか、お金がかかりますとか、いろんなイメージがありま��す。だから、「やっぱり落ち着いてからじゃないと子供を産めないな」みたいな、いまはそういう社会だと思うんですよね。
なぜそうなっているのかを考えると、いま子育てをしている人たちが大変そうに見えるからだと思います。ネットを見れば「しんどいです」「つらいです」といった話がたくさん出てくる。でも、子供ってすごくかわいいし、一緒にいると幸せを感じられるし、子供がいるからこそ感じられる日々の尊さみたいなものが、少なからずあると思っていて。そこにはほとんどスポットライトが当たっていないと思うんです。
だから、そんな世の中のイメージとか状況を、変えていきたいと思っています。「子育てって楽しいよね」「幸せだよね」とか、「子供がいてくれたから自分も成長できたよね」とか、そういうことを実感できるように、iibaを通してたくさんのきっかけを提供していきたいと思っています。
そうすることで、「子供を産んでみたいかも」とか「子供と一緒にいる人生ってハッピーだよね」とか、そういう社会になれば良いなと思いますし、そういう社会にしていきたいですね。


株式会社ディプコア 代表取締役CEO
インタビューの当日、新聞の朝刊には少子化関連のニュースがありました。「少子化は進んでいる。一方で既婚者数は増えている」という内容でした。これはまさしく、子育てについてどこかネガティブなイメージがあるから、ということも影響したデータだと思いました。 逢澤社長は「PARENT TECHとして親を笑顔にしたい。そうすることで次の世代の未来が明るくなるから」とおっしゃいましたが、この考えに個人的にはとても共感しました。私も自分の子供たちに笑顔で接したいですし、家庭の中を明るい雰囲気にしたいです。そして、「大きくなったらこんな家庭を持ちたい」と感じてもらいたいと思いました。 そうすることで、ゆくゆくは現在とは逆のニュースが紙面を飾るかもしれません。世の中のイメージを変えるのは決して簡単ではありませんが、同社には期待値を超える企業文化を武器にチャレンジを続けて欲しいです。iibaユーザーとしても引き続き応援しています!

2024.10.30 公開

2025.03.03 公�開

2024.11.22 公開

