
効率と非効率。合理性と非合理性。変えることと変えないこと───。上場を果たし、20周年を迎えたヌーラボ橋本正徳の心の中に、少しだけお邪魔した。
2024.08.01 公開

2024.08.01 公開
株式会社ヌーラボ 代表取締役 橋本 正徳
設立:2004年
事業内容:チームのコラボレーションを促進するサービスの開発・提供

RPO事業代表
自社プロダクトへの信頼感や愛着を持ち続けてもらうために、自社のブランド力を「資産」として捉える「ブランドエクイティ」を体現している企業として尊敬、応援しています。主要サービスであるSaaS型のコラボレーションツール「Backlog」は、直近でも優れたサービスとして、国内外で複数の受賞歴を持ち、ブランドコンセプトに共感するユーザーも数多い。BtoBプロダクトでありながら、toC向けのイベントやBacklogユーザーコミュニティJBUG(ジェイバグ:Japan Backlog User Group)等からのリファラル集客で安定した成長基盤を構築。今後、ヌーラボサービス全体を利用できる「ヌーラボアカウント」をハブに、あらゆるオフィスワーカーのワークフローを、一貫してサポートすることを目指されています。
表現活動に興味があったので、福岡の高校を卒業してから、東京に出て舞台関連の専門学校に入りました。学校に通いながら、劇団の立ち上げをしたり、焼き鳥屋でアルバイトをしたりしていました。頭で考えていることとか心の中にあるものを、表現活動を通じてアウトプットしていました。ちなみに、この感覚はいまも変わっていませんね。昔は舞台や芝居を通して自分を表現していて、いまは仕事やサービスを通じて自分を表現している感じです。
地元の福岡に帰ってきたのは20歳のときです。もともと20歳になったら落ち着こうと思っていて、実家の建築業を手伝う形で働きはじめました。でも、実家の仕事はすぐ辞めてしまったんです。自分の性格と合わないと感じてスパッと辞めました。

とはいえ生活があるので、個人事業主として新聞の折り込み広告のデザインをしたり、知り合いから資金援助してもらって八百屋をはじめてみたり、いろいろやってましたね。どこかの会社に就職することなく、流れに身を任せていました。
中学生か高校生のころからパソコンを触っていて、プログラムを書いたり、見よう見まねでデザインしたりしていたんです。なので、仕事をどうしようかと考えていたときも、「パソコンに関わる仕事だったら続けられそうだな」と思いました。
プログラマーとして働きはじめたのは、23歳くらいのときだったかと思います。子どもが小学生になるタイミングで、毎月お給料がもらえる仕事をしないといけないな、と。ただ、実務経験がなかったので経験を積むためにも派遣プログラマーとして働くことにしたんです。
派遣プログラマーとして仕事をしている時に、気の合う仲間ができて、一緒にプログラミングの勉強をしたり、オープンソースの活動をしていました。そして、2004年に仲間と僕の3人で会社を立ち上げたんです。

もともと起業をしようと思っていて、派遣プログラマーとして働き出したときも「3年後には独立します」と伝えていました。とはいえ、「こういうサービスをつくりたい」とか「こういう事業をやりたい」という考��えはありませんでした。当時は生活が大変だったので、まずはお金が欲しいという気持ちの方が強くて。自分の収入を上げることを目的に起業したというのがぶっちゃけたところです。
イシュートラッキングサービスのようなソフトウェアは会社設立以前から数回開発していて、Backlogは3回目の開発になります。
仕事を仕上げるまでの過程で発生したタスクや課題を整理して管理するために、あらゆる議題を記録し、その後を追跡できるシステムが必要になります。Backlogはいろんな方向性から検討し、誕生したサービスですね。
誕生の背景にある一つのストーリーとしては、僕たち自身が「使いたい」と思えるサービスがなかったことです。当時、東京の企業と取引することが多かったんですが、打ち合わせをするためだけに東京に出張していたんです。金銭的にも時間的にも体力的にもロスが多くて、イシュートラッキングシステムがオンライン上にあれば便利だね、ということで、既存のサービスをいくつか使ってみたんですが、なかなかしっくりこなくて。「じゃあ自分たちでつくってみようか」という流れです。
もう一つのストーリーは、派遣プログラマー時代の実体験です。仕事でグループウェアを使っていたんですが、どうも気分が乗らなかった。もちろん情報の共有とかは普通にできるんですが、使っていて楽しくないんです。逆に家で使っていたメールサービスはとても楽しくて。クマなどのペットキャラクターがメールを運んで来てくれるものなんですけど、かわいくて楽しいんですよ。メーラーに普通にメールが届けばいいのに、わざわざペットキャラクターを経由するというムダな工程があるんですが、そのムダに価値があって。気がつけば大した用事もないのにメールを送りたくなってしまうという(笑)。

そこで考えたんです。ムダのないグループウェアはできれば触りたくない。ムダのあるメールサービスは積極的に触りたい。ということは、ムダのあるサービスウェアがあれば良いんじゃないかって。あ、ムダという言葉はちょっとニュアンスが違うかもしれませんね。ムダじゃなくて、遊びの部分というか、そういう感じです。
みんなでイシュートラッキングサービスをつくっていたときに、「ユーザーにとって使いたくなる仕掛けのあるツールにしたい」と思っていて、それが開発途中のBacklogのコンセプトともマッチしていたんです。
そうですね。人を楽しませようという気持ちを持った社員が多いので、いろんなアイデアが出てきていましたね。「こんなことをやったらユーザーさんが驚くんじゃないか?」とか「こんな機能があったらユーザーさんが楽しんでくれるんじゃないか?」という感じです。
おもしろいのは「こうすれば仕事は効率的に進むんじゃないか?」という意見ではないことだと思います。効率的に仕事が進むことはとても大切ですけど、その観点だけでユーザーさんによろこんでもらえるサービスをつくるのは難しいんじゃないかなと思っています。アプローチの仕方が少しズレているというか。
効率を追求するには良いコミュニケーションが必要で、良いコミュニケーションを取るには良い関係性が欠かせません。良い関係性は、相手のことを思う気持ち�とかサービス精神、ポジティブさから生まれると思うんです。それってプラスアルファの部分で、どちらかというと非効率的なことですが大事なことだと思っています。

これは社員を採用するときのポイントでもあって、楽しむことに前向きな人を採用するようにしているんです。自分が楽しみを得るためにがんばれる人というか。うまく言葉にするのは難しいんですけど。そういう人って、「こうしたらおもしろそうじゃないですか?」というアイデアが出てくると思うんですよ。中にはこれまでとはちょっと違う新しい切り口のアイデアもあるはずで、ユーザーさんはそういうアイデアをよろこんでくれるんだと思います。「効率的」や「合理的」からサービスを考え始めると、どこにでもある普通のアイデアに着地することが多いと思います。それを否定するわけじゃなくて、少なくとも僕たちは違うやり方でサービスをつくりたいという話です。
オンラインで作図ができる「Cacoo」というサービ��スは、最初は業務フローを簡単に描けることを目指していたサービスでした。そこから進化して、最終的になんでも描けるツールになりました。

ただ「なんでも描ける」「キレイに描ける」だとユーザーさんに刺さらない。オールマイティすぎると「結局何ができるの?」になってしまうので。だから最初は「Webサイトのワイヤーフレームが描けるツールです」とアピールポイントを絞って販売をはじめました。
Cacooを販売するときには、Backlogのときとは違う戦略を取ったんです。Backlogは日本語で日本向けに販売しましたが、ユーザーさんの声を見ているとけっこうバッドなものもあったんです。「これができない」とか「ここがわかりにくい」とか、重箱のすみをつつく系の。もちろん貴重な意見としてありがたく頂戴するんですが、僕たちだって人間だからグッドな評価が欲しいじゃないですか(笑)。なので、Cacooのときは逆の戦略にしたんです。
具体的に言うと、Cacooは最初から英語でつくって、英語圏のユーザー向けにリリースしました。2009年くらいだったと思うんですが、当時はTwitter(現X)がポピュラーになり始めた頃で、新しいもの好きはTwitterを使っていたんですね。Cacooに飛びついてくれたのは海外��のそういった人たちでした。サービスをリリースしたら、「良いツールが出たぞ」とシェアされて、海外のメディアで取り上げられて、ユーザー数がどんどん伸びていきました。
最初は海外のユーザーばかりで、日本の僕たちがつくった日本製のサービスだと知らずに使ってくれていました。「このサービス、よく見たら日本語にも対応してるぞ」みたいなつぶやきもあって、「狙い通り、しめしめ」とうれしい気持ちになったのを覚えていますね。

海外で評価を受けたものが歓迎される雰囲気が、日本にはあると思うんです。食べ物とか、映画とか、そうじゃないですか。たとえそれが日本製のものでも、逆輸入みたいな感じで注目を集める。そのこと自体に何か言いたいわけではなくて、Cacooはその雰囲気にうまく乗れたんじゃないかなと思っています。
「Nulab Pass」は情報セキュリティやガバナンスを強化するためのオプションサービスです。生まれた経緯のひとつは、BacklogやCacooの利用企業が増えてき�たこと。中には大手もあって、そういう企業は、社内の誰が、どういう操作をしたのか、ログを残しておく必要があるんです。
もうひとつの経緯は、僕らもガバナンスの強化が必要だったからです。当時上場しようとしていたので、セキュリティがしっかりしていて、サービスのログインを一元化するシングルサインオン(SSO)や監査に必要なログを取得できるサービスの必要性を自ら感じたことが開発の背景にあります。
結果的にそうなっていますね。個人的には「自分たち」の範囲も変わってきていて、会社の成長を感じたりします。
たとえば、以前の「自分たち」はヌーラボの社員を指していたんです。ところがいまの「自分たち」は、ヌーラボの社員に加えてBacklogやCacooなどのサービスを使ってくれているユーザーさんも含んでいる感覚があります。「みんなで良い仕事しようぜ」と同盟を組んでいる感じ。販売元とお客さんという対峙する関係ではなく、横並びで同じ方向を向いていて、自分たちの目線の先には「良い仕事」というゴールがあって、みんなで一緒にゴールを目指している感覚なんです。
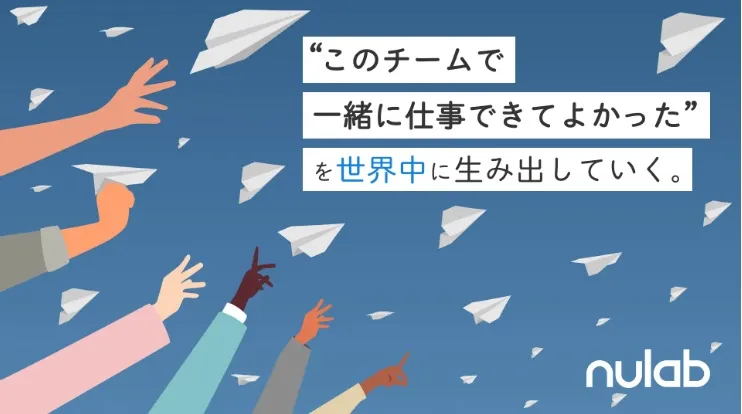
現在のブランドメッセージには「このチームで一緒に仕事ができてよかった」というフレーズがありますが、ここでいう「このチーム」はヌーラボの社員とたくさんのユーザーさんのことです。良い仕事ができた!という達成感をたくさんの人と一緒に得たいし、そのゴールにたどり着けるようにみんなでがんばろうよ、という気持ちを言葉にしたらこうなりました。
個人的に特に意識していることはないんです。昔からそうだったというか。
舞台や芝居をやっていたときは、小さな劇団だったのでなんでもやっていました。チケット販売もやるし、大道具もやるし。お客さんと直に接することもあるし、そこで芝居の感想を聞かせてもらって、次の作品に活かすという感じでした。
焼き鳥屋でアルバイトしていたときも、お客さんと会話したり、お客さんの食事のペースを見ながら、焼き鳥を焼いたり魚を捌いたりしていました。
いまも同じ感覚なんです。カウンター商売をしていて、僕らはお客さんに楽しんでもらいたい。だからお客さんの表情も気になるし、楽しんでもらえたら本当にうれしいと感じる。このうれしい気持ちを何度もたくさん感じたいからがんばるみたいな。この感じがベースにありますね。

上場にはメリットとデメリットがあると言う人もいますが、僕はデメリットはないと考えています。よく未上場の企業の社長さん達から「社外の人からいろいろ言われるでしょ?」という質問がありますが、今はそういう時代じゃないと思っていて。
というのも、世の中にはSNSがあって、僕たちのサービスにはフィードバックをくれるお会いしたことのないユーザーさんかもしれない人たちが沢山いて。さらに、話題になってニュースに取り上げられると、顔も知らないし、ユーザーさ�んかどうかもわからないような人から、中傷コメントされたりもする。僕や僕たちにいろいろ言う人はすでにたくさんいるんですよね(笑)。僕個人にもX上で約1万人くらいのフォロワーがいますが、1万人から見られているので、良いこともそうじゃないことも含めて誰かから何かを言われる可能性のある時代なんですよ。そう考えると、「株主からいろいろ言われる」は特にデメリットではないと思っています。参考になる良い意見ももらえますし。
逆に、信頼してもらえるメリットがあります。社内の監査体制や情報セキュリティ、もちろん事業の状況や業績に関しても、それなりにちゃんとしていないと上場できませんから。「ちゃんとしてる会社です」と言う社会的な保証書を得られるのは大きなメリットだと思いますね。上場企業じゃないと取引できません、という会社もあります。たくさんの会社に僕たちのサービスを使って欲しいので、上場して良かったと思ってます。
変えたことはほとんどないですね。社内の管理体制くらいでしょうか。仕事をするときのスタンスやユーザーさんとどういう関係性でいたいかは変わらない部分だと思います。
競合他社の動きを気にすることはあ�りますが、どういうサービスだろう?と興味を持ってウォッチするレベルですね。僕たちのゴールは「このチームで一緒に仕事できて良かった」という瞬間をたくさん生み出すことであり、競合に勝つことではないので。
ただ、僕らのユーザーさんが類似のサービスに移ってしまうのはものすごくイヤだから、どういうサービスを提供しているのかはしっかり見ています。
「“このチームで一緒に仕事できてよかった”を世界中に生み出していく」というブランドメッセージは、2020年くらいに言語化したものです。上場を見据えていたので、そのタイミングで、改めて大切にしていることを言葉にしました。

ただし、これからもずっと同じメッセージを出し続けるかはわかりません。あくまでも「現時点ではこれです」という感じです。ブランドメッセージって、世の中と僕たちとの接点であり、ヌーラボはこういうスタンスで世の中とつき合っていきますよ、という宣言�だと思っています。僕たちが変わらなくても、世の中が変われば、使う言葉や言い方は変えるべきだと考えています。
えっと、、、これはとても難しい質問で、うまく説明できるかわからないんですが、本質的なものって言語化が難しいと思っています。僕が自己開示があまり得意ではないということもあるのですが(笑)。
本質って自分の中に大切に持っているものだと思うんです。時々新しい要素が追加されて、変化したり、進化したりしながら、奥のほうに大事にしまってあるものだと思うんです。それを「僕の本質はこれです」と言葉にした途端、自分の中から出ていってしまって、その瞬間で切り取られて固定されてしまう気がするんですよ。
なので、何か対外的なメッセージを発信するときは「(時代の空気とか世の中のいまの価値観を踏まえてあえて言葉にするとしたら)大切にしているのはこういうことです」という感じになってしまうんです。

代わりに、個人的には行動することを大事にしたいと思っています。「これが大切だと思うんだよね」と言葉にする以上に、大切にしているものを心の中にしっかり持った状態でたくさん行動したい。その行動には僕の本質というものが滲み出ると思うし、その行動を見て僕が大切にしていることを感じ取ってもらえたらうれしいなと思っています。
「言葉にしないと伝わらない」という意見があることも理解しているつもりです。でも、誰かに何かを伝える時に、行動を大事にするパターンと言葉を大事にするパターンがあるとしたら、僕は前者のタイプだということでしょうか。えっと、、、やっぱり言葉で伝えるのは難しいですね(笑)。
引き続き、良い仕事ができてよかったという体験を生み出せるサービスを提供していきたいです。その際にポイントになるのが、「多様化」というテーマにどう向き合うかだと思っています。

日本を考えると、労働力が減少していくけどひとり当たりの仕事量は増えていくと感じます。そこでDXが必要になるという流れになりますが、今度はDXをするための労働力が足りない。なので、海外から労働力を招き入れることになり、日本国内においては半ば強制的に多様化が進むと考えています。
世界に目を向けると、「格差を是正するためにも平等に仕事を与えましょう」みたいなことが国際的な会議で話されています。そのため、やったことがない仕事に就く人が増えてくるかもしれません。そうなると、世界においても多様化がどんどん進んでいくんじゃないかと考えています。
多様な人たちが仕事で使うツールは、多様化に対応されたものである必要があると思います。だから僕たちのサービスは多様化に対応されていないとダメですし、逆説的に僕たち自身が多様化していかないといけません。
多様化のために必要なのは、まず自己をちゃんと持っておくことだと思います。自分はどういう人間なのかを認識することで初めて、他者の存在や自分との違いが理解できるようになると思うからです。
自己をちゃんと持つという文脈で言えば、ヌーラボのみんなには「こうであって欲しいな」というものがあります。
一つは、真面目にならないで欲しいです。合理性だけを基準にしないで欲しい。「常識で考えたらこうすることが合理的だよね」という常識を疑って欲しい。常識は時代とともに変わるものですし、合理性だけでつくられたものってどこかつまらない場合が多いので。
もう一つは、人を楽しませることに一生懸命でいて欲しいです。誰かを驚かせたり、よろこばせるにはどういう仕掛けがあればいいだろう?と考えることに、時間とカロリーを使って欲しい。そういうことを考えるのっておもしろいですし、ワクワクしながら仕事することが、実は最も合理的で生産的だと思っているので。


株式会社ディプコア 代表取締役CEO
名刺交換をさせていただいた時に、名刺の裏側に何か文字がプリントされていることに気づきました。裏返して見てみると、そこには「NUICE TO MEET YOU」の文字がありました。 「NICE」ではなく「NUICE」となっているのは、「Nulab」が掛けてあるのだと思いますが、「初めまして。一緒の時間を持つことができて僕たちはうれしいです。これからよろしくお願いします」と言ってもらえた気がしました。 橋本社長は「ヌーラボのみんなには、人を楽しませるために一生懸命でいて欲しい」とおっしゃっていました。名刺のプリントから、同社のカルチャーを感じることができました。

2024.09.06 公開
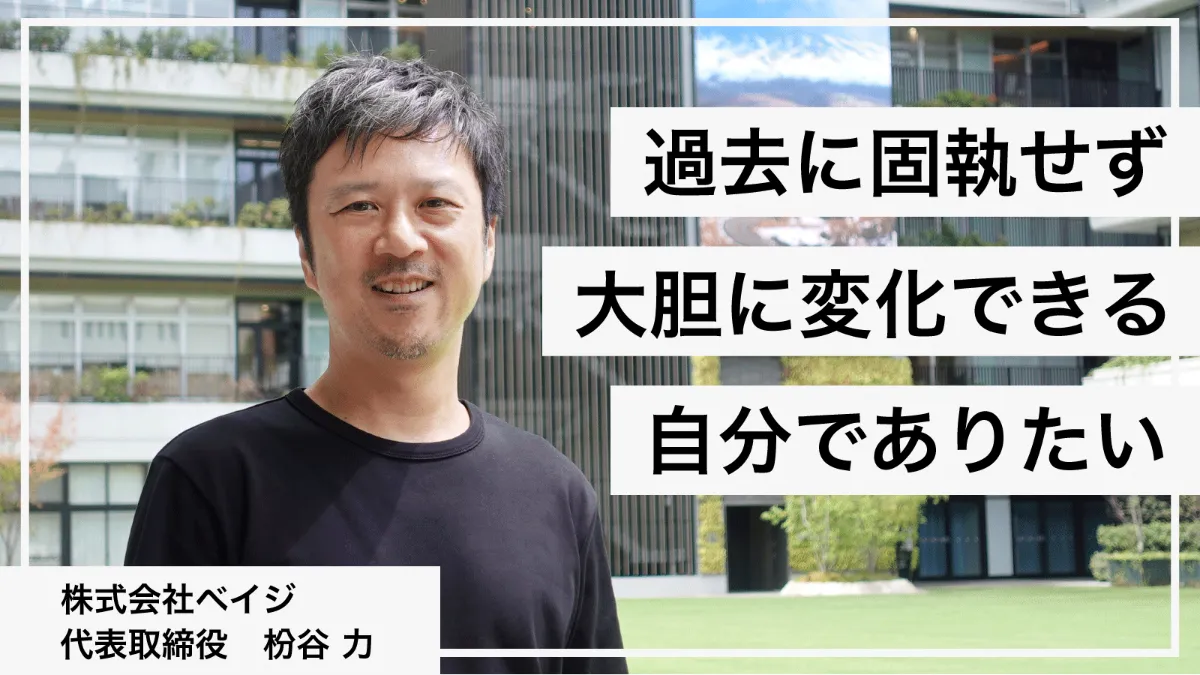
2024.09.19 公開
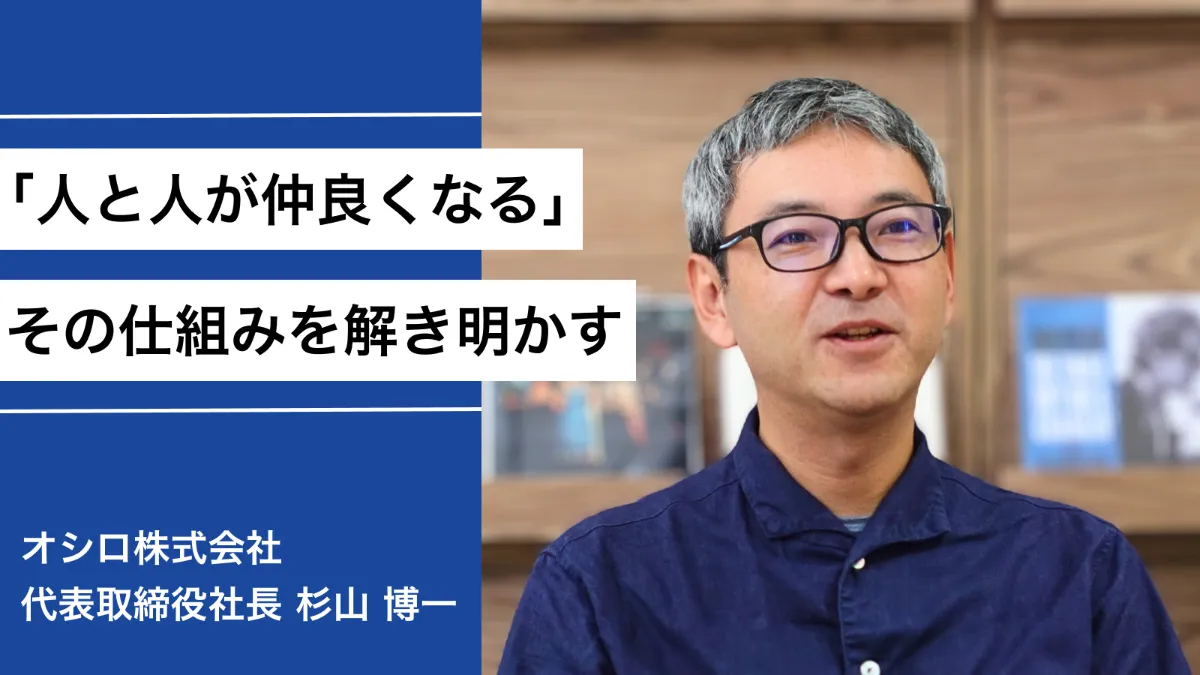
2024.11.26 公開

