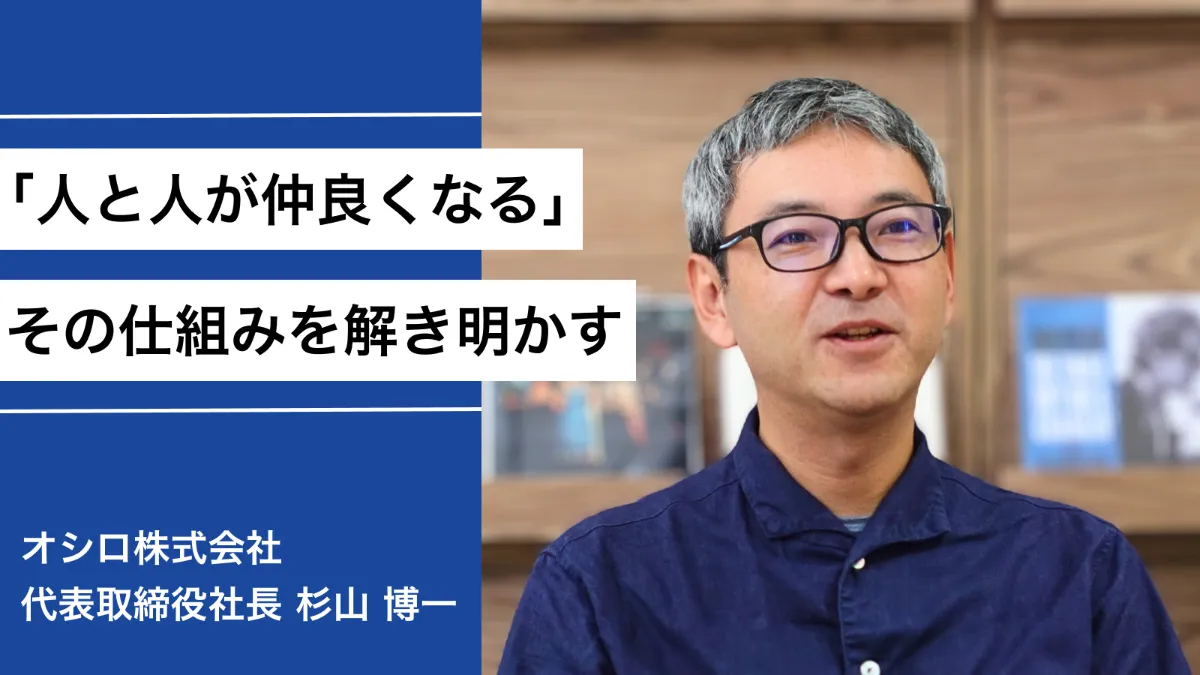
8年間の孤独を原体験に、コミュニティサービスの開発を進めてきたオシロ杉山。見えてきたのは「人と人が仲良くなる」ことが持つ大きな大きな可能性。
2024.11.26 公開
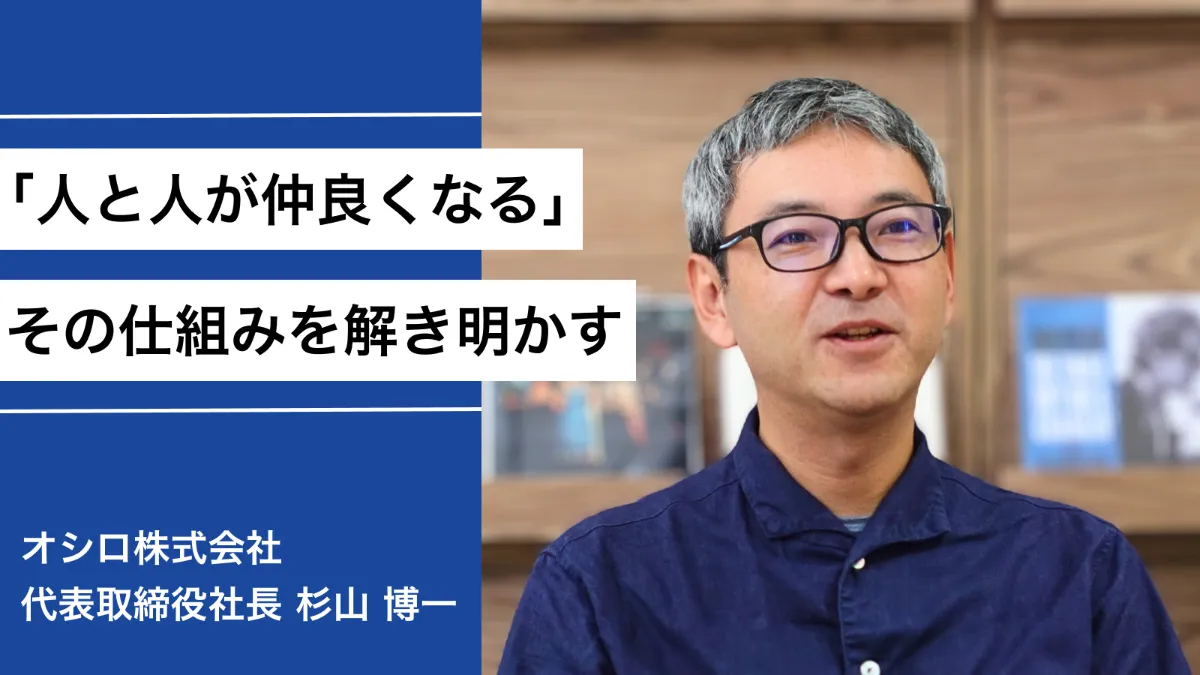
2024.11.26 公開
オシロ株式会社 代表取締役社長 杉山 博一
設立:2017年
事業内容:オウンドプラットフォーム 「OSIRO」の開発、「OSIRO」を利用したサイトの企画・制作・運用・管理
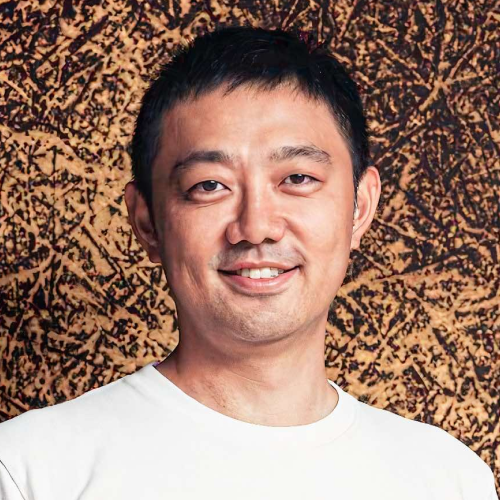
株式会社コルク 代表取締役社長
出会ったとき杉山さんはデザイナーで、僕は出版社に勤める編集者。お互い、起業するとは思いませんでした。起業した中でのさまざまな試行錯誤を共有し合い、応援し合う仲なので、オシロの事業がうまくいって仲間が増えるといいなと推薦しました。
24歳の時に世界一周の旅に出ました。日本に戻ってからアーティスト活動を始めたんです。表現の仕方は人それぞれありますが、私の場合は絵を描くことでした。
そもそも、世界一周から帰ってきて思ったのは、「自分は就職できない」ということです。アルバイトはしたことがありましたが、企業で働いたことがありませんでした。それ以前に、決まった時間に決まった場所に行くというのがとても苦手な人間だったんです。そのため、自分ができること、やりたいことは何だろうと考�えた結果「絵を描きたい」という気持ちがあり、そのままアーティストとして活動を始めたという流れになります。

24歳から30歳まで、アーティストとして活動していましたが、絵を描いて食べていくことは非常に難しいことがわかりました。学生のときに買ったMacintoshがあったので、知り合いの会社のロゴや名刺のデザインをやらせてもらいながら細々と食いつないでいたものの、それだけではアーティスト活動を続けていけなかった。
30歳のとき、自分には才能がないと自覚して、アーティストとしての活動を終わりにしました。そこからフリーランスのデザイナーだけを2年くらいするのですが、24歳から32歳までの合計8年間は、現在で言うところの完全フルリモート状態でした。
上司もいないし、同僚もいません。表現活動をしているので、「自分のやりたいことができているか」という観点では幸せなのですが、仲間がいないことや人間としてのつながりが感じられない日々というのは、こんなにも不健康なのかと感じていました。
その後は、デザイナーから起業の道に方向転換することになります。デザインと経営はまったく畑が違うと思うかもしれませんが、僕の中ではどちらも「表現方法」の違いでしかありませんでした。
外資系の金融機関で働き、米国でMBAを取得し、最新の金融サービスを学び帰国した方と出会い、ここ日本でも必要なんだ!と熱き男に絆されて、一緒に会社を立ち上げ、当時まだ日本にはなかった金融サービスづくりに挑戦しました。他にも、シェアリングエコノミー領域でのサービス立ち上げや、外資系企業の日本法人立ち上げなども経験させてもらいました。そして、後にオシロの共同創業者の一人となる四角大輔氏と出会ったんです。
大輔さんは当時、数々の実績を出していた音楽プロデューサーの仕事を辞め、ニュージーランドへの移住に向けて動いていました。彼はニュージーランドのことを偏愛していたので、ニュージーの素晴らしさをたくさん教えてくれたんです。僕も興味が出てきていざ行ってみたら、ニュージーランドのことがどんどん好きになっていきました。

以来日本とニュージーランドを行き来する生活を4年くらい経験したあと、ニュージーランドへの移住を本気で考え始めるようになりました。そして、いつものように日本からニュージーランドに行くために空港にいったときに、事件が起きたんです。
搭乗手続きをしていたら、何かの手違いで飛行機に乗れなかったのです。これまでに何度も渡航していたのに、その日に限って、こんなこともあるのかと.....。
空港で途方に暮れていたときに、「お前はまだセミリタイアするには早い」「まだ日本でやるべきことがある」と頭の中に聞こえてきた気がしました。そして「日本を芸術文化大国にしなさい」とお告げのように言われたんです。冗談ではなく、天から命じられたと理解しました。

それからは、あれだけ好きだったニュージーランドへの移住はスパッとやめ、どうやったら日本が芸術文化大国になるかだけを考えるようになりました。いま思い出しても不思議ですが、どれだけ働いても全然疲れを感じない状態になったんです。アスリートがゾーンに入った状態というか、天命を授かって無敵状態になったのかもしれません��(笑)。
当時は、自宅のマンションの一室で開発をはじめ、そのあと渋谷のオフィスに間借りさせてもらっていたときは毎日朝6時すぎにオフィスへ出社し仕事をしていました。決まった時間に決まった場所に行けなかった僕という人間を知っている人にとっては、ありえないと思われるかもしれません。でも、無敵状態の僕はこれまでとは違います。アーティストやクリエイターがずっと活動できるようにするにはどうすればいいかを考え、それらを実現する仕組み作りをはじめていました。
最初は、海外のサービスを見つけて日本に持ってくるという案がありました。そこで英語で調べつくしたところ、毎月自分が決めた金額でアーティストやクリエイターを支援するというサービスを見つけたんです。
「これは良いサービスだけど、8年間孤独だったときの僕が使っても、これだけでは活動を続けられないな」と思いました。要はお金だけじゃダメということです。
さらに調べていくと、アーティストやクリエイターのファンが集まるオンライン上の掲示板サービスを見つけまし��た。中には日本のアニメのファンが集まっている掲示板もあって、覗いてみると20万人もの人々が参加し、ものすごい熱量でやり取りをしていたんです。日本のアニメについて、熱のこもったやり取りがくり広げられているのを見て、胸が熱くなりました。
でも、結局このサービスは無くなってしまったんです。たくさんの人が集まって、好きなことに高い熱量で没頭していても、このサービスは持続できなかった。
これらのサービスに触れてみて、僕がやりたいことはこの両方が合わさったものだと思いました。簡単に言えば、アーティストやクリエイターに「お金とエール」をおくり続けられるサービスです。ただ、いくら探してみても見つけることができなかった。そのため、「ないなら自分でつくるしかない」とつくり始めることにしました。
それまでの経験から、プラットフォームをつくるにはたくさんのお金と多くの時間が必要になることはわかっていたんです。ただ、このときの僕は「日本を芸術文化大国にする」という天命を授かっていたので、必要性に迫られ迷わずつくり始めていました。
2015年の3月に自宅マンションの一室で開発をスタートして、12月にはβ版をリリースしました。当時は、アーティストやクリエイターがコミュニティオーナーになり、エンドユーザーであるファンの方々は、審�査の後にサブスクリプションでコミュニティに所属いただけるというものです。
最初のユーザーはオシロの共同創業者で作家の大輔さん(四角大輔氏)でした。彼は「プラットフォーム自体をオリジナルで持ちたい」といった根本を覆すようなアイデアを出してくれました。2016年は、さらに2人の作家さんが使ってくれてコミュニティオーナーは3人になりました。β版とはいえ、きちんと料金をお支払いいただいて使っていただき、さらに機能改善を進めていきました。
そんな日々を過ごしているときに、地下鉄のホームでたまたまサディ(コルクの佐渡庸平氏)に会ったんです。彼とは以前から飲み友達でしたが、そのときは久しぶりの再会でした。普段はタクシー移動である彼とこうして電車で会うことには本当に驚きました。
「ニュージーランドに行くって言ってなかったっけ?」と聞かれて、天命を授かった話をし、「僕はこれに人生を賭けることにした」と言うと、「そこまで本気なら一緒にやろうよ」と。彼が経営するコルクは日本で初めての作家・クリエイターのエージェントで、つくりたい未来が似ていたのと、その割にはお互いの強みの部分が全然違う。一緒にやるのはおもしろいなとお互いが思い、彼の参画が決まったんです。

そこからは、コルクのオフィスに間借りさせてもらい、開発を進めていたのですが、やはり「資金が必要」という話になりました。そこで、ちゃんと会社にして資金調達をしようと考え、2017年1月にオシロ株式会社を設立したんです。
オシロ社がスタートした後も、しばらくはサディにお願いして、コルクのオフィスの中に間借りさせてもらっていました。そして、いろいろな方を紹介してもらったり、知り合いのところへ伺い、事業の話をしにいきました。
「この仕組みがないと、アーティストやクリエイターが生きていけないし、文化が醸成していかない。そうなると、日本は世界のなかで生き残っていけないと思っている」「日本を盛り上げていくための新しい仕組みだ」「すでに3人の作家さんに使ってもらっていて、データも取れている」。そういうことを伝え続けたんです。お金とエールが続かないと、創作活動を続けることができないというの��は僕の原体験なので、熱が込もっていたと思います。
並行して進めて行ったのは、人と人が仲良くなるためのメカニズムを解き明かすことです。アーティストやクリエイターが持続的に「お金とエール」を受け取るためには、応援者であるコミュニティに集まった人と人が仲良くなることだと仮説を置きました。しかし、どうすればそうなるのかを解明するのは本当に難しいことです。
ただ、僕自身が小さいころにいじめられっ子だったというのもあり、この「人と人が仲良くなる」というテーマについては普通の人より興味がありました。自分の中に、「どうすれば仲良くなれるのかを知りたい」という純粋な動機もあるんです。
恐竜を研究する学者がいるとしたら、その人たちって「恐竜に関するたくさんの謎があり、どうなっていたんだろう?」というロマンを求めて研究を続けていくじゃないですか。研究して、これまではわからなかったことを解明することで、自分自身の存在意義を表現していると思うんです。それと同じで、僕にとっては「人と人が仲良くなる」を解明することが、自分の表現活動にもなるんです。
アーティストやクリエイターは応援者がいないと活動を続けることが難しい。そして、応援者の中には、毎月お金を��出してくれる人と、そうじゃない人がいる。であれば、毎月お金を出してくれる人同士を横でつなげる。そうすることによって、応援者が応援団になり、応援団が続けば、お金もエールも持続していくし、アーティストやクリエイターは活動を持続できる。人と人が仲良くなるための仕組みを考え、それを一つずつ「OSIRO」というプロダクトに組み込んでいきました。

アーティストやクリエイターは、多くの苦悩を抱えています。そのため、「OSIRO」で自分だけのコミュニティを持てることで、たくさんある悩みを少しでも減らしていきたいと思っています。
たとえば、アーティストやクリエイターには創作活動の苦悩があります。そして、いまの時代だとSNSの苦悩がある。意図していない伝わり方をして炎上してしまうと、その対応にものすごいエネルギーが必要なだけでなく、何より繊細なアーティストにとっては心理的ダメージが大きい。コミ��ュニティができて応援団ができたとしても、今度はコミュニティを運営するという苦悩もあります。
SNSの苦悩については、コミュニティがあることで炎上を未然に防ぐことができると思っています。具体的には、世の中に発信する前にコミュニティ内にポストして、ワンクッション置くことが可能です。本人には悪気がなくても、世の中から見たら少し感覚がズレていたり、使う言葉が強すぎたりすることがあります。ただし、事前にコミュニティに投げかけて、リアクションをもらうことでテストができ、そうすることで炎上を未然に防ぐこともできるのではないかと考えています。
そして、コミュニティの運営ですが、実はこれも本当に大変なんです。応援者を集めて応援団というコミュニティをつくるだけでも大変なのに、コミュニティの中で何も起きなければ活性化せず、廃れてしまいます。コミュニティは立ち上げた後の運営がとても大事なんです。
コミュニティをどのように活性化するかは、これまでコミュニティマネージャーの手腕に委ねられていました。しかし、ある人はコミュニティ運営が上手だけれど、ある人はあまりうまくないという個人差が生まれてしまうことがありました。コミュニティ運営が担当する人によって左右されてしまうと、アーティストやクリエイターの苦悩を減らすという目的が達成できません。そのため、僕たちはコミュニティを科学し、どうすれば上手に運営できるか��を突きつめていったんです。
SNSやコミュニティ運営の苦悩がなくなり、お金とエールが届く状態を維持する。そうすることで、アーティストやクリエイターは本来の活動に専念できるようになります。
くり返しになってしまいますが、コミュニティ運営の難易度は非常に高いです。コミュニティマネージャーとしては、まず場を適正に盛り上げるのが大変です。そして、盛り上がったら盛り上がったで運営の手間が増えます。場の熱を下げることも重要になります。つまり、アクセルとブレーキの両方の役割を果たすことが求められるんです。
この大変な役割を、どうすれば軽減できるのか。冷たすぎず、熱すぎない。コミュニティ内を適温に維持するには、どうすればいいのか。僕たちは、ここを考えていきました。
出した結論の一つは、テクノロジーを使ってコミュニティの状態を把握するということです。盛り上がりが足りないのか、盛り上がりすぎているのか、そういうことをデータで測り、状態を把握できるようにしたんです。僕たちはこの指標を「熱量指数」と呼んでいます。たとえば、コミュニティメンバーの滞在時間など、いろんなデータをもとに算出しています。

ちなみに、この「熱量指数」をサディの「コルクラボ」というコミュニティで活用された事例があります。彼には、作家には絶対に失敗して欲しくないという気持ちがあるので、まず自分がコミュニティオーナーになって色々と試してみると言ってくれたんです。データサンプルを取り、機能改善につなげて欲しいということでした。
「熱量指数が200くらいであればそのコミュニティは適温」という想定でした。ところが、コルクラボでは一時期「熱量指数1,800」という数値が出たんです。ログを見てみると、1日に4時間もコミュニティに参加している人がいました。そして、コミュニティを辞める人が出てきてしまったんです。その方は、盛り上がりすぎてしまい、燃え尽きてしまった。
ここでの学びから、「熱量指数が1,000を超えるとコミュニティマネージャーは危険信号」という認識になりました。コミュニティには純粋で熱量が高い人が多く集まっているので、一度盛り上がり始めると熱中し、どこまでも行ってしまう人もいらっしゃる。そのため、コミュニティの状態をデータで把握して、必要があればクールダウンできるようにしたんです。
人間だと異常を見逃す場合があるので、「コミュニティマネージャーのAI化」を進めています。コミュニティの状態をテクノロジーで把握して、状況に合わせたアドバイスやアラートを運営者に出してくれるというものです。こうすることで属人化を防げますし、コミュニティの運営を一定以上の品質で汎用化できます。
他にも、人と人が仲良くなるために必要なことをレシピ化しています。運営者ができていること、できていないことをデータで把握し、「いまはこんなことをすると良いですよ」と状況に合わせて最適なレシピを出すということも自動化しています。
そうですね。大切なのは目的と手段を間違えないことだと考えています。新しいテクノロジーをサービスに組み込むことが目的ではなく、あくまでお金とエールが持続するために「人と人が仲良くなる」居場所になるコミュニティをつくり、適切な盛り上がりを維持して、アーティストやクリエイターの苦悩を軽減することが目的です。この目的を果たすためにテクノロジーを活用したという順番ですね。
人と人が仲良くなるために必要なことは何なのかを貪欲に考え、それをサービスにも反映していますから、コミュニティに参加したメンバー同士がつながりを深めていくことにもなります。アーティストやクリエイターとファンが仲良くなり、ファン同士も仲良くなる。僕たちのコミュニティサービスを介して、このような関係性がつくれるようになってきたことはとてもうれしく思っています。

最近では「OSIROを社内コミュニケーションツールとして使いたい」と言ってくださる企業が増えてきているんです。リモートやハイブリットで働くことが一般的になったことで、会社と従業員や、従業員同士のつながりを深めるために何かできないかという企業が増えてきています。
上場企業においては、非財務情報の開示が義務づけられたことも影響しているのではないでしょうか。社員のエンゲージメントがどうなっているかなどは、簡単には把握できません。組織サーベイなど、すでに様々なサービスがありますが、データが取れる範囲が狭かったりして、企業にとっては緊急度と重要度が高いニーズになっているようです。
そうですね。仕事をする上で効率的にコミュニケーションを行なうためのツールは世の中にたくさんあれど、人と人が仲良くなることを目的に設計されているものではありません。一方で、僕たちの「OSIRO」は効率的なコミュニケーションを取るためではなく、人と人が仲良くなるには何が必要なのか?にフォーカスして開発してきたプロダクトになります。そのため、データで把握できる範囲や内容が、業務効率化を目的につくられたサービスとは大きく異なるんです。
会社組織の中では役職や部署、職種での切り分けが一般的だと思いますが、コミュニティでは「好きなものが同じであること」が基準になります。そのため、職場では発生しないコミュニケーションが生まれ、その積み重ねがお互いのつながりをより良いものにしてくれるんです。
たとえば名古屋のある会社では、こんなことがあったそうです。その会社には「サーフィン部」という社内の部活があったそうです。そこにマーケティング部の新人が入部して、休みの日にサーフィンに行った。そこには同じ部署の部長がいて、会社では仕事の話ばかりで趣味の話は一切しなかったそうですが、部活で�同じ波に乗ったら友達感覚が芽生えた。
その新人の方は、仕事ではなかなか自分から発言しづらかったそうですが、部活を通じてハードルが下がった。そして、会社で思い切って自分のアイデアを部長に提案したそうです。SNSを使った施策だったのですが、部長は「めちゃくちゃ良いじゃないか!」と褒めてくれた。新人の方の提案は実際の施策として採用されて、結果的に成功したそうです。極端な例ですが、これは「人と人が仲良くなったら業績が伸びた」というわかりやすい例だと思います。

人と人が仲良くなることをベースに開発された「OSIRO」を社内コミュニティとして使うことで、組織のつながりがより良いものになるんじゃないか。そういうことに気がついた経営者の方から、相談が寄せられるようになってきました。最近だと1万人以上の従業員を仲良くしたいと数社からお声がけをいただいています。
結論は「強化していく」ですが、この結論にいたるまでには、個人的に葛藤がありました。というのも、「日本を芸術文化大国にする」というミッションがありますから、企業の社内利用についてはあまり乗り気ではなかったというのが本音です。
しかし、企業内とはいえ趣味コミュニティを促進することは、ミッション・ビジョンにもつながると考えました。なにより、アーティストやクリエイター向けのサービスを充実させていくためにも、財務基盤が強固になることは必須です。プロダクトの開発にはやはりお金がかかりますから。やるべきことをやり続けるためにも、法人向けでこれだけ求められるということですから、社会に役立つことは大切だと考えました。また、オシロという会社をしっかり成長させることで、社員のみんなの給料だってあげることができます。企業の課題解決にもつながることで、僕たちのサービスが求められている実感もあります。
はい。この「300名」は少し控えめな数字かもしれません。社会に求められるサー��ビスになっていることが前提です。
何をしたいのかというと、やはり「人と人が仲良くなる」の解明です。コミュニティマネージャーをAI化したときに、コミュニティ運営に関するレシピを山程つくりましたが、それで終わりだとは思っていません。もっと様々な角度から、いろんな実験をして、サービスに反映していきたいと考えています。そのためにも、様々なコミュニティを立ち上げ、PDCAを回していきたいんです。
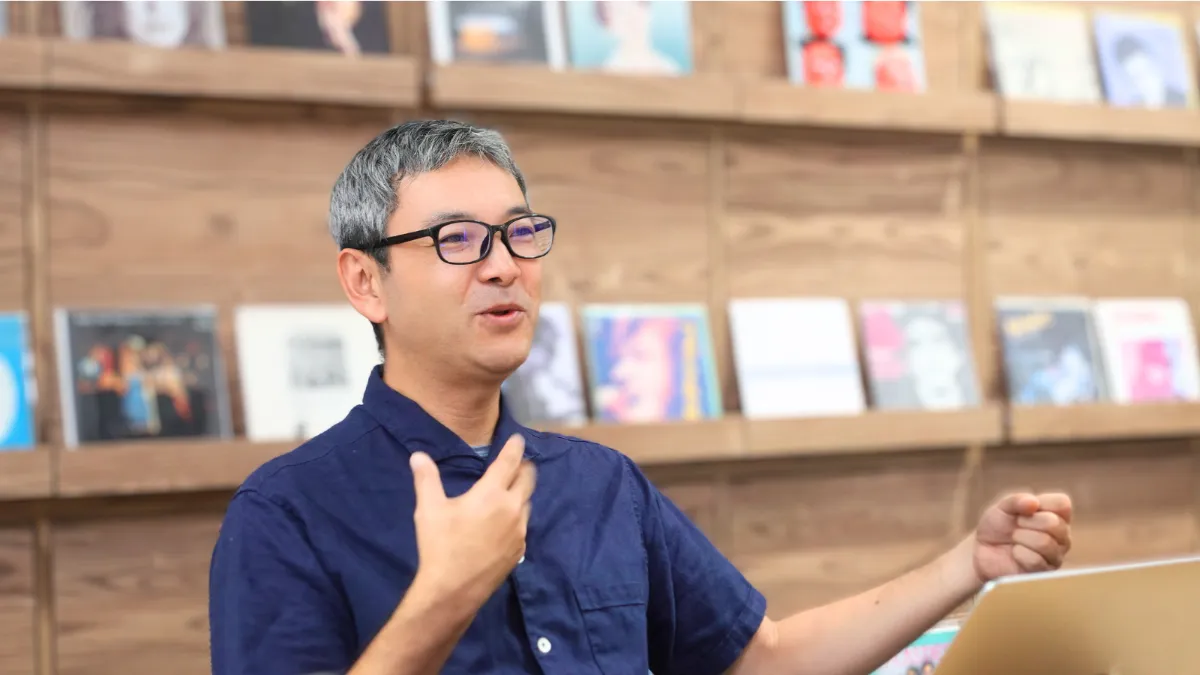
人軸とかテーマ軸、地域軸など、コミュニティを考える際の軸はいくつかありますが、大好きな人やモノ、コト、場所でコミュニティをつくることができれば、魅力的なんじゃないかと考えています。
たとえばですが、雑誌の編集を経験された方で、「人と人とのつながりに興味がある」という方はとても可能性があると思っています。紙の雑誌などは時代の移り変わりもあって変革期だと思いま��すから、もし、雑誌編集のご経験を活かしたくて、コミュ二ティに興味があるという方は、ぜひ一緒に仕事がしたいですね。
あとは特定の専門分野で豊富な知識をお持ちである、という意味で学芸員の方で人と人とのつながりに興味がある方も非常に親和性があるのではないかと考えています。博物館や美術館のコミュニティを担当していただけると、とても相性がよいですよね。
これは抽象的になってしまうのですが、物事をやり切る力だったり、未経験のことでも挑戦する気質だったり、自発で情熱的になれる人だったり。新しいものを生み出すためにも、これらの資質の方が必要なんじゃないかと思っています。
これからも様々なコミュニティを立ち上げていくので、なかには想定通りに行かないことも出てくると思います。それでも、目的を達成するために最後まで走り切れるかどうかは、大事なポイントだと思います。
新しいものを生み出すクリエイティビティというのは、色々なことを含むと思っています。たとえば、自分で新しいアイデアを出すというのもそうですし、別々のアイデアを�くっつけて新しいものをつくるというのもあります。みんながアイデアを出しやすい雰囲気づくりができるのもクリエイティブだと思いますし、どこかの企業とコラボイベントをするとしてその段取りをキレイに調整できることもクリエイティブだと思います。
そう考えると、いわゆるクリエイティブ業界でがんばってきた方は、これからのオシロで活躍できると思います。テレビでも、ラジオでも、雑誌でも、広告でも、映画でも、経験職種問わずいろんな方が活躍いただけるのではないでしょうか。
僕が大事にしたいのは、価値観が文化として残り続けていくことです。会社として掲げているミッションがあって、そのミッションを実現するために大事にしたい価値観があります。この価値観が、今後も残ってくれたらうれしいなと思っています。
たとえば、僕はHonda(本田技研工業)という会社が好きなんです。なぜかというと、本田宗一郎のDNAが残っているからです。いま、グループ全体で20万人くらいの従業員がいて、売上も過去最高を突破して、規模はどんどん大きくなっています。それでもなお、本田宗一郎は生き残り続けている。この事実に僕はとても興奮するんです。なので、僕も価値観を大切にしたいと思っています。

ここで大切にしたい価値観は大きくふたつあります。まず、プロフェッショナルであること。結果を出すために努力をするとか、そういう当たり前のことにしっかりとこだわれるマインドを大事にして欲しいと思っています。
もうひとつは「美意識」ですね。何を美しいと感じるかは個人差がありますが、まずは自分が美しいと感じることにこだわって欲しいと思っています。美意識のある思考、美意識のある行動、美意識のある言葉選び、経営にもプロダクトにも美意識を求めます。自分が良いと思うことを大事にしていると、仕事をしていてもハリが出ますし、達成感や満足感が得られると思うんですよね。
変化がたくさんある、非常にエキサイティングな数年間が待っていると思っています。
僕たちは人と人が仲良くなることの解明に挑戦していて、コミュニティ専用オウンドプラットフォーム「OSIRO」を通じて、機能というより、カルチャーを提供しているつもりです。コミュニティという言葉や存在を知っている人はたくさんいると思いますが、コミュニティが社会の中でどのような役割を果たすのかを考えたことがある人は多くはないのではないでしょうか。
世の中の流れはいま、確実に「人と人のつながり」を求めている。それらをどのように生み出すかに向いていると考えています。「他の誰かとつながっていること」が人間の幸せの根底にあるんです。WHOは2024年に「社会的つながりに関する委員会」を発足することを発表しました。これは人とのつながりがなければ人間は健康になれないということの証です。また、先ほどお伝えしたように、企業活動や仕事においても同じことが言えると思います。
心の幸せや心身の健康、そして仕事。社会のなかの様々な文脈が、いずれもコミュニティに着地しています。
海外では、「文化的処方」というものが普及していると聞きます。例えば、不眠症の人が「眠れなくて」と病院に行くと、「最近人と話してますか?」と質問される。加えて、「何が好きですか?映画ですか。じゃあ、映画が好きな人が集まるコミュニティに参加してみてはどうでしょう?」とアドバイ��スされるそうです。人とつながれるコミュニティが薬になるわけです。
そう考えると、僕たちがこだわり続けてきたコミュニティサービスで解決できることは、本当にたくさんあると思っています。いまはまだ小さな規模ですが、これがどんどん成長して、大きな産業になります。オシロの従業員だって、300名じゃ全然足りなくなるでしょう。1万人でも足りないかもしれない。それくらい世界を変えるポテンシャルがあると思っています。だって、世界中がコミュニティを欲している時代ですから。
僕はHondaが好きなので、また自動車業界を例に出しますが、どの自動車メーカーにも黎明期がありましたよね。まだ自動車が出たばかりのころ、これから先、事業として成立するかまだわからないという時期があったはずです。その時期に、「自動車には未来がない」と判断して離れていった人もいると思います。一方で、自動車の価値を信じて、未来を信じてがんばり続けた人もいた。そして、気がつけば自動車産業という大きな大きなものをつくり上げた。コミュニティにも、これと同じことが言えるのではないでしょうか。
自動車産業の黎明期と同じ雰囲気を味わえるというのは、歴史をつくる当事者になるということです。そして、これからのオシロで仕事をするということは、ちょっとおおげさかもしれませんが、歴史の登場人物になれるかも��しれないということだと思います。そういう環境をイメージしたときに、細胞が沸騰してゾクゾクする。そういう方と一緒に仕事ができたら最高ですね。


株式会社ディプコア 代表取締役CEO
私はパーソナルジムに通っていて、トレーナーさんに聞いたのですが、同じジムになんと、86歳のおじいちゃんがこられているそうです。 ご高齢ではあるものの、20kgくらいはベンチプレスを上げてトレーニングしていて、とても若々しい方だと伺いました。トレーナーさんの話では、身体を鍛えること以外にも趣味があるそうで、「まわりにはおとなしくなってきた友達もいるけど、自分は趣味を通じていろんな人と関わっているからまだまだ大丈夫!」とおっしゃっていたそうです。 他の人とのつながりがあること。趣味など自分が興味のあるテーマでつながっていること。これらが心身に与えるプラスの影響は本当に大きいのだと思います。杉山社長から様々なお話をお聞きして、なおさらそのように感じました。 同社のサービスは法人向けの展開にも注力していくということで、今後世の中での認知度・利用度が高まっていくはずです。人間関係の悩みや不安が、今よりも少なくなっている。そんな未来になると、とても素敵ですよね。
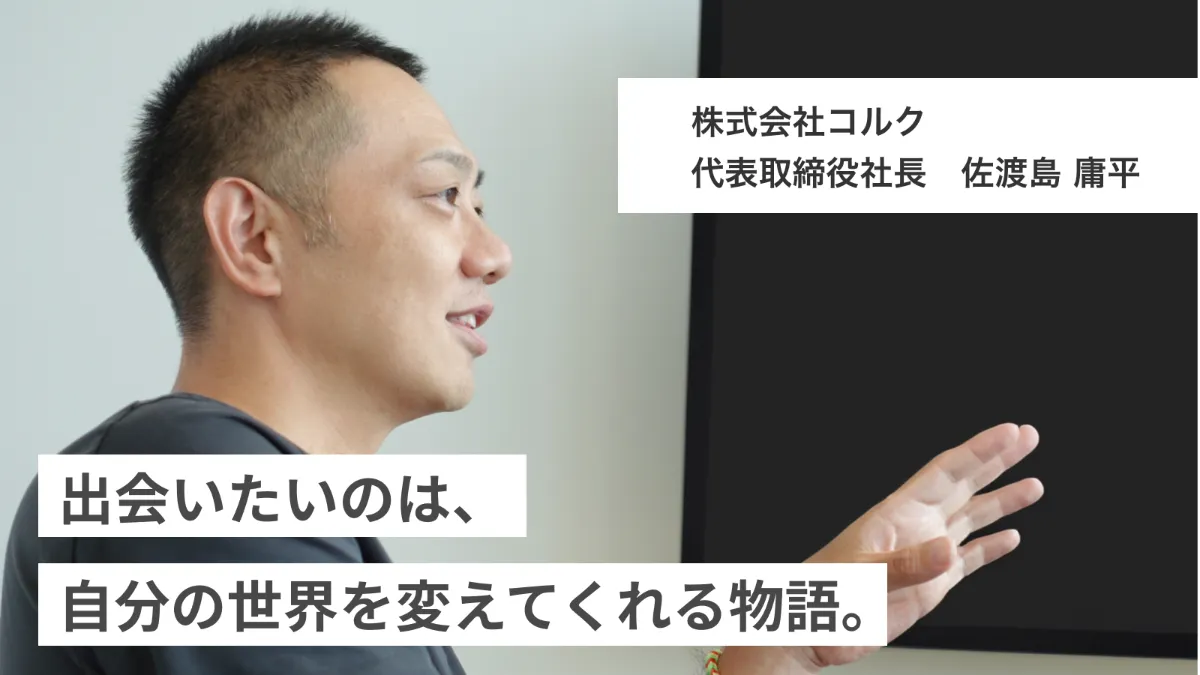
2024.10.28 公開

2024.08.01 公開
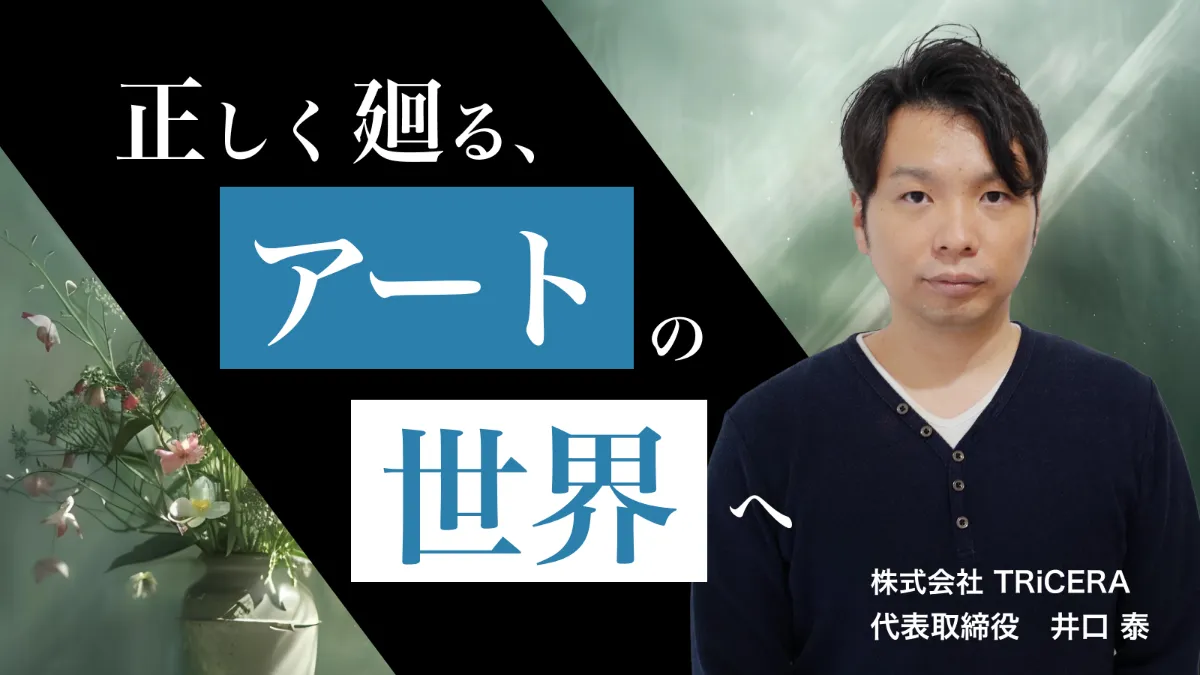
2024.08.01 公開
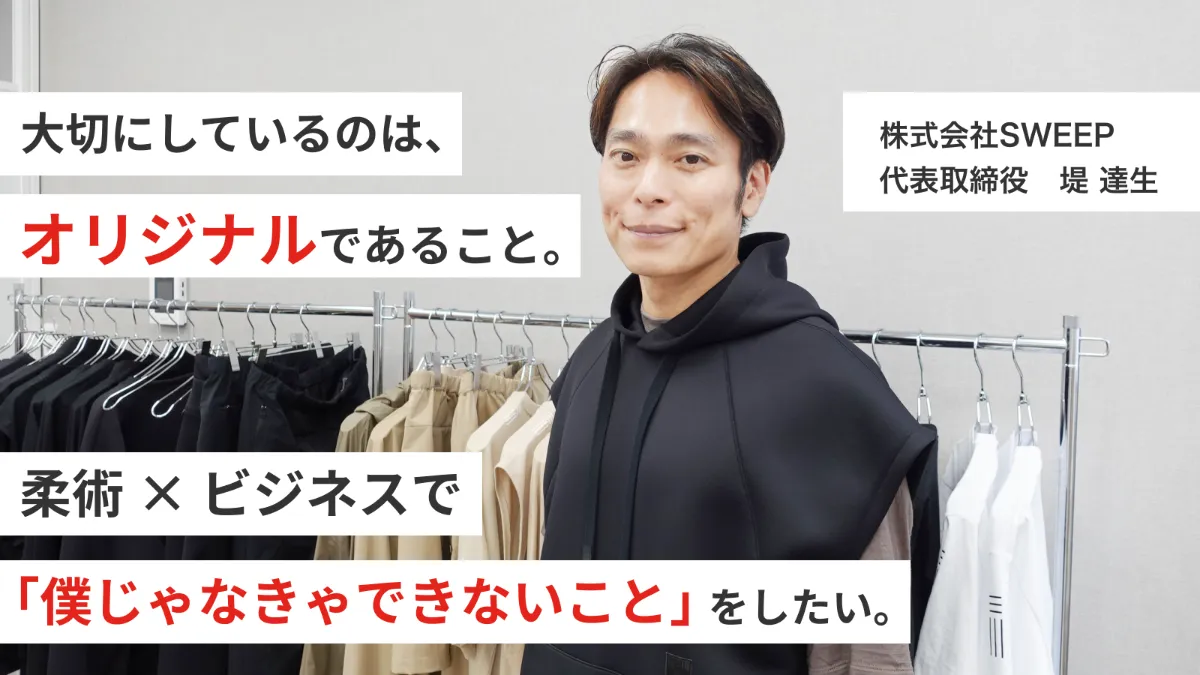
2024.10.01 公開

2025.04.11 公開

2025.11.26 公開

2024.12.13 公開

