
経営経験も専門知識もないなかで任された代表の役割。「検証・体系化・提供」のプロセスでドローンの社会実装を目指す高野の、裏方の哲学。
2025.08.01 公開

2025.08.01 公開
株式会社スカイピーク 代表取締役 高野 耀
設立:2017年
事業内容:産業用ドローンの教育・人材育成事業/導入支援・運用代行事業/コンサルティング事業

株式会社EXPACT 代表取締役
株式会社スカイピークは、ドローン人材育成の第一人者として、制度や技術の変化が著しいドローン業界において、柔軟かつ着実に事業を展開されています。代表の高野さんは、華やかさよりも現場と対話を重ねることを大切にされる実直な方で、その誠実な姿勢が行政や企業との信頼関係にも結びついているように感じています。市場変化にも鋭く反応し、必要とされる知見や仕組みをタイムリーに提供するその姿勢には、一貫したビジョンと熱量を感じます。空のインフラを支える存在として、今後のさらなる発展に大きな期待を寄せています。
東京出身で、子どもの頃からスポーツが好きでした。幼少期はサッカーをしていましたし、中学と高校ではサッカーをしながらゴルフにも挑戦していました。
高校の終わりからサッカーのコーチのアルバイトを始めました。家から徒歩数分のところにフットサルコートがあったのですが、そこで元Jリーガーの方がチームを立ち上げたので、コーチとしてお手伝いしていたんです。「教えるのがうまい」と評価をしてもらっていて、難しいことをやさしく噛み砕き、わかりやすく説明できることが自分の強みのひとつなのだと気づくことができました。この強みは、その後のスカイピークの事業でも役に立っていると思います。
大学に入ってからもコーチは続けながら、競技フットサルの社会人チームで夢中になってやっていました。週に3日とか4日はジムに行ってトレーニングして、食事は鳥のささみとゆで卵と納豆とか(笑)。トライアウトを受けたりもしましたし、結構本気でやってましたね。

スポーツばかりしていたら、就職活動のタイミングが終わっていました。大学3年のときに就職活動をするのが普通だと思うのですが、私は4年になってからやるものだと勘違いしていたんです。4年になって、まわりのみんなに「そろそろなの?」と聞いたら、「もう終わったよ」と言われて。
そもそも、そのときは「本気でち�ゃんと仕事をしよう!」というマインドになっていなかったので、もう少しやりたいことをやろうと前向きにとらえ、大学を卒業しても就職せず、アルバイトしながら引き続きトライアウトを受けたりしていました。
もちろん、プロになるのは簡単じゃなくて、1〜2年くらいがんばったのですが、いよいよ働くことと向き合わないといけないと考えたんです。父親が税理士だったことから、私も簿記とファイナンシャルプランナーの資格を取りました。資格を活かして会計事務所でアルバイトを始め、その後、経理として就職しました。
事務職として働いていたものの、一円単位の繊細な仕事は少し苦手でした。環境を変えてみようと転職してみたものの、当時はなかなかうまく馴染めなくて、会社員ではない道を考え始めました。
それからは、スポーツ関連の仕事で何かをお手伝いするとか、複数の仕事をしていました。フリーランスと言うか、フットワーク軽く、複数の業務委託を請け負っていた状態です。そんな中でいろんな社長と経営者ネットワークをつくったりもしていたのですが、その流れで知り合ったある方と仲良くなりました。
その方は新たにドローン事業を始めようとしていました。ドローンはどこでも自由に飛ばせるわけではないので、飛行試験や講習などのために施設をおさえるのが重要とい�うことでした。私はスポーツをやっていたから、競技場など広い施設をたくさん知っていました。ここでシナジーが生まれたんです。
「ドローン事業を始めようと思っているから手伝ってよ」という感じでやり取りが始まりました。その方をオーナーとして、ドローン事業を形にするための実行部隊が私という感じです。
そうなんです。経験を積み、いまでこそ航空業界の専門家の方々などと「自動化の未来に向けて」というテーマで対談をさせていただくことも多いですが、当時は専門的なことはわからないところからのスタートでした。最初はお手伝いから関わり始めましたが、オーナーはほかにも事業をやっていたので忙しく、実務的なところは私が進めていきました。ただ、そのときは専門的な知見がないため、詳しい人たちの力をお借りしようと思い、少しずつドローン関係者とのネットワークをつくっていったんです。

専門家の方々とのつながりが増えていって、いろんな情報が�私のところに集まってくるようになりました。実務も進めていたので、現場の理解も深まっていきました。
その状態で2年ほど経ち、さまざまなご縁があったこと、そして現場の理解が進んでいたこともあって、私が代表になることになったんです。
意識していたことはいろいろありますね。現場を深く理解するために、複数の立ち位置の人に話を聞きに行くこともそうですし、時間軸を意識して、短期的な目線と長期的な目線で物事を考えてみることもそうです。産業分野ごとに切り分けて情報を整理することも大切でしたし、ときにはドローンとは関係ない視座から考えてみる、ということもやっていました。
広い関係性をつくり、そのなかでいろんな角度から物事を見てみる、考えてみる。そうすることで、事業についての理解が進み、自分なりの見解が持てるようになっていったと思います。
オーナーからは任せてもらっているので、その分、結果でお返ししなければと思い、自分なりにがんばっているつもりです。
ドローンの業界は新しい分野ということもあって、とても大きな会社か、すごく小さな会社か、そのどちらかという極端な業界だと思っています。その中でスカイピークは稀有な存在で、小さい会社ではあるものの、長期的な目線で事業を進めています。そのため、同業他社にはできないような価値提供ができると思っていますし、業界の発展に寄与できるような動きを取っていきたいと考えています。
航空法では、人が乗れない構造で、自動操縦によって飛行可能な、100g以上のものを「ドローン」といいます。

カメラを積めば空からの視点で撮影ができますし、撮影した映像や画像といったデータが取得できるので点検や調査にも使えます。また、トンネルや地下�空間にも入っていけますから、危険が伴う場所の調査にも有効です。こういった観点で、手軽な用途から専門的な用途まで幅広い可能性が注目されているのがドローンだと思います。
世の中の一般的なイメージとして多いのは、ドローンで撮影した映像だったり、空中に文字や絵を描くドローンショーだと思います。そのような活用も進んでいますし、点検や調査でも活用されています。
そうですね。橋や道路といった交通インフラの点検や建物に対する点検調査、工事現場の進捗管理をはじめとした建設分野での活用が多いです。
他にも、過疎化した地域での物流を担うといった地域課題の解決という文脈もありますし、災害時の状況把握や初動を早めるためといった防災や災害時対策という文脈もあります。防衛や農業といった分野でも活躍していますから、本当に幅広いです。ただ、私たちは主にBtoBがメインなので、一般的には見えにくいかもしれません。
ドローンは業務機器なので、飛ばすとしても専門的な知識や技術が必要になります。業務用のドローンを買ってきて「さあ仕事に使おう」となっても、すぐ飛ばせるわけではありません。守るべきルールも、知っておくべきマナーも、たくさんあります。

現状だと、一部のスペシャリストや専門家に依頼して、代わりに飛ばしてもらい、仕事で必要なデータを取得することが多いです。ただ、それだけではなかなか世の中に広がっていかないというのが私たちの考えです。
そのため、スペシャリストや専門家の方が持っている知識や技術、ノウハウといった暗黙知を、私たちが言語化し、形式知として体系化してまとめ、世の中に広めています。そうすることで、便利なツールとしてのドローンがさらに広まっていくと思いますし、結果としていまよりも便利な世の中になると考えているからです。
少し前の話になりますが、2015年に首相官邸にドローンが落下したというニュースがありました。それをきっかけに、どのように安全を担保するのかだったり、どのように管理するのかだったり、いろんな議論が起こったんです。その流れで、まずは民間の資格制度ができました。
スカイピークは2017年の設立ですが、その当時は民間資格から国家資格に移行しつつ、段階的に制度整備が進んでいく流れを感じていました。その中で、教育ニーズはなくならないと想定し、将来的に中心になっていくであろう産業分野において教育サービスを事業の中心にしようと考えたんです。

具体的には、専門家の方からドローンを飛ばす際のノウハウを学び、それを体系化していきました。現場で活かせる知見をお客様に提供していくために、まずは私たち自身が現場に触れ、学ばせていただき、正しく理解すること。このプロセスを非常に大事にしてきました。
並行して、講習団体として国交省航空局に登録したり、総務省消防庁と協定を締結していきました。私たちが提供する教育サービスが一定の品質を担保していることを証明するためです。
そして、2022年12月にはドローンを飛ばすための知識や能力を証明する国家資格が誕生しました。それにより、ドローンを安全に飛行させ、産業での活用を促進しやすくなりました。このような世の中の変化に合わせて、私たちはドローン関連の教育ビジネスを軸に、少しずつ事業の幅を広げたり、厚みを持たせていきました。
その際に注意していたのは、しっかりとバランスを取ることです。私たち自身が現場に触れることは大事にしていましたが、自分たちでできる経験や体験はどうしても限られてしまいます。その状態で教育ビジネスをやろうとすると、内容に偏りが出てしまう懸念があります。そのため、私たちのスタンスや考え方、価値観に共感してくださったパートナーの方々にも協力をいただき、偏りが出ないように注意していました。
また、「ドローンに関する教育ビジネス」というと、資格を取得するためのスクールを運営すると思われるかもしれません。私たちもスクールの運営をしていますが、それだけじゃなく、新規でドローンスクールを立ち上げる際のサポートをしたり、独自に開発した教育プログラムを提供したりしています。また、ドローン物流や3D地図を活用した実証実験の実施などを通じて企業の新規事業開発を支援したり、ドローンを業務に活用するための導入支援や運用代行なども行なっています。

「完全にオリジナルか」というと少し語弊があります。というのも、たとえば国家資格であれば一定の均一性が必要なので、国が基本的なものを用意するんです。私たちは基本的な内容にアレンジをするにとどまります。ただ、アレンジをする際には、文字だけのものにイラストを入れてわかりやすくするなどの工夫も含まれます。このあたりは、「難しいことをわかりやすく伝えられる」という私たちの強みが活きる部分なのかもしれません。
それ以外にも、実務でドローンを使う場合は、業務理解や業務知識が求められます。そういった「仕事に活かすための知識やノウハウを提供できる」というのは、私たちの独自性だと思います。ドローンを操縦するためだけではなく、実務に活かすための知識や技術も学ぶことができる。これが私たちがつくる教育プログラムの特徴だと思いますね。
みんなでやっているというのが回答になるかと思います。「みんな」というのは、スカイピークの社員だけじゃなく、いろんな分野の専門家の方々も含めてです。
私たちは会社としては大きくないものの、比較的古くからこの業界で活動してきました。加えて、私たちの考え方に共感いただき、協力してくださる方々がいます。そのため、割と幅広い領域で専門的な知見をカバーできるネットワークがあります。なので、それぞれの専門家の方々にサポートしていただいたり、教育プログラムの監修を手伝っていただくことができるんです。
物流だったらこの人とか、建築はこの人とか、分野によって「この人」という方が結構いらっしゃいます。「業界を発展させるために」や「今以上に便利な世の中にするために」という理由で協力してくださり、濃いお付き合いができているのではないかと思っています。
専門家の方々にとっても、多少のジレンマがあると思うんです。というのは、専門性が高く、優秀であればあるほど、その人に仕事が偏ってしまうということです。持っているノウハウを世の中のために活かしたいという気持ちがあっても、ひとりで対応できる仕事量は限られてしまいます。
そのため、知見を体系化し、正しい情報を広くわかりやすく伝えていくという想いに共感いただき、いろいろな協力をいただく中で、私たちはノウハウを言語化し、イラストなども使いながらわかりやすいものに落とし込む部分を担っているという理解です。

最近では、紙の媒体で伝えるだけじゃなく、「オンラインを活用して均一化した内容を幅広く提供していきたい」という考えのもと、Gakken LXさんとの提携を始めました。国家資格のデジタル化を推進する会社さんとご一緒させていただくことで、より多くの方に専門的な知識や技術を提供できるようにしています。
そうですね。基本的なスタンスはBtoB向けになるかと思います。趣味でドローンを飛ばす人も、仕事で使う人も、ユーザーが増えてくると何かしらの事故が起きる確率が高まっていきます。そうなると、国交省などは「いかに安全を担保するか」「いかにリスクを排除するか」ということを考えるんですね。つまり、ドローンを飛ばす際のルールが明確になっていくんです。
そうなると、趣味でドローンを飛ばす人たちは、資格を取るのが大変なので、やっぱりちょっと面倒になるんです。また、資格を取った後は私たちとの接点がなくなってしまうため、BtoCのほうが長期的な関係性になりづらいです。
ビジネスとしては、お客様と長くお付き合いをしたいというのが基本的なスタンスだと思います。そのため、やはりBtoBを中心に考えるようになります。お客様はドローンを仕事で使いたいので真剣に勉強しますし、内製化したいというニーズもありますから社内で体制づくりを進めたいというケースもあります。ドローンを使った業務マニュアルのレビューをして欲しいという依頼もありますから、BtoBのほうが私たちがお役に立てるポイントが多いんです。

それとは別に、ドローンとは関係ない一般の皆様のことも無視することはできません。なぜなら、ドローンのような新しい技術は、受け入れられる社会的な土壌がないと広まっていかないと考えているからです。
私たちや私たちが仕事でお付き合いをするお客様を「ドローンを飛ばす側」とすると、一般の皆様は「ドローンを飛ばされる側」だと思います。双方の目線を大事にしながら、この便利なツールを世の中に広めていくための取り組みを進めていきたいと考えています。
ドローンを飛ばされる側の目線で、ドローンの法整備の現場について触れさせてください。自動車を例にすることが多いのですが、運転免許や交通ルール、車検といった仕組みがあることで、一定の安全が担保されている状態となり、誰もが当たり前のように自動車を使っていると思います。ドローンの場合は、いまやっと免許と言われるような国家資格ができ、車検に該当する機体認証制度ができてきたところです。交通ルールはいまだ整備中というところでしょうか。
飛ばす側としては「国家資格は必ずしも必要ではないよね」という意見が一定数あるのが現状です。でも、飛ばされる側の目線で考えてみると、それは不安だと思います。自動車であれば、無免許の人が、車検に通っていない車を、ルール関係なく運転しているようなものです。これって非常に怖いですし、危険です。ドローンが当たり前に使われている世の中からは遠い世界だと思います。
私たちは世の中をいまよりも便利にするためのツールとしてドローンを広めていきたいです。だからこそ、世の中に広めていくための動きを取り続ける必要があると考えています。そのため、飛ばされる側の皆様に向けても、教育サービスを提供していきたいんです。だから広報や普及活動にも継続的に注力しています。
一例として、こどもの日に小さなお子様向けのコンテンツをつくり、発信しています�。昨年は未来社会をイメージしたイラストの「塗り絵ドローン」や、小学4年生の女の子が考えてくれた「折り紙ドローンのつくり方」を、会社として協力し、共同コンテンツとして公開しました。
今年は「ピークちゃんと学ぶドローンクイズ」と銘打ち、ドローン博士を目指すクイズもつくりました。誰もが気軽に楽しめるように、コミュニケーションデザイナーさんに企画やイラスト作成などで協力していただきました。スカイピークのHPで無料ダウンロードできるので、よろしければ見ていただけるとうれしいです。
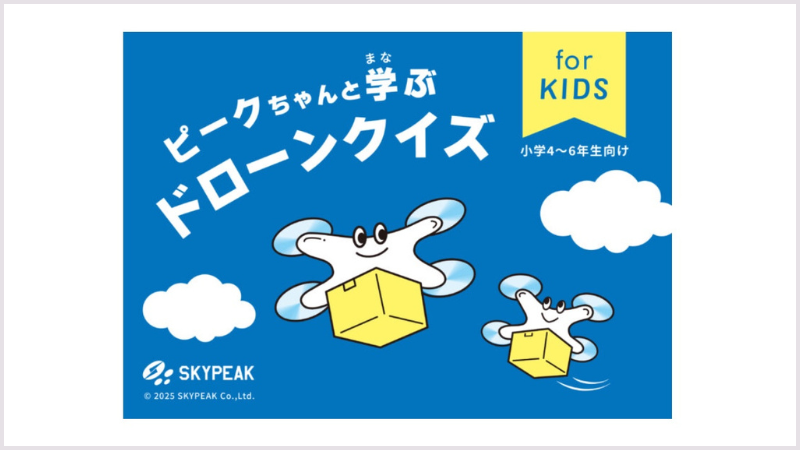
ほかにも職業体験のようなリアルイベントをやったり、noteを使って情報提供したりもしています。裾野を広げてたくさんの方にドローンのことを知っていただくきっかけづくりとして、継続的に情報を発信することは、業界としても重要だと思っています。ドローンが当たり前の便利な世の中にしていくために、直接的なお客様だけでなく、関わる可能性のある多くの方々のことも意識して、さまざまな取り組みを推進していきたいと考えています。
はい。企業向けの研修サービスも一定数ありますし、ドローンを導入するための支援を依頼されることもあります。おっしゃる通り、そういうものも含めて広義の「教育」だと捉えています。
具体的な事業やサービスだと各論になるので、少し抽象度をあげてお話しすると、私たちは『知見と技術とともに未来をつくる』ということをひとつのスローガンとして掲げています。専門家の方々が持つ知識やノウハウを形のあるものにし、それを活用して新しい技術を世の中に広めていくということです。

そのためには、先進的な技術や知見を「検証」すること、検証が終わったものを言語化し、「体系化」すること、最後にサービスとして「提供」すること。これらが必要になると考えています。この三角形をぐるぐる回すことで、新しい技術を広く社会に普及させ、世の中がいまよりも便利になると考えています。
まさに新規事業開発は実証実験から始まることが多く、「検証」というフェーズにおける支援です。たとえば大手の企業であれば研究開発や技術検証の予算があります。そこで、「こういう現場でドローンを使って、こんなことができないかと考えています。プロの立場で技術の検証や導入検討に向けた取り組みをサポートしてくれませんか?」と依頼をいただき、実証実験やテスト業務などを行なっています。
ただ、私たちが実証実験をしたからといって、世の中に広がっていくことはありません。実証実験や専門家との連携を通じて得られた知見を「体系化」し、noteのようなプラットフォームを使ってコラムを書いたりして発信していきます。
発信をすることや教材にまとめることで情報を「提供」しているのですが、お客様のなかには「自社にノウハウをためたい」という企業もあります。そういう企業からは、「社内で研修をする際のプログラムをレビューして欲しい」などの依頼をいただきます。ここで新しい「検証」が始まります。
こういう具合に三角形をぐるぐる回していて、その過程で生まれたひとつの例が、新規事業開発であり、ドローン導入支援という感じです。
私たち自身の現場の経験もありますが、その業界に詳しい専門家とのネットワークを活かしています。たとえば建築業界であれば、一級施工管理技士など、工事や改修の実務に携わっている方々がいますし、法律が関係することは関連手続きで国内随一の行政書士の方に顧問で入っていただいています。
そういったパートナーの方々とのネットワークを活かしているので、網羅性が高く、質の高いサービスが提供できるのだと思います。これまでコツコツと取り組みを積み重ねてきたことから、ありがたいことに信用をいただけるようになってきて、少しずつお取引が増えているのだと思います。
たとえば、海上保安庁に対してドローンの教育訓練を行ないました。いまでもお付き合いを続けていますが、当時は初めての国とのお仕事ということで、色々と勉強になった感慨深い経験です。
ほかにもJR東海とは、実証実験や教育訓練などでさまざまな取り組みをさせていただいています。また、ゼネコンからは建物に関する点検の依頼も来ています。まさに教育を軸に、「検証→導入→運用」と段階的な支援を行なっていると言えるのではないでしょうか。

何か特定の「これ」というきっかけがあったわけではなく、小さなひとつの実績が、次の案件につながり、そういうのをいくつか進めていくなかで信用が生まれ、結果として大きな仕事につながったと考えています。
あと、役割分担みたいな部分もあると思っています。新しい産業や業界には、これまで大手企業のなかでその分野に特化して取り組んでいた方が独立するケースがあります。ドローンにおいても同様で、たとえば機体を開発するハードの会社などは、会社としては新しいものの、代表の方は業界では古くから名前が通ったエキスパートという場合があります。
私たちは、以前からさまざまな現場に飛び込み、多くを学ばせていただきまし�た。そのため、私たちはそういう会社ともつながりがありますし、そういう会社は「スカイピークは業界を盛り上げるためにがんばっている」と私たちを応援してくれることが多いです。そういったつながりがあるなかで、「僕らはより上流の開発に注力するから、実務のオペレーションや教育はスカイピークにお願いしますね」という具合に、ご紹介をいただくことも多いです。
大手企業にとって、スカイピークには「使い勝手がいい会社」というイメージがあるかもしれません。フットワークが軽くて、小回りが効きますし、質を担保しているからです。そういった中で、通常ではなかなかお付き合いできないような上場企業との取引実績ができてきたことで、次第にスカイピークブランドとして信頼をしていただけるようになってきました。
いろんな仕事をする中で、先ほどの「検証」「体系化」「提供」の三角形を回し続ける。そうすることによって、ドローンという新しい技術が、より広く社会に溶け込んでいくのだと思っています。

私たちの生活を有事と平時のふたつにわけてお伝えをします。
まず有事ですが、たとえば南海トラフという重要なキーワードがありますが、そのリスクに備えるときにドローンが活躍します。また、起きてしまったあとの対応がよりスムーズにできるようになります。
自治体ごとに作成されているハザードマップを使えば、それぞれの地域で懸念すべき場所があらかじめわかっていますよね。ということは、いざというときには懸念地点にドローンを飛ばし、映像や画像で状況を把握することができます。「こういう状況になったらドローンを飛ばす」という条件や、飛ばす際のルートを事前に設定しておけば、いざというときに自動で状況把握ができ、そのデータを自治体の災害対策本部で一元管理することも可能です。
これまでは人間が状況を把握しに行っていました。しかし、身の危険もありますし、時間もかかります。その課題をドローンであれば解決できます。災害発生時にはどれだけ初動をはやくするかが重要ですから、まずはドローンで状況が把握できることは、とても良いことだと思います。
いまは、それぞれの自治体がいざというときに備えて準備を進めており、大手企業が中心になって災害対応に向けたシステム開発や情報連携のネットワーク構築などを進めています。私たちは、そういったプロジェクトにメンバーとして参加し、オペレーションづくりの一部などに携わっています。
一言でいえば、生産性の向上に大きく寄与できるはずです。わかりやすい例だと、物流の課題があると思います。運送業の人手が足りない問題ですが、ドローン物流が一般化すれば、これまでよりも効率的な配送ができる可能性があります。
あとは、交通インフラの維持でしょうか。鉄道や高速道路などは、まさに生活するためのインフラです。民間が運営しているものの、「維持しなければいけないもの」だと思うんです。採算が合わないからこの鉄道は廃止しますとか、そう簡単にはできませんから。

そこで課題になってくるのが、交通インフラ維持のための点検やメンテナンスです。特に点検においては「現地で目視で点検する」というのが一般的でしたが、人間が実施するには非常に多くの手間がかかります。そんななか、レベル3.5飛行(※)の制度整備が進んだことで、遠隔で自動で点検できるようになりますから、交通インフラの点検には非常に大きなインパクトがあると考えています。
(※)レベル3.5飛行:一定の条件下において、看板の設置といった立入管理措置を撤廃。これにより、「高所の点検が容易になる」「人手をかけずに広範囲の点検が可能になる」など、点検作業の効率化や人的コストの削減などが期待されている。
増えてきそうな取り組みとしては、インフラの点検のように「遠隔で、自動で、ドローンを使って⚫︎⚫︎する」というものです。
ドローンには、ラジコンの延長線上というイメージをお持ちの方も多いと思います。操縦者がいて、視界に機体を捉えながらドローンを飛ばす、というものです。しかし、遠隔になると、これまでの世界線とはまったく異なる運用方法や操縦スキル、法�規制の理解、安全管理などが求められます。加えて、技術の進化という変数もあります。

技術の進化というのは、たとえば通信技術です。Starlinkのような低軌道衛星通信ネットワークが発達し、山間部や離島、海上でも接続が可能になりました。法律や規制の緩和や整備も進んでいます。そのため、モノを運ぶとか、遠隔で交通インフラの点検を行なうとか、そういったものがだんだん当たり前になっていく動きが進んでいます。
いまはさらにAIの文脈が加わってきています。遠隔と自動に加えて、これからは自律的に飛ぶことが可能になってくるはずで、取得したデータもAIで処理されていく。そうなると、本当の意味での省力化が近づいてくると考えています。
もうひとつ、より重要性が増すものは、やはり「安全」だと思います。ユーザーが増え、ドローンの存在が当たり前になっていくなかで、やはり安全であることは必要最低条件です。どれだけ利便性が上がっても、一度大きな事故が起きてしまうとマイナスのイメージがついてしまいます。そうなると、世の中への普及も止まってしまう。そのため、安全に対する取り組みを通じて意識し続けることが大切ですし、その土壌となる教育にも、改めて力を入れていくことが重要だと思っています。
ドローンが出てきたばかりの頃は、見たことがない機体が空を飛んでいて、わかりやすく「すごい!」という印象だったと思います。あの頃と比べると、いまはマイナーチェンジを繰り返して少しずつ進化しているフェーズだと思います。
「空を飛べることはわかったので、じゃあどんなことに使えるの?」とか「世の中に普及させるにあたって法整備は大丈夫?」とか。そういう細かいチューニングを繰り返しているのが、ここ数年だと思っています。物事が一度に大きく前進するわけではなく、少しずつ少しずつ、日常に具体的に落とし込んでいく時期です。とても地味ですが、今後のために本当に大事な時期だと思っています。
法整備や安全面への配慮がテーマになると、「日本はとにかく厳しい」という意見が一定数出てきます。海外に目を向けると、強気なスタンスのところであれば新しい技術の活用はどんどん進んでいく側面もあると思います。
ただ、個人的には、良いか悪いかは別として、日本は慎重だと思っていて、まずはキチンと検証をしたうえで世の中に広めていくスタンスだと思うんです。これはドローンに限らず、鉄道や航空、自動車もそうだと思うのですが、何か起きてからでは遅いので、慎重に進めていくというのはとても大切だと考えています。
ドローンのような新しい技術を取り入れていく場合も、細かくルールを決めたり、法改正をしたりして、適切に社会に馴染むようにしていく。このスタンスは、時代が進んでも変わらないと思いますし、それで良いと思っています。
代わりにいまの時代に私たちができることは、ルールを正しく理解して、多くの人にわかりやすく伝えていくことです。以前とは比べ物にならないくらい情報発信のハードルが下がっているので、専門的な立場からの情報を世の中に広めていくことはできると思っています。

少なくとも私たちは社会的な信用を積み上げてきたつもりですし、信頼できる情報をわかりやすく発信することで世の中に正しい理解が広まると信じています。社会的な安全を担保できるようになると思いますし、私たちの取り組みを応援してくれる人も増えてくるはずです。いまの時代に信頼性の高い発信を続けることは、私たちの役割というか、責任なのだと個人的には考えています。
新しい産業だからこそのやり甲斐があると思っています。というのも、私たちのような決して大きいとは言えない会社が、国や自治体、大手企業など簡単にはお取引ができない相手とお付き合いができるのは、刺激的です。
個人的には、期限を切って設定したゴールまでがんばるより、終わりがないほうが燃えるタイプなので、このままどこまでいけるか挑戦し続けたいと考えています。
競技でフットサルをやっていたときも、「強いチームに入って大会で優勝したい」よりも「強いチームを倒したい」と思うタイプだったんです。自分の中ではそれと似ていて、スカイピークがやりたいことや私たちの価値観を大事にしながら、どこまでいけるのか。共感してくださっている方々を大切にしつつ、少しずつフォロワーを増やしていって、果たして自分たちは世の中にどれだけの影響を与えることができるのか。そういうことにチャレンジしていきたいです。
先ほど「安全」の話を例に出しましたが、時代に合ったテーマに対して具体的な打ち手をどんどん進めていって、「産業ドローンで教育をしっかりやるならスカイピークだよね」というポジションをきちんと確立したいですね。
わかりにくい、というのが正直なところです。空を見てもドローンが飛んでいるわけではないので、日常生活ではまだ実感しにくいというのが本音です。ただ、多くのお客様と接する中でいただく「ありがとう」「助かったよ」という一つひとつの言葉は純粋にうれしいですし、目の前の誰かの役に立っているということは少なからず実感しています。
航空に関わることは、どうしても時間がかかる分野です。そのため、自分たちだけで、すぐに世の中を変えられるほど甘くはないと思っています。ただ、日々たくさんのきっかけやご縁があって、それらがいまにつながっていること。社員であったり、お客様であったり、協力会社やパートナーの方々であったり、いろんな方から期待をいただいていること。それらに対しては、本当にありがたいですし、できるだけのことをしたいという気持ちがあります。
ドローンという新しいツールで世の中をもっと便利にしたいという想いはありますが、そのための方法論としては目の前の��一つひとつの案件で一生懸命がんばるしかないと考えています。結局はその積み重ねで、小さな良い変化が少しずつ広がっていくはずなので。
自分たちができる範囲のなかで最善の努力をすることで、その努力が、いつになるかはわからないですが、いつかどこかで何かにつながっていく。何かにつながったときに、これまでよりも便利になったり、従来は難しかったことが簡単になったりしたら、うれしいなと思います。
足の長い仕事だと思っているので、すぐにわかりやすい成果が出せるとは考えていません。ただ将来的に、「スカイピークがあって良かったな」と言ってもらえたら、それだけですごくうれしいし、そのためにいまを一生懸命がんばっています。
自分たちは裏方で構わないんです。ただ、スカイピークがやったことがきっかけで、世の中が少しでも良い方向に進んで行ったとしたら、それは素晴らしいことだと思います。そういう気持ちでこれからもがんばっていこうと思っています。


株式会社ディプコア 代表取締役CEO
インタビューで高野代表がおっしゃっていたことのなかで、生産性向上の話が印象的でした。これまで人間が行なっていたことをドローンに任せることで、たとえば、これまでは1日かけて行なっていた建物の外壁点検が数時間で済むようになる。自動化や自律飛行の技術が進めば、1人で複数台を操縦したり、人が現地にいなくてもドローンを飛ばせるようになる。そうなれば、業務効率の向上やインフラの維持に大きなインパク��トが出ると思います。 今後少子高齢化が加速する日本社会においては、できるだけ早い段階から生産性向上のための施策を推進することが不可欠だと思います。その一部分を、ドローンのような新しい技術が担うことになるのではないでしょうか。ドローンの社会実装に取り組む同社のような存在は、この先の日本社会を支えるひとつの希望になると感じました。

2024.11.29 公開

2025.11.10 公開

2025.03.28 公開
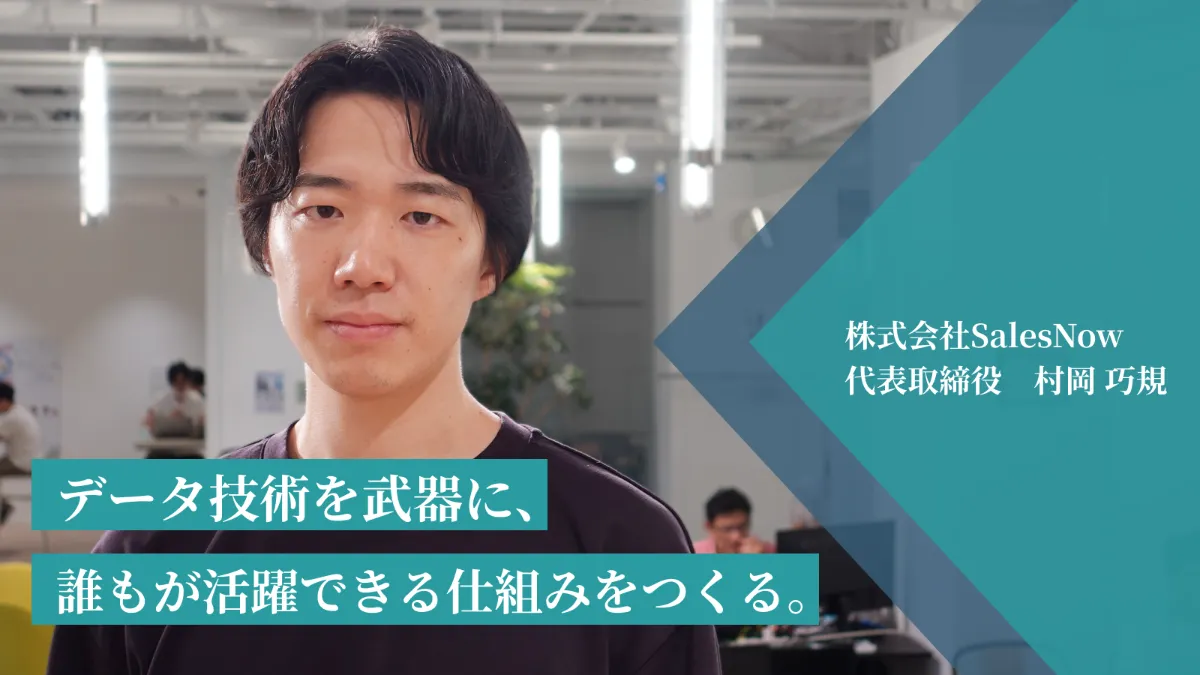
2024.08.01 公開

