
歴史を変えるモノづくりがしたい、その志で空飛ぶクルマに挑戦する福澤。あらゆる経験を学びに変えて、狙うはグローバルでのカテゴリーナンバーワン。
2024.11.29 公開

2024.11.29 公開
株式会社SkyDrive 代表取締役CEO 福澤 知浩
設立:2018年
事業内容:空飛ぶクルマ(電動垂直離着陸航空機(eVTOL))の開発・製造・販売・運航サービス等

STRIVE 代表パートーナー
投資家の世界では、「must haveに投資しろ、nice to haveには投資するな」というのはよく言われることです。それはもちろん一つの真理ではあると思います。ただし、その基準だと“空飛ぶクルマ”は、現時点では、完全にnice to haveです。しかしながら近未来はわかりません。5年後、10年後には、“空飛ぶクルマ”が当たり前のもの、must haveなものになっているかもしれません。もっと言うと、私自身がそういう世界を創りたいと思ってSkyDriveに投資させて頂きました。 SkyDriveの福澤さんは、そんな世界の実現に向けて、泥臭くハードワークを厭わずに日々活躍してくれています。簡単に実現しない世界であるからこそ、これからもやりきって欲しいという応援の意味も込めて推薦しました。
東京大学工学部を卒業して、トヨタ自動車に入社しました。僕はもともと、「新しいモノづくりがしたい」「歴史を変えるようなもの、世界中の人にとって意味があって、みんなの日常的な幸せのレベルが上がるものをつくりたい」と考えていて、トヨタならこの想いが実現できるかもしれないということで就職先を決めたんです。
トヨタではグローバル調達の仕事をしていて、多くの現場でトヨタ生産方式を用いたカイゼンを経験しました。並行して、在職中から、週末に活動するボランティアの有志団体にも所属していたんです。自分たちも楽しめて、かつ次世代の子どもたちに意味のあるモノづくりをしようというコンセプトの団体でした。
その団体で、若手のエンジニアが集まって何をつくるかアイデア出しをしたことがあったんです。その中で「空飛ぶクルマをつくったらおもしろいんじゃないか」という案がありました。アイデア出しをしたのは2015年で、当時は5年後に国際的なスポーツイベントが東京で開催予定でした。そこで「開会式で飛べたらいいね」という案も出てきて、みんなで盛り上がったんです。そこから、開会式で飛ばすことを目標に空飛ぶクルマづくりがスタートしました。

最初は手のひらサイズのものから始まり、少しずつ大きなサイズ��のものをつくっていきました。なかなかうまく飛ばないと苦戦をしていたときに、もう40年くらいラジコンを自作しているラジコン業界の重鎮みたいな人が僕たちの有志団体に参加したんです。彼が加わったことで開発が加速して、ゆらゆらと機体を浮かせられるようになりました。
このとき空飛ぶクルマの開発に関わっていたのは10人〜20人くらいです。みんな本業を持っていて、毎日作業場に来る人はほとんどいませんでした。
あるとき、トヨタグループから協賛金をいただけることになったんです。新聞の取材にも来ていただいて、「空飛ぶクルマ、トヨタが支援」みたいなタイトルで紙面に載ったんです。すると、結構な反響がありました。「おもしろいことをやっている団体がある。一緒にやりたい」ということでメンバーが100人くらいに増えたんです。開発ができる人はもちろん、事業のことがわかる人やPRに強い人など、さまざまな強みを持った人が集まる団体になり、いろんなことが進みやすくなりました。
ちょっと話がそれますが、ボランティアの有志団体の時に、合計で2億円の協賛金が集まったんです。週末に活動している団体で、まだプロダクトも完成していないのに、これだけのお金を集めたのはすごいことだと思っていて、みんなのパワーが結集したからこそだと思います。
この時点で2018年なのですが、開発の進捗は微妙な感じでした。機体を浮かすことはできたものの、目標にしていた「開会式で飛ばす」を達成するには土日だけ開発をしていても間に合わないという状況だったんです。そこで、週末だけのボランティアじゃなくて、もっと本腰を入れてやった方がいいんじゃないか、と考えるようになりました。

そのとき、海外でも空のモビリティを開発する会社が出てきていて、「ドローンの次はこれが来るかも」という雰囲気がありました。そのため、投資家をまわってみて、資金が集まれば法人化を検討しようという流れになったんです。
ただ、投資家に説明するには、いろんな資料が必要になります。そこで、有志団体のなかで詳しい人を見つけて、一緒になって事業計画と資本政策をつくりあげ、投資家をま�わっていきました。そうしたら最初の資金が集まったので、「じゃあ本格的に事業として空飛ぶクルマをつくろう!」ということで、会社を立ち上げることにしたんです。
週末に活動するボランティアの有志団体から、会社としてフルタイムで開発をするというのは大きな変化になります。当時のメンバーの中には、もちろん本業がある人もいたので、各自が「SkyDriveの社員になるか」の意思決定をしました。結果、100人のメンバーのうち僕も含めた5、6人が初期メンバーになり、2018年に株式会社SkyDriveとして新しいスタートを切りました。
機体開発を進めながら資金集めを行ない、法律や規制をどのようにクリアしていくかなどの検討をはじめました。
機体の価格をいくらにするか、お客様を乗せるとしたらチケットの価格はどうするのか。ただ空飛ぶクルマをつくるだけではなく、事業にするためにはそういうことも決めていかなくちゃいけません。加えて、そもそもどこから飛ばすの?とか、飛ばすためにはどこに許可を取らなきゃいけないんだっけ?ということも詰めていく必要があります。こういったさまざまな事案を、少しずつ前に進めていきました。
僕たちの機体は航空機のカテゴリーに入るのですが、航空機の経験がある人から言わせると、「この認証を取るにはこれくらいの期間が必要」といった相場があるんです。ただ、僕たちの空飛ぶクルマは固定翼じゃないし、動力は電池だし、「航空機」という同じカテゴリーではあるものの、飛行機とは異なる点が多い。みんなの知見が活かせる部分と、そうじゃない部分があるので、手探りしながら前に進んでいく感じでした。手探りで進んでいるというのはいまも変わらないですけど(笑)。
最初のターニングポイントは有人飛行に成功したことですね。
2018年にSkyDriveを立ち上げたときは、機体を浮かせることができたという状態です。そこからテストするところも広い場所に変えて、機体を大きくしていきました。また、人を乗せるので安全性が非常に重要になります。安全性を高めるにはどの部品が良いか、制御はどうするか、そういうことを研究していきました。加えて、機体やシートのデザインも進めていきました。見た目は絶対にかっこいい方が良いで�すし、シートは快適な方が良いので、デザインにもこだわっていきました。
こういうことを同時並行で進めていき、2019年12月に初めての有人飛行に成功したんです。外部には非公開のテスト飛行でしたが、僕たちの機体が人を乗せて空を飛びました。短い時間だったものの、空飛ぶクルマとして一歩目を踏み出した感じでした。
初めての有人飛行に成功した後、2020年4月に現在のCTOである岸がSkyDriveに入社します。彼はもともと三菱航空機の副社長で、MRJのチーフエンジニアでした。航空機のスタートアップが日本に存在していることに興味を持ってくれたようで、大企業から小さな僕たちの会社に来てくれたんです。彼の加入で、日本の航空機業界でのSkyDriveの認知が大きく上がりました。同時に、技術的にも一段上のステージに移ることになります。
岸の加入の少し後ですが、2020年8月に公開有人飛行のデモフライトを行ないました。そもそも「開会式で飛ばす」という目標を掲げていたのですが、スポーツイベント�そのものが延期になってしまった。ただ、僕たちだけでもいいからやろう!というということで、メディアにも公開してデモフライトをしたんです。ネットを張ったテストエリアの中でしたが、人を乗せて約4分間の飛行に成功しました。ここから、開発が次のステージに移っていくんです。

次のハードルは認証を取ることでした。安全性が担保されていることを証明する必要があったんです。ここでの「安全」は墜落につながるような事故が起きないことを指すのですが、数億時間飛んでも事故が起きないことを航空機は定量的に証明しているんです。
「空飛ぶクルマ」でも、この安全性を証明する必要がありました。証明するための過程が本当に大変なんです。たとえば、モーターの安全性を証明するには、「数千時間モーターを回し続けても異常が出ない」というデータを出す必要があります。加えて、モーターの設計書については、設計手順ごとに、各工程においてどのような安全管理をしているのかをすべて書面で示すことが求められます。こういったことをたくさん積み重ねていき、最終的に数億時間飛んでも墜落しないということを証明するんです。
当時の機体は、日々いろんな部品をつけたりはずしたりしながら、テストを重ねていくやり方でした。ただ、機体が大きくなると「とりあえず試してみよう」ができなくなります。安全性の証明も必要になってきますから、設計の仕方を見直す必要が出てきたんです。
そこで、岸の存在が非常に活きてきます。彼の入社は航空機業界でちょっとしたニュースになっていましたから、「岸さんと一緒に仕事がしたい」という航空機のエンジニアがSkyDriveに入社してくれました。そして、彼が中心になって設計の仕方を航空機ベースのものに変えていってくれたんです。
空飛ぶクルマを実現させるために必要なステップだと考えていたので、ためらいはありませんでしたね。これはハードウェアのスタートアップあるあるだと思うのですが、どこの会社も最初はすごい技術を持ったスーパーエンジニアのような存在がいるケースが多いです。ただ、実用化をする際に壁に当たる。センスや直感といったものはモノづくりにおいて非常に大切なのですが、それを数字や言葉に落として、安全性や耐久性について世の中の承認を取ることが難しかったりするんです。
軌道修正することなく直進していくと、結果的にプロダクトが世��に出ないまま終わってしまったり、スーパーエンジニアが辞めてしまって「モノはあるけど設計図がない」といった状態になってしまい、仕様を解明するのに膨大な時間を使ってしまったりします。僕たちにとって設計の変更は乗り越えるべき壁だったので、ここはがんばろうと覚悟を決めました。
変更の過程では、社内に混乱が生まれました。というのも、航空機の経験者が出すシミュレーションは、ラジコンの玄人にはなじみが少ないからです。「理論と実践は違う」みたいな感じで、意見の食い違いが起きました。
そのため、どこで意見が食い違っているのか、どれくらいの差が出ているのか、そういうのをひとつずつ確認しながら解消していったんです。「この係数の出し方が少し雑だったね」とか「制御の話をしていたけど、ここは構造の話だね」という感じで、丁寧に解きほぐしていきました。あるべき設計ができる状態になるまで、2年くらいかかりましたね。
僕たちも「スタートアップあるある」に気をつけていたものの、やっぱり意見の食い違いが起きてしまったし、しっかり壁にぶち当たったという感じです(笑)。結局は、困っていることをひとつずつほぐして解決するしかありません。いまでは、ラジコンエンジニアも航空機エンジニアも、それぞれが役割分担しながらシナジーを出してくれています。
次のターニングポイントは2023年の1月ですね。当時の僕たちは基本設計に苦戦していました。そのタイミングで、アーノルドがSkyDriveに加入します。彼はドイツのeVTOL(垂直離着陸機)メーカーであるVolocopter社のCTOだった人物です。簡単に言えば、eVTOLの分野で世界トップクラスのCTOだった人が、SkyDriveに来てくれたということです。
彼の加入によって、当時直面していた基本設計の課題はクリアになり、技術レベルが一段上がり開発にも加速がつきました。
もともと優秀なエンジニアの獲得には注力していました。日本はもちろん、世界にも目を向けてサーチしていたんです。海外にも空飛ぶクルマを開発している会社がありますし、1万人くらいの技術者がいます。1万人くらい技術者がいたら、そのうち数人くらいは僕たちに興味を持ってくれるだろうと考えていました。
いろんな技術者とコンタクトをとっていたのですが、そのうちの一人がアーノルドでした。彼はそのときアジアのマーケットに興味を持っていて、「eVTOLはこれからアジアで伸びる」と考えていたようでした。そこにタイミング良く僕らがアプローチしたんです。
他の会社も彼にコンタクトを取っていると聞いたので、彼に選んでもらえるようにできることはいろいろやりました。CTOの岸にドイツに飛んでもらって接点を持ったり、経営者全員で「I LOVE YOU!」と言っているメッセージ動画を送ったりもしました(笑)。

ありがたいことにこちらの気持ちが通じて、2023年1月にアーノルドが加入し、SkyDriveは一段上のステージに進むという流れです。
空飛ぶクルマの変化としては、2人乗りから3人乗りへの変更です。2人乗りの機体は、事業的に勝負するのが難しいという課題がありました。パ��イロット1人とお客様1人になるため、どうしてもチケットが高くなってしまいます。収益性の高い運航を実現するために、2人のお客様を乗せられるようにしたいということで、3人乗りの機体に軌道修正しました。
社内の変化は、開発力の大幅アップがあります。彼の加入によって、グローバルで航空機エンジニアの採用が加速しました。インドネシアやインド、トルコのエンジニアが多いのですが、「アーノルドがいるなら」という理由でSkyDriveに来てくれています。
もう一つの変化としては、組織づくりでまた壁にあたりましたね(笑)。ラジコンエンジニアと航空機エンジニアが一緒になったときの学びから、お互いの意見が食い違わないように前もって通訳スタッフを採用したんです。こういう場合はパートタイムでの採用が多いそうなのですが、何かあったときにすぐにサポートしてもらえるようにフルタイムの社員を10名弱採用しました。

おかげで仕事上のコミュニケーションではそこまで困らなかったものの、いま思えば生活面のサポートについてもっと考えておけば良かったという反省があります。というのも、開発施設が山奥にある�のですが、車じゃないと行くことができません。日本で使える免許証がない人もいるので、「じゃあどうする?」という課題に直面しました。今回もちゃんと壁にぶち当たって、その経験からいろいろと学ばせてもらっています。
僕らはいま、グローバルでカテゴリーナンバーワンのポジションを狙っています。この目標に対しては、現状で先頭集団に入ることができているという認識です。
注視しているのは、空のモビリティを開発している企業のランキングです。海外のコンサル会社がまとめているもので、リアルタイムで更新されるものがあるんです。ファイナンスの状況や、実用化までの目標に対して開発がどこまで進んでいるか、プレオーダーがどれくらい入っているかなどの指標があります。
空のモビリティは世界中で試行錯誤が続いていて、機体についてもまだ最適解が出ていない状況です。飛行機のような固定翼のものもありますし、僕たちのような小型のマルチコプタータイプのものもあります。ターゲットにしているのは、小型マルチコプターのカテゴリーでナンバーワンになることです。SkyDriveは常にトップ3に入っていて、十分にトップが狙えると考えています。
他2社は2人乗りなのに対して、僕たちは3人乗りです。そのため、商用化されれば事業的な評価は僕たちの方が高くなると見込んでいます。あとは僕の主観ですが、機体のかっこ良さではSkyDriveがダントツで1位だと思っています(笑)。

グローバルで認証を取得している会社はまだないので、いまはそのために動いているところです。ちなみに、2024年の6月には、アメリカ連邦航空局で「空飛ぶクルマ」の型式証明(国土交通省が航空法に基づき、新たに開発された航空機について、その型式ごとに設計、構造、強度、性能などが所要の安全基準及び環境基準に適合していることを証明するもの)の申請が正式に受理されました。
これまでに数々のメーカーが空のモビリティに挑戦していますが、途中で挫折するのは大きくふたつのパターンがあります。まずは認証が取れずに終わってしまうパターン。そしてもうひとつは、認証が取れたけれど機体が売れずに終わっていくパターンです。認証は一つずつクリアしていくことが大切ですし、プレオーダーは現時点で250以上獲得できているので引き続きがんばっていきます。しっかりと指標をクリアし、グローバルで存在感を出していくことが短期的な目標ですね。
万博は、複数の機体が空港でもない場所で飛ぶ世界初の場になる予定なので、とても先進的な取り組みになると思います。万博で飛ばす予定があるのは4事業者で、僕たちはその1社に入っています。国産の機体はSkyDriveだけなので、日本代表として世界のトッププレイヤーに入っていることをアピールできるようにがんばりたいと思っています。
事業化までに時間がかかるというのは、個人的にはあまり感じていません。自動車メーカー出身ということもあり、そういうものだと思っているところがあります。自動車だって、新しいタイプを��ローンチするまでに6年とか8年とかかかりますから。
インターネットのサービスと比べると、相対的に時間がかかるというのはあると思います。僕たちは、β版を出して、使ってもらいながら改良していくというやり方はできないので。その代わり、世に出たらみなさんが本当に驚くようなインパクトを提供できると思います。これまでの移動の当たり前が大きく変わるので。
世の中に与えるインパクトが大きいぶん、難しい仕事だと思います。ただ、「どうすればできるようになるだろう」と突破口を考えるのが楽しいので、いつも熱量高くいられるのかもしれません。

もちろん僕だって100点じゃないですし、そもそも人間なので気持ちが乗らないとか、調子が悪いという日はあります。経営をしていると次から次に壁がくるので、気分が落ち込むこともあります。個人的に気をつけているのは、壁を経験したときに得られた学びをちゃんとストックしておいて、次に活かすということです。
簡単なことで言うと、体が疲れていると感じるときには、ストックしてある「ちゃんと寝る」「サウナに行ってリフレッシュする」という学びを使います。仕事をしていて気分が乗らないときは「カフェに行く」とか「ジムで身体を動かす」を使います。
経験の中で学びを得て、ひとつずつストックし、状況に合わせて使っていくという感じですね。もちろん、過去のストックが通用しないときもあります。その場合は、ちゃんとふり返りをして学びにする。「こういうのは何かが起きてからの対応じゃ間に合わないから、前もって予防をしておかないといけないな」という学びもあります。そういうものも含めてストックしていくんです。
CTOの岸が入社してくれて、ラジコンエンジニアと航空機エンジニアの意見が食い違うということがあったとき、人事のメンバーに大きな負荷がかかりました。双方のエンジニアから人事に対して「なんでこうなってるんだ」「会社としてどうするんだ」といった声が集まったみたいです。

経営としてちゃんとフォローができていなかったことを反省しました。人事や管理部門など、技術以外の部門に対して、自分は何ができるだろう。自分がフォローするのか、フォローが得意な人に任せるのか、どっちがいいだろう。そういうことをふり返り、学びにしていったんです。
ダイバーシティは進んできたと思っているので、次はインクルージョンを強化していきたいと考えています。インクルージョンが進めば、さらに生産性が上がると思っています。
会社としては「Beyond Borders」というバリューを掲げています。超えたいボーダーはふたつあって、ひとつは自分の中にある「これが普通だよね」という常識です。それを軽やかに超えていこうというもの。もうひとつは、相手と自分でバックグラウンドが違うので、違うものを持った個人同士がチームになることで、各自のこれまでの経験や価値観を超えていこうというものです。
僕たちは空飛ぶクルマというこれまでにないモノづくりに挑戦しています。いわゆるゼロイチに直面することばかりで、外的環境を含めた変化も多いです。そのため、このバリューを大切にしながら、世の中のみんなが驚いて、世界が変わるようなプロダクトをつくっていきたいと思っています。

2030年くらいには、小型マルチコプターの領域でグローバルナンバーワンになっている計画です。空を飛ぶとか、空を自由に移動するという、小さいころに多くの人が思い描いた未来は、もうすぐ実現します。まずはそこまで高い熱量でがんばろうと思います。

株式会社ディプコア 代表取締役CEO
今回は、事業化まで長い期間がかかり、認証の取得にも多くのハードルがある市場で戦う経営者へのインタビューでした。 いつもお聞きしているように、「これまでのハードシングスは?」という質問をしたのですが、「自分の中にはハードシングスというものはないですね」との回答。「あのときは、あのタイミングで、こういうことをしておくべきだったなというふり返りはします。それが学びになり、今後に活かされていく。未来に活かせる学びが増えていくんです。だからハードシングスだと思ったことがありません。何か問題が起きたらそれは自分の責任なので、同じ問題を起こさないように自分で何とかするしかないですよ(笑)」とのことでした。 福澤社長のような経営者にお会いするたびにいつも思うのは、物事はどういう角度で捉えるかによってまったく変わってくるということです。他責にせず自ら反省するも、そこで落ち込まず、すぐに未来の糧につなげていく、夢に向かって邁進する思いの乗った言葉から熱を感じました。
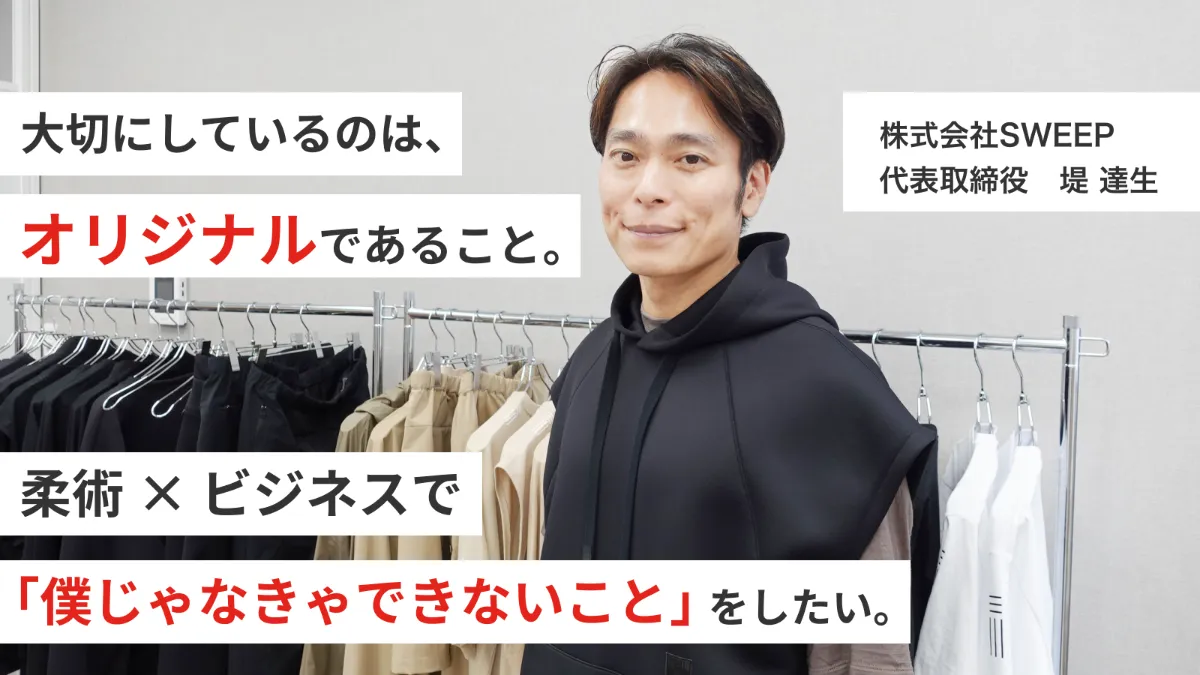
2024.10.01 公開
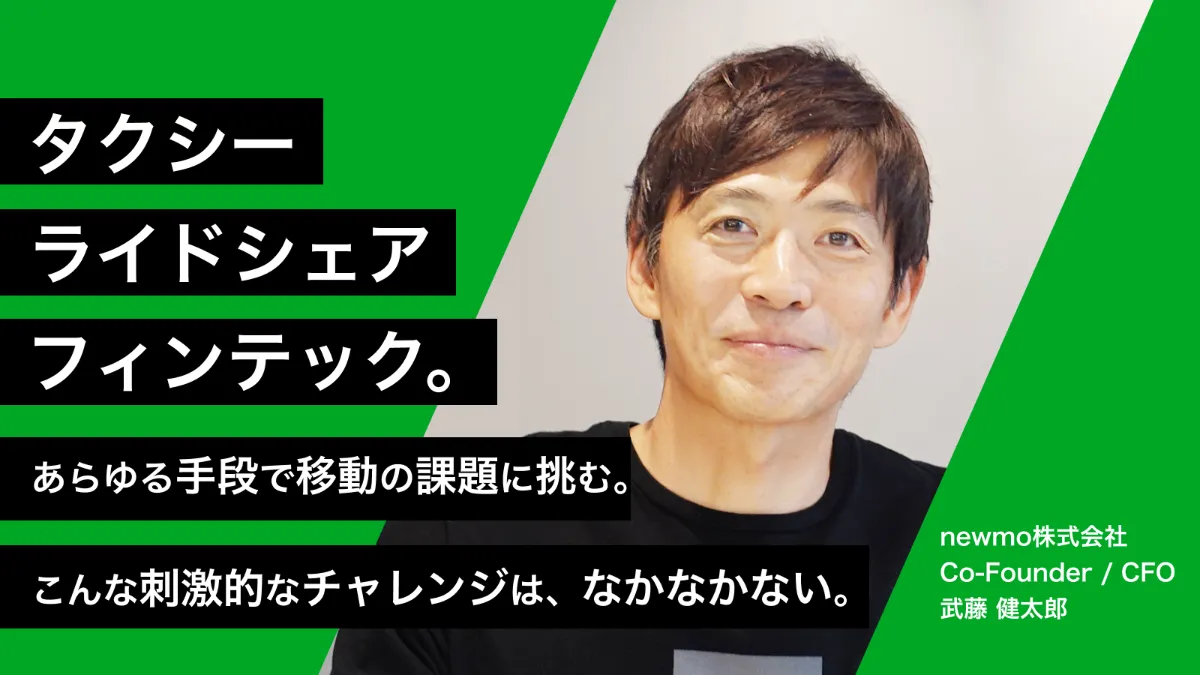
2024.09.03 公開

2024.11.22 公開

2025.08.01 公開

