
2030年をゴールに国際競争が続く量子の分野。日本発スタートアップQunaSysが描く世界での勝ち筋。そして、いまだからこそ得られるキャリアの魅力とは。
2025.03.28 公開

2025.03.28 公開
株式会社QunaSys COO 松岡 智代・CFO 菅谷 俊雄
設立:2018年
事業内容:量子コンピュータを用いたソフトウェア開発、量子技術関連コンサルティング

JICベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社 ベンチャーキャピタリスト
QunaSysは量子コンピュータを有効に活用するためのソフトウェアやアルゴリズムを開発するスタートアップです。化学業界や電機業界をはじめとした名だたる大企業と量子コンピュータ活用に向けたプロジェクトを進めるほか、内閣府や文科省など国のプロジェクトでも重要な役割を担うなど日本の量子コンピュータ業界を牽引する1社であり、今後のますますの活躍を期待しています。

株式会社QunaSys COO 松岡 智代
京都大学大学院工学��研究科材料化学専攻博士課程修了(Ph.D)。新卒で経営コンサルティングファームのArthur D Little Japanに入社。化学・素材・自動車を中心とした製造業に対して新規事業戦略や中長期戦略の策定支援に従事。2020年、QunaSysに入社しCOOに就任。仕事の軸にあるのは「化学×ビジネス」。「物事をいかに説明するか」に強い関心がある。好きなタレントはタモリさん。最近ハマっているのは、石。

株式会社QunaSys CFO 菅谷 俊雄
東京大学経済学部卒業後、投資銀行でクロスボーダーM&Aや資金調達業務に従事。金融の経験を積んだ後、2019年にスタートアップの世界へ。モビリティ関連スタートアップでCSO、COOとして上場に貢献。2023年、QunaSysに入社し、CFOに就任。趣味は登山やボクシング。最近は週に4〜5回はジムに通っている。米国で弁護士としての経験を持つ。
▶︎ 松岡 :QunaSysは2018年創業の会社です。現CEOの楊(ヤン)と大阪大学の藤井教授や御手洗准教授が中心となって立ち上げました。量子物理学の知見を活かして、これまでのテクノロジーでは成しえなかったことを実現するためにつくられた会社になります。
「量子」や「量子コンピュータ」という言葉は、最近ではたまにメディアでも出てくるようになりましたが、まだまだ新しい分野です。従来のコンピュータ産業は、その大きな領域のなかでハードウェアやミドルウェア、ソフトウェアと、ある程度カテゴリーが分かれていると思います。ただ、量子コンピュータの世界はそこまで明確に線引きされているわけではありません。これから産業としての形をつくっていくフェーズにある、新しい分野だと思っていただければ良いと思います。
▶︎ 松岡 :まず量子コンピュータに関わるプレイヤーは、ほとんどが先進国です。ただし、日本と米国ですごく大きな差があるわけではありません。量子コンピュータそのものをいわゆる「ハードウェア」とした場合、大手ITベンダーがしのぎを削って研究開発を進めています。IBMやGoogle、日本だと富士通などの会社です。ほかにも大学発などのスタートアップがいて、なかには上場する企業も出てきています。
ハードウェア上で動作するミドルウェアやソフトウェアを開発しているのがQunaSysですが、この領域のプレイヤーはグローバルでもそれほど多くありません。なぜかというと、量子コンピュータ上で動くソフトウェアのアルゴリズムを理解できる人材は、世界的に見ても少ないからです。
5年ほど前の時点では、この領域の研究者は世界で500人に満たないと言われていました。もちろん、いまはもっと増えていると思いますが、アルゴリズムを理解して研究開発を進めていける人材が非常に少ないということは変わらないと思います。
また、用いる計算による棲み分けがあり、目的によって結構な違いがあります。そのため、同じようなソフトウェアを開発してみんなで競合しているという感じではありません。ミドルウェアやソフトウェアをやっているQunaSysのような会社は、日本では10社もないと思います。
▶︎ 菅谷 :「従来のコンピュータと何が違うか」という観点で言うと、量子コンピュータは情報の処理の仕方が異なります。従来のコンピュータは「0」か「1」の二進法で情報を処理していくのですが、特定の状態をひとつずつ計算するため、処理できる範囲が限られたり、処理に時間がかかったりします。一方で、量子コンピュータは「0」と「1」を同時に扱うことができ、同時に多くの情報を処理することが可能です。
従来のコンピュータは「0」か「1」なので、地球上で例えると北極と南極でしか動かせないようなイメージです。でも、量子コンピュータは地球上のどこでも動かせる。だから、計算のパワーがケタ違いなんです。

その代わり、自然原理を使って計算をするので、量子コンピュータは外部のノイズの影響を受けやすいという特徴があります。少しでも外部から影響を受けるとエラーが出てしまうため、エラーの発生やノイズの影響をなくすためにはまだまだ開発が必要です。そのため、いま世界中でその競争をしているところになります。
従来のコンピュータと量子コンピュータを比較して、どちらが優れているかという話ではありません。それぞれを併用し、お互いの得意分野を活かすことで、従来のコンピュータだけでは成しえなかったことができるようになると言われています。
▶︎ 菅谷 :量子コンピュータの多くは摂氏マイナス200℃以下、ほぼ絶対零度に近い極めて温度が低い環境で動作します。これはいろいろな理由があるのですが、簡単に言うと量子は熱や電磁波の影響ですぐに情報が壊れてしまうので、それを避けるためです。周囲のわずかな振動や電磁波、温度変化にも影響を受けるほど、非常に繊細な性質を持ちます。代わりに、特定の分野においては非常に高いパフォーマンスを発揮します。
現代のスーパーコンピュータでも困難な分子レベルの物質のふるまいを、量子コンピュータなら「仮想の世界」で再現することが可能になるかもしれません。極端なたとえを使えば、仮想空間の中に「もうひとつの小さな地球��」のような環境をつくり、その中で自然現象をリアルに再現するような未来も想像されます。
何か新しい物をつくるとした場合に、現実で試す前にサイバー空間でその可能性を検証することができると期待されています。これにより、リアルな世界ではコストやリスクの面で難しかった実験も、仮想環境で事前に試すことが可能になります。たとえば、環境負荷の小さい材料やこれまでにない新しい素材の発見・設計といった分野での応用が注目されています。
▶︎ 松岡 :私から少し専門的なことをお伝えすると、量子コンピュータはどんな計算にも強いわけではなくて得意分野があります。たとえば、CAEの計算(コンピュータ上で製品の設計データに各種の条件を与え、数値解析によって構造や性能を仮想的に評価・予測する手法)であったり、素因数分解、最適化、量子化学計算、機械学習などが量子コンピュータの得意分野になります。
CAEの計算だと、自動車や建設の分野で活かすことができます。物体に何かの力がかかったときにどういう構造にしておけばいいか、といった計算をするのですが、現在のコンピュータだと大きな規模で計算しようとするとラフになりますし、精緻にやろうとすると小さな規模になってしまう。これを、量子コンピュータを使って大規模かつ精緻に計算できるように研究が進められているところです。
また、風の向きや力の大きさを予測して計算するのはすごく難しいんですけど、量子コンピュータを使えば従来より高い精度で計算できるようになります。風力発電の発電量予測などにも使えますし、地球規模の環境予測もできるようになると言われています。
ちょっと話がそれてしまいますが、最近聞いた天気予報の話があります。天気予報ってみなさん見ていると思うのですが、10日後の天気とかだと予測の部分が大きいから信じている人は多くないと思うんです。でも、シミュレーションの精度が上がることで「10日後の予報でも絶対に当たります」となると、私たちの日常の行動って変わると思うんです。QunaSysとしても、そういうアプリケーションを世の中に出そうとがんばっています。

量子化学計算で言えば、たとえば創薬や製薬の分野で活躍すると考えられています。お薬が身体の成分とどうくっついて、どのような効果が見込めるのかといった解析やシミュレーションに使えるからです。
お薬の成分の活性予測を2倍とか3倍の精度でできるようになると、これまでは3粒飲んでいた錠剤が1粒で済むようになります。量子コンピュータでちゃん��と計算することで、そういうインパクトを世の中に提供できるようになるかもしれない、ということです。そうなれば、お薬をたくさんつくらなくて済みますし、医療費をおさえることができるはずです。何よりお薬を飲む方の負担を減らすことができます。そういう未来を目指して、がんばっています。
▶︎ 松岡 :私は、もともと「物事をどう説明するか」にとても関心があったんです。化学に興味を持ったのも、「物事がなぜそうなっているのか」を理解したかったからです。思い返せば小さい頃から本とか図鑑が大好きで、詳細にいろんなことを調べて追求していくタイプでした。そういう学習モデルを持って生まれてきたんだな、という気がしています(笑)。
就職したコンサルティングファームでは化学や素材、自動車などの製造業の企業に向けて仕事をしていたのですが、2017年くらいから化学��メーカーで量子コンピュータが話題になっていたんです。調べてみると、楊と御手洗だけでやっていたQunaSysが出てきて、量子コンピュータとはどういうものなのかをヒアリングに行ったのが最初の出会いになります。
個人的には、「実直で地に足がついた良い会社だな」という印象があって、いろいろと手伝うようになりました。そして、シリーズAの資金調達をした頃に、さすがに人手が必要だということで、「一緒にやりませんか?」と誘っていただいたんです。私も「コンサルを出て違うことにチャレンジしようかな」と考えていたときだったので、そのままQunaSysへの入社を決めちゃいました。
▶︎ 菅谷 :僕は前職のモビリティ関連スタートアップが上場することになり、一つの区切りがついたので次の挑戦の場を探そうと思っていました。もう少しアーリーというか、まだ何ものにもなっていないこれからの会社が良いというのが自分の中の条件でした。
何となくですが、大学発とか、研究ドリブン・技術ドリブンの会社に関わってみたいと思っていて、そういう会社に興味があるとまわりの人に言っていたんです。「おもしろそうな会社があるよ」と紹介してもらったのがQunaSysでした。
量子コンピュータについては言葉を聞いたことがある程度だったのですが、自分なりに調べていくとおもしろくて(笑)。特に材料開発の分野などは、これまでに考えられなかったような素材が生まれる可能性を秘めているということで、環境負荷を軽減できそうだったり、世の中に大きなインパクトが出せるポテンシャルがあると感じました。やっていることに夢があり、技術の力で世界を変えてしまうかもしれないという可能性にすごく魅力を感じたので入社したという経緯になります。
▶︎ 松岡 :事業としては、「リサーチ事業部」「クオンタムソリューション事業部」「ケミカルリサーチソリューション事業部」という3つの事業部があります。
大まかにそれぞれの事業について説明すると、リサーチ事業部は、量子コンピュータでできることは何かを考え、カタチにしていく事業部です。クオンタムソリューション事業部は、リサーチ事業部がアウトプットしたものをソフトウェアに載せて、量子コンピュータで誰もが使えるようにすることがミッションです。
そして、ケミカルリサーチソリューション事業部は、アプリケーションの領域でユーザーの普段の業務と量子コンピュータを繋ぐ役割を担っています。化学業界の顧客に向けて行なうのですが、たとえば「量子コンピュータで効率化できます」といきなり言われても、すぐに実務に落とし込むことは難しいと思うんです。そのため、量子のことを何も知らない人でも量子コンピュータ上で動くアプリケーションを活用できるようにすることが、この事業部の役割になります。
量子コンピュータをPCだとすると、WindowsなどのOSやExcelなどのアプリケーションが必要です。私たちは量子コンピュータ用のOSやアプリケーションをつくり、それを実務で活用するためのサポートも提供しているというイメージになります。
ほかにも具体的なサービスの例を挙げると、『QURI(キューリ)SDK』というツールがあります。量子コンピュータ上で動かすアプリケーションを開発したい場合に、「量子コンピュータ上でこういうことをしたらどうなるか」とか「あの量子コンピュータの上でこのソフトウェアを動かしたらどうなるか」ということを検証することが可能です。どういうアルゴリズムやアーキテクチャやハードウェアの組み合わせが最適か性能評価することで、アプリケーションの設計や実装を効率化するイメージです。
▶︎ 菅谷 :僕はCFOとして経営管理部門を見ています。昨年までは資金調達を行なっていたので、そこに最も時間を使っていましたが、何とかひと段落がつきました(2024年11月に総額17億円の資金調達を実施)。現在は、採用や人事評価制度の設計、社員のエンゲージメントをどう高めていくかといった人に関わる部分の組織づくりにほとんどの時間を使っています。
▶︎ 松岡 :私はCOOとしていろいろやっているので説明が難しいのですが、端的に言うならビジネス統括という役割になります。とはいえ、明確に「これ!」と言い切ることが難しいというのが本音です。
なぜかというと、試行錯誤が多く、「何をやるべきか」が決まっていない活動がたくさんあるからです。量子を使ってこれまでは成しえなかったことをするというのが大きな方向性なのですが、そのために何をやるかは本当にさまざまです。
たとえば、政府への働きかけも必要ですし、ケミカルリサーチソリューション事業でどんなサービスをつくるかというのも重要です。時期によって注力することも変わっていて、以前は『QPARC(キューパーク)』という企業コミュニティの立ち上げをがんばっていました。

これは量子コンピュータについて学びたい企業を対象にしたもので、量子コンピュータのハードウェアとアルゴリズムを学ぶことができ、産業への応用やそれによる課題の解決を目指すコミュニティです。ある程度立ち上がってきたので、いまは他の人に任せて、代わりに『QURI SDK』をたくさんのユーザーに使ってもらうにはどうすればいいかを考えたりしています。
▶︎ 菅谷 :魅力に感じるのは、会社の成長を左右する部分にいろんな角度から関われるところでしょうか。
前提として、量子の世界と既存のビジネスとの決定的な違いは、マーケットがまだ存在していないということです。量子には大きな可能性があると言われていますが、産業として成立する100%の保証はありません。そのため、自分たちで新しい産業をつくっているという感覚です。本当に大変ですけど、これが非常に刺激的です。
たとえばSaaSであれば、ユーザーの課題やニーズをある程度のレベルで想定できると思います。CFO的な観点��で言えば、たとえば資金調達をして、営業リソースを投入する。これをできるだけ短い期間で行なって、一気にシェアを取りに行くことで会社を成長させることができます。
量子の場合は、「こういうことができるようになるかもしれない。できるようになるはずだ」というイメージはあるものの、まだまだ検証を重ねていくフェーズです。そのため、どんなに営業リソースを投下しても、売上が生まれるわけではありません。だから、「これまでとは戦い方が違う」というのが最初の大きな学びでした。
短期的な戦い方が通用しないので、資金繰りをしっかりとマネージしながら、長期的な事業戦略を描く必要があります。長期戦を戦い続けるために、どういう組織にするかも重要です。これはどの会社も同じだと思いますが、会社のカルチャーや大切にしたい価値観、各自のキャラクターを理解した上で、最もパフォーマンスが高い状態をつくるには何が必要なのかを考える。事業計画をどう作るかみたいな話と、人事的な部分をどうしていくかという話を、明確なマーケットがない状態で組み立てていくんです。個人的には、これがとてもおもしろいですね。大変ですけど(笑)。
▶︎ 松岡 :私も「これまでになかったものを自分たちの手でつくりあげていく」というのがおもしろいですし、燃える部分ですね。ただ、事業をつくっていく上で難しいと感じているのは、不確実性の多さです。市場と技術の両方に不確実性があります。
「理想的な量子コンピュータができれば、理論上はこういうことができるようになります」ということは言えますが、理想的な量子コンピュータがいつ完成するかは誰にもわかりません。理想的な量子コンピュータの赤ちゃんはつくれるのですが、赤ちゃんが思い描いた通りの大人になる保証はありません。

理想を語り、魅力を感じていただいて、可能性に賭けてもらうことが必要ですが、不確実性が多いのでユーザー側も意思決定が難しいんです。そのため、コンソーシアムをつくったり、『SDQs』という取り組みを通じて世の中に発信したりしています(SDQs:量子コンピュータによる企業の長期的成長に重要なESGへの貢献ストーリーを考えるQunaSysが始めた取り組み)。
一筋縄ではいかないですが、そのぶん特別なことに挑戦しているという実感がありますし、物事がひとつ前に進むと大きな達成感がありますね。
▶︎ 松岡 :そうですね。不確実性を減らしていこうと思うと、「これをやったほうがいいんじゃないか」とか「これは必要ないんじゃないか」など、いろんな意見が出てきます。こういった迷いが出てくると組織が混乱するので、出てきた意見を検証する必要があるのですが、検証が難しいんです。
▶︎ 菅谷 :その通りで、コンセプトの検証にとても時間がかかるんですよ。短期間で仮説検証できれば良いのですが、こればかりは技術の発展に合わせるしかありません。ただ、いまのペースだとひとつの仮説を検証するのに2〜3年かかります。現場の社員からすれば、結果が出るまでに2〜3年も待つことになるわけなので、ちょっとしんどいですよね。
▶︎ 松岡 :検証結果を待っている間にだんだん不安になってくるので、もっと楽に価値が出せるんじゃないかとか、そういう思考になってきます。人間なので仕方ないとわかっていながらも、その上でベクトルを統一する難しさはやっぱり感じています。
ただ、不安をきれいに解消してくれる魔法はなくて、会話や議論を通じて「この方向でいいんだ!」という共通認��識を積み上げていくしかないと思っています。社内のミーティングで何度も言葉にしたり、いまやっていることが何につながっていくのかを改めて説明したり。こういった取り組みは地味ですが本当に大事なプロセスだと思っていて、けっこう丁寧にやっていますね。菅谷も、「こういう計画で、こういう理由でこういうことをやっていきます」というのをドキュメントに残して、口頭でも繰り返し伝えています。私も前職時代よりも、共通認識をみんなで持てるようにかなり意識しています。
▶︎ 菅谷 :先日も伊東で全社合宿をしたんですよ。普段はフルリモートなので顔を合わせないのですが、せっかくみんなで集まったので、4日間の合宿で本当にたくさんの会話をしました。すごく有意義な時間だったと思っていて、こういうイベントをうまく活用しながら、「自分たちは前に進んでいるんだ」ということを何度も言葉にして伝えていくことが大切だと思っています。
中長期の方向性という観点では、僕はひとつの時間軸として2030年までが勝負だと考えています。少し専門的な話になりますが、日本政府が「ムーンショット目標6」において2030年までに一定規模の量子コンピュータの開発と実証を行なうと言っていますし、内閣府の「量子未来社会ビジョン」では2030年までに量子技術による国内付加価値の拡大を掲げています。米国のITベンダーのなかには、2030年前後に量子コンピュータを開発する計画を発表しているところもあります。世界的に、2030年というゴールに向かって競争が行なわれているんです。
この競争にどの企業が勝つかが大きなポイントで、QunaSysとしてはOSやアプリケーションの分野においてしっかりと成果につなげていきたいと考えています。
僕はこの分野では自分たちにアドバンテージがあると思っているんです。というのも、海外に比べると、日本はユーザーとなる企業が非常に協力的で、恵まれた事業環境にあるからです。ユーザーが何を求めているかという理解はそれなりに進んでいるので、結果として「どういうコンピュータをつくったらいいのか」についても独自の見解を持てるはずだと考えています。その見解に基づいて、真ん中のOSをつくることができれば、量子コンピュータを利用するためのプラットフォームを押さえられるんじゃないかと思っています。ハードウェアは米国のベンダーが強いので、QunaSysが本格的に参戦するわけではないのですが、どうせ競争をするのであれば野心的にというか、グローバルに戦っていきたいですよね。

▶︎ 松岡 :私は、先ほどお伝えしたようなさまざまな取り組みを愚直に続けていくことが大きな方向性だと考えています。量子コンピュータの価値を広げる研究をして、それをアプリケーションに載せて、ユーザーの皆さんに使ってもらう。量子コンピュータのことを知らない人でもちゃんと使えるところまで持っていく。そのためにできることを、本当に愚直にやり続けることですね。
そうすることで、2030年には量子コンピュータがひとつの産業として立ち上がっていると思いますし、QunaSysが主要なプレイヤーとしてマーケットを牽引している姿をイメージしています。私たちがちゃんとポジションが取れている未来を信じて、いまできることを手を抜かずに積み重ねていくことが大切だと思っています。
▶︎ 松岡 :これはシンプルに組織強化です。研究開発については優秀なメンバーが揃っているので、QunaSysの量子技術を活用することでどんな課題が解決できそうか、どんな価値を生み出せそうか。そういうことを考え、ユーザ�ーに提案したり、ユーザーとディスカッションするポジションを強化したいと考えています。ぴったりな言葉が思い浮かばないのですが、一般的なポジション名だと「事業開発」と「セールス」を掛け合わせたようなイメージです。
新しいソリューションを創出し、提案する一方で、ユーザーとの対話を通じた課題発見から開発に繋げる動きもあります。最初はトライアンドエラーになると思いますが、数を重ねることが重要だと考えています。良い反応が返ってきたら「そこに価値がある」とわかりますし、そうじゃない場合は違う仮説を立てればいいので。
▶︎ 菅谷 :化学業界に限定するつもりはなくて、自動車メーカーでもいいですし、銀行でもいいと思っています。大手企業であれば、おそらく量子について検討するチームがあるはずなんですよ。量子の技術を自分たちのビジネスにどう活かすかを考えている、小規模な研究所みたいなところが。
ただ、提案先の部署としては、そういった研究所じゃないところにアプローチしていきたいと考えています。その企業の売上とか儲けを生み出している、事業をやっている部署をイメージしているんです。そういう部署が持っている「こういうことができないか」をキャッチして、形にすることができれば、その企業にとって非常に強力な武器になるからです。
顧客に提案しているメンバーは3〜4名しかいないので、リソースが足りておらず、このようなアプローチができていません。でも、今後テクノロジーが発展していくと、いよいよ「この量子の技術を何に使うか」という話になってきます。そのため、いまのうちにどういうことに活かせそうかというのを顧客にちゃんと伝えられる人を採用したいんです。
量子に詳しい僕たちが、量子に詳しい研究所の人たちとやり取りしても、技術的な話がどうしてもメインになってしまいます。そういった角度だけではなく、「中長期的な経営において何を成したいか?あるべき姿は?」その道筋の中で、量子をどう活かすかの議論を行うことが、量子を経営にリンクさせることにつながると思っています。産業として立ち上げるためにも、量子よりも事業寄りの部署にアプローチして、量子の技術がビジネスの成長や拡大に寄与することを実証していきたいと考えています。
▶︎ 菅谷 :まず「来月や来年までに」ではなく「2030年�までに」という前提を置きます。そして、「5年後の2030年に向けて何をしましょうか」というテーマで話をします。
たとえばですが、タイヤメーカーの方と話をするとしましょう。お客様は製品をつくる際に、コンピュータを使ってさまざまなシミュレーションをします。Aという素材を使ってタイヤをつくり、その耐久年数をシミュレーションするとして、舗装された道路と未舗装の道とで結果は変わります。舗装された道路でも天候によって結果が変わりますし、自動車の重量によっても差がでます。Aの素材じゃなくてBを使った場合はどうなるか?Cだったらどうか?というのを考え出すと、膨大な時間がかかります。
でも、量子コンピュータはそのような計算が得意なので、いろんな条件でさまざまなシミュレーションが可能です。いろんな大きさやいろんな物理現象を、同時に考えることができるんです。

これは現在の技術の延長線上にはない新しい世界です。いま目の前にあるさまざまな当たり前を無くしたときに、どんなビジネスができそうかをお客様に投げかける。「5年後にはこうなってるかもしれません」というイメージをお客様に��持ってもらう。そうすることで、お客様にとっての新しいビジネスのやり方を一緒につくりあげていく。こういうことを想定しています。
▶︎ 松岡 :ダイレクトメールを送ったり、アポ無しで飛び込みをしたりもしますが、結局は誰かの人づてで会いにいくのが一番確実です。代表の楊がいろんな講演会に行っていますし、『QPARC』のようなコミュニティもあります。また、QunaSysのリサーチャーはさまざまな研究所とつながりを持っていますので、研究所の方から「興味を持っている企業がありましたよ」と紹介をいただくこともあります。こういったつながりを活用してアプローチするのが効果的だと考えています。
▶︎ 菅谷 :10社と接点を持てば、そのうち2社程度とは具体的な話が進む感覚を持っています。事業上の競合がいないので、競合他社とバッティングすることはありませんが、技術的にはまだ確立されていないのですぐに仕事に結びつくわけではありません。その代わり、うまく話が噛み合えば、そこからは結構スムーズに進むと思います。その割合が20%くらいじゃないかという想定です。
企業の経営層との商談になることは稀で、先方社内で役員を口説いてもらうことが多いです。そのための資料を一緒につくっていく感じなので、エンタープライズ向けの営業をしていた方には馴染みのある動き方だと思います。
▶︎ 菅谷 :何か特定の「これが活かせる」というものはないと思っています。何かしらのスペシャリティがあれば、それを使って活躍できるのではないでしょうか。
たとえば、いまのコンピュータ産業で言えば、ハードウェアとインフラがあり、ソフトウェア、サービスがあって、ユーザーがいるという構造です。どこに強みを持っているかで、活躍できるポイントが違うと思います。
業務目線が強いコンサル的な経験をお持ちの方であれば、技術よりも業務に寄ったところで強みを発揮できると思います。ハードウェアやインフラに近い人であれば、「コンパクトな設計にするためには」といった観点で強みを活かせるはずです。何が言いたいかというと、量子という専門的な分野ではあるものの決して間口が狭いわけではないということです。
逆に量子についての知識がない方のほうが、おもしろい提案ができるかもしれません。量子の専門家はQunaSysにたくさんいるので(笑)。それよりも、お客様にとって量子の技術がどう見えるのかであったり、お客様の気持ちになって相手のビジネスをさらに伸ばすにはどうすればいいかを考えられる。そういう方のほうが活躍するイメージがありますね。
デジタルで世の中は大きく変わっていますし、自動車業界も、小売業界も、どんどん変わっているじゃないですか。AIはすごく進化していますし、仕事の進め方もいままさに変わっている最中だと思います。量子という道具だけに固執することなく、たとえば既存の仕組みと組み合わせたり、AIと掛け合わせたりすることで、いろんな可能性があると思います。お客様のビジネスにインパクトが出せるところに、どうやって量子の技術を活用していくか。それをお客様と一緒に描いていければ最高ですよね。
▶︎ 菅谷 :ディープテックという言葉がありますよね。核融合技術などのクリーンテックやAI搭載ロボットなどのロボティクスなど、ディープテックにもいろいろあります。量子コンピュータもそのう��ちの一つです。これから技術革新が進み、大きく発展する可能性があるディープテックですが、量子コンピュータはこの先の発展がほぼ約束されているというのが個人的な考えです。
まず国策であること。そして、グローバルの超大手企業各社が注力していること。これらの理由から、ほぼ間違いなくこれからの発展が約束されていると思います。いま世界中で競争が行なわれていて、5年後の2030年までに誰が主導権を握るかが決まります。社会実装されると、これまでは成しえなかったようなことができるようになりますから、世の中に与えるインパクトは非常に大きいです。
また、経済的なインパクトもとても大きいと思います。従来のコンピュータ産業はここ100年ほどで進化・発展してきました。量子コンピュータが産業として立ち上がると、従来のコンピュータ産業の隣に同規模のものがもうひとつできあがるイメージです。
いまのタイミングでその先頭グループに入っておくか、様子を見てちょっと落ち着いてから参加するかでは、見える景色や得られる経験に大きな差があると思います。約束されている大きな変化に早めに飛び込むことは、キャリアとしてとても大きなメリットがあるというのが僕の意見です。
ビジネスにおける国際的な競争の中で、ここ最近、日本��には明るいニュースが少ないと思います。ただ、量子の分野においては、日本は世界でまだまだ戦えるし、勝つことができると思っています。そこにチャレンジする機会があるというのは、そうそうやってこないチャンスだと思いますね。
▶︎ 松岡 :私も似た考えです。いまって本当にいろんなことをやらせてもらえる、恵まれたフェーズだと思うんです。なので、言われたことをやるのではなく、「自分でビジネスをやりたい」という人にとってはめちゃくちゃおもしろいタイミングだと思います。

私はいま、量子コンピュータが産業としてちゃんと立ち上がるようにいろんな取り組みをしていますが、何かの施策をしたいと思ったときに、なんでも実行できるんです。量子に興味がある人を集めてコミュニティをつくることはもちろん、国に何かのプランを持ち込むこともできます。逆に、国から意見を求められることもたくさんあります。
これはプレイヤーが少ないことも影響していると思いますが、経済産業省などが量子関連の会議をするときは必ず声をかけてもらえます。私たちの意見をすごく尊重してもらっているという感覚がありますし、それだけこの分野に賭け��ているんだと思うんです。なので、量子コンピュータを取り巻く環境は、いまが最もエキサイティングで、最もおもしろいタイミングなのだと思います。
この分野に関しては、みなさんとても協力的です。それは、新しい技術を学ぶとか、ちょっと使ってみるとか、そういうことが好きな人が多いからだと思っています。海外の場合は、「どれだけのリターンがあるの?ビジネスとして成長するの?」というのが先にくるイメージなのですが、日本の場合は「すごそうな量子というものに触れてみたい」といったピュアな好奇心が勝つ印象です。
運営しているコミュニティにも、「会社としてはまだ検討していないのですが、個人的にとても興味があって」という連絡が結構きています。私としては、日本でこのチャレンジができることは本当に恵まれていると感じていますし、だからこそ結果につなげたいと思っています。


株式会社ディプコア 代表取締役CEO
お二人へのインタビューを通じて、新たな産業の胎動を感じると共に、日本の未来にひとつの希望を持つことができました。 量子の分野では2030年までを目安として国際的な競争が行なわれているとのことで、技術の進化によって5年後には世の中が大きく変わっているかもしれません。 比較対象になるかわかりませんが、現在これだけ市民権を得ているAI技術も、5年前は一部の研究者やエンジニアの専門領域だったはずです。それがいまや日常業務はもちろん、日常生活にも広く浸透しています。 5年後、「量子」がいまよりもずっとポピュラーになったとき、果たしてQunaSysはト��ッププレイヤーになっているのでしょうか。量子技術の進化や日本の国際競争力の向上に希望を持つと同時に、同社の発展にも大きな声で声援を送りたいと思いました。

2025.05.02 公開

2025.08.01 公開
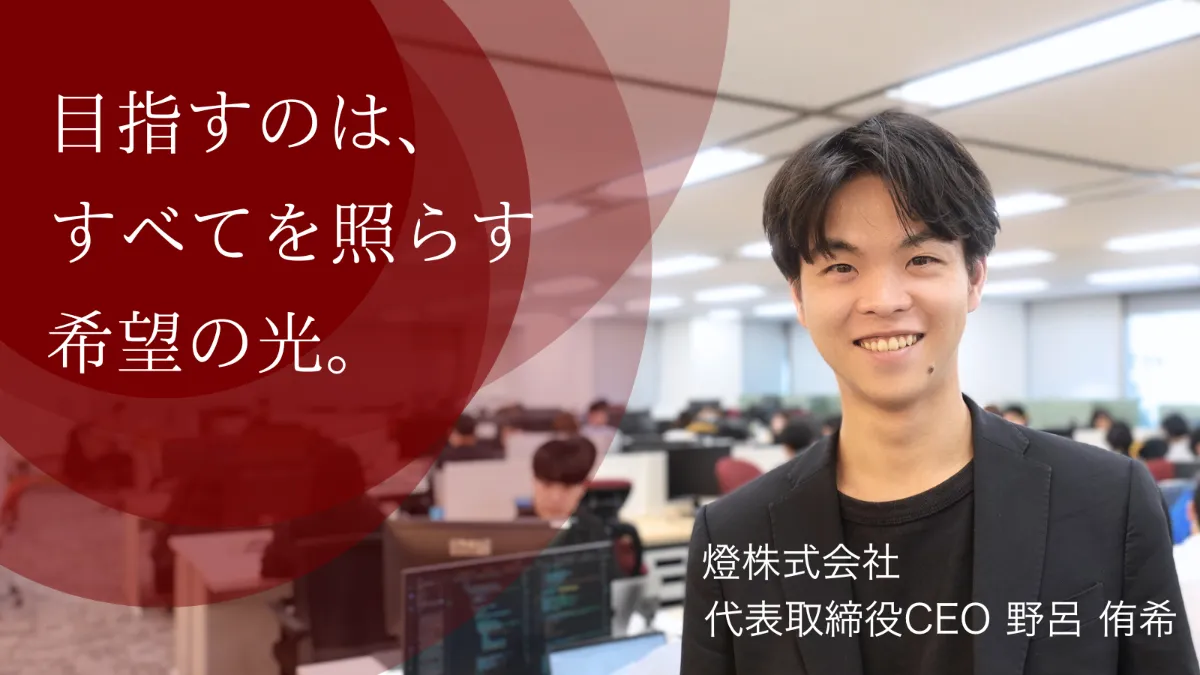
2024.12.18 公開

2024.11.22 公開

