
孫正義の鞄持ち時代の挫折が英語学習の原点に。コーチングモデルで革命を起こしたトライズ三木が語る、学びの力。
2025.11.10 公開

2025.11.10 公開
トライズ株式会社 代表取締役社長 三木 雄信
設立:2006年
事業内容:語学教育事業、デジタル教育事業

株式会社トークナビ 代表取締役
��三木社長は、人の可能性を信じ、成長を支援する仕組みを築く情熱的な経営者です。自ら学び、挑戦し続ける姿は、社員や周囲に大きな勇気と希望を与えています。そんな三木社長率いるトライズは、語学を手段として人材を育成し、日本社会のグローバル化と経済発展を力強く支えています。教育を通じて人の未来を切り拓き、社会に革新と明るい光をもたらす存在として、今後ますます注目していきます!
英語学習市場は、日本において長年にわたって大きな課題を抱えてきた。PEST分析の観点から見ると、政治的には企業のグローバル化推進政策、経済的には人材競争力の国際的地位低下、社会的には日本人の英語習得への根深い苦手意識、技術的にはeラーニングからAI活用への急速な変化という、複雑な環境変化が起きている。特に、世界でも最低レベルと言われる日本のビジネスパーソンの自己学習・自己啓発の低さ(※)は、この市場の深刻な課題を如実に表している。
そうした中、1995年のYahoo! JAPAN立ち上げや三菱地所での広報業務を経て、2006年にトライズ株式会社を創業した三木雄信氏は、独��自の「コーチングモデル」で英語学習業界に革命を起こしている。同社は「学ぶことを通じて人と組織の可能性を拓く」を経営理念に掲げ、従来のeラーニングの限界を突破する個別最適化された学習サービスを展開している。今回はそんなトライズ株式会社の三木雄信さんに、ThinkD単独でじっくりお話を伺った。
(※)世界18ヶ国・地域の主要都市で実施されたパーソル総合研究所「グローバル就業実態・成長意識調査(2022年)」では、「社外の学習・自己啓発の活動状況」という設問において、日本は「とくに何も行なっていない」が52.6%を占める。
福岡県の久留米大学附設高等学校に通っていて、孫泰蔵さんや堀江貴文さんが同級生でした。学校のモットーは「和して同ぜず」で、論語に出てくる言葉なのですが、いまでも私に影響を与えていると思っています。
「君子和して同ぜず、小人同じて和せず」という一節で、「立派な人間は、人と協調して親しく交わりながら�も、道理や自分の信念を曲げない。器の小さな人間は、表面的に同調しても、心からの調和はない」という意味です。
こんなモットーを掲げている学校なので、各自が自分の考えをしっかり持っている感じでした。当時は男子校ということもあって、荒々しい気風というか、個性的な人が多かったと思います。サービス業を中心に親が商売をやっている生徒も多くて、「自分の道は自分で切り拓く」というタイプが多かったと思いますね。

私自身も実家が建設業を営んでいたので、幼い頃から漠然と「将来は社長になりたい」と思っていました。そのための準備として、経営について学ぶために東京大学の文科二類に進学したんです。
就職先として三菱地所を選んだのは、実家の建設業の上流工程だったからです。幼い頃から身近にあった建設業の最上位を経験してみたいと考え、就職しました。
私は1995年に社会に出て働き始めたのですが、実はもうひとつ仕事を持っていました。それは、孫泰蔵さんが在学中に立ち上げたインディゴ株式会社の取締役という仕事です。大学4年生のときに取締役になり、そのまま三菱地所に就職したので、いまで言う兼業のような状態で社会人生活をスタートしました。
そして、1年目の冬に、Yahoo! JAPANの立ち上げという大きなプロジェクトがありました。Yahoo! JAPANは1996年4月にオープンするのですが、私が取締役をしていたインディゴ株式会社がその立ち上げをサポートしていました。
オープンに向けて「日本中のウェブサイトを集める」というのがプロジェクトの趣旨でした。当時はポータルサイトがないので、何かのウェブサイトを見ようと思うと、サイトに記載されている「おすすめのリンクはこちら」のようなものを辿っていくか、URLを直接打ち込むしかありませんでした。そんな時代に、日本中のウェブサイトをすべて集めるという目標を掲げ、2週間で約2万サイトを集めて納品したんです。慌しかったですが良い思い出です。
当時のYahoo! JAPANは検索サイトではなく、名簿や住所録のようなディレクトリでしたので、集めた2万サイトをどのように整理するかを検討する必要がありました。「最初は芸術、次にビジネス、そして文化でカテゴリー分けして欲しい」というのが孫社長からの指示でした。
なぜこの順番なのかわかりますか?米国版がABC順だったからです。米国�版は、Art、Business、Cultureの順で並んでいたので、日本版も同じにしようということでした。私は「米国だとABC順は意味がありますが、日本では通じません。五十音順に並べ替えますか?」と提案したら、「まずは新しいサービスをオープンすることが大事だから、ABC順で最速でやってくれ!」と言われて、「わかりました!すぐやります!」みたいな。これも良い思い出ですね(笑)。

いまでこそ兼業や副業が一般的になってきましたが、当時はまだ終身雇用の世の中で、一社で勤めあげるのが当たり前でしたから、相当珍しかったと思います。
ただ、Yahoo! JAPANが立ち上がったあと、インディゴ株式会社はソフトウェアの事業に力を入れるようになりました。私はあまり興味を持てなかったので、会社から抜け、そこからは三菱地所の仕事により一層打ち込んでいきました。
私が入社する前、バブル期の三菱地所は「世界三大都市の大家になる」という大きな戦略を掲げていました。日本の東京で丸の内を買い、米国のニューヨークでロックフェラーセンターを買い、英国のロンドンでパターノスター・スクウェアを買いました。その後、バブルが崩壊し、三菱地所の世界戦略も見直しが必要になりました。私が入社した1995年はそういう時期で、社内の雰囲気はどこか暗い感じがしていました。
私の配属先は広報部だったのですが、毎朝7時半に出社して、専門紙を含めた32の新聞に目を通し、三菱地所関連の記事があったら切り取ってファイリングするというのが日課でした。
ある日、いつものようにファイリングをしていたら会社に電話がかかってきました。私が電話を取ると「ロックフェラーセンターの運営会社がチャプターイレブン(※)を申請した」というものでした。
(※)チャプターイレブン:米国連邦倒産法第11章のこと。日本の民事再生法に相当する。申請をしたのはロックフェラーセンターを保有・運営していた企業体(Rockefeller Center Properties など)。この破産手続きに伴い、三菱地所はロックフェラーセンターの所有権を担保権者に移譲し、ロックフェラーセンターの保有を失った。
緊急の連絡で、広報部にも知らせることになっていたらしく、それを私が受け��たんです。いま思えば、すごい電話を取ってしまったなという感じなのですが、当時は1年目だったので重大さをしっかりと理解できていませんでした。ただ、こういうこともあり、会社に少し元気がないな、というのが私の印象でした。
東京の丸の内も同様で、いまでは信じられないかもしれませんが、仲通りはシャッター街になっていました。当時たくさんあった地方銀行の支店が、維持が難しくなり次々にシャッターを降ろしていきました。その様子は、新聞で「丸の内の黄昏」という特集が組まれたほどです。

そんなご時世ですから、広報部としてはあまりやることがありませんでした。企業広告を出すにしてもお金がかかりますし、そのときは明確な広報戦略もなかったと記憶しています。ただ、何もしないわけにはいかないので、親しい先輩と一緒になって、いろんな研修やセミナーに参加していました。
ある日、先輩とカフェで休憩していたときに、これからどうしていくかを相談しました。明確な戦略はまだ出ていない。だからといって何もしないのは違うと思う。じゃあ、自分たちなりに会社にとって必要なことを考えて、それに基づいて広報しようという話になりました。
そうです。そして、バブル崩壊でいろいろなものを失いましたが、丸の内は残っていることに気づきました。そこで立てた広報戦略が「丸の内に集中する」というものです。
30年前の丸の内は、三菱グループの企業ばかりで、「三菱村」じゃないですけど、どこか閉鎖的な雰囲気がありました。丸の内を盛り上げるには、この雰囲気を変えたいと思い、三菱グループの人たちはもちろん、それ以外の人たちにも丸の内を楽しんでもらえるようにしたいと考えました。
そして、「24時間」「オープン」「インタラクティブ」というキーワードを決め、それらのキーワードを象徴するようなものをつくったり、発信していくことにしたんです。
ひとつの例が、カフェです。ちょうど日本でオープンカフェが流行り始めたころだったので、丸の内にもカフェをつくったところすごくヒットしました。また、街路樹も見直しました。仲通りの街路樹は枝葉が多く、どっしりとして安定感があるものの、光を遮ってしまい通りの雰囲気を暗くしていました。だから、ケヤキを中心とした街路樹に植え替え、光が入り、風が抜けるオープンで明るい通りにしました。
ほかにも女性向けライフスタイル誌とタイアップして�、丸の内を特集したペイドブック(※)を出したり、丸の内を楽しむためのポータルサイトを立ち上げたり、いろいろやりました。
(※)ペイドブック:企業や団体などの広告主が制作費や印刷費を負担して出版される冊子・書籍・雑誌のこと。一般的には「ムック」と呼ばれることが多い。
丸の内を活性化するためのこれらの取り組みは、いまでは都市開発の事例として研究対象になっています。米国のビジネススクールでもケーススタディとして取り上げられているはずです。
三菱地所の広報部として何か別の戦略があったのかもしれませんが、少なくとも私の記憶では具体的な方向性は示されなかったと思います。もちろん、バブル崩壊後で会社として大変な時期でしたから、広報戦略を立てることよりも優先度の高い事案がたくさんあったのではないでしょうか。
ただ、明確に覚えているのは、丸の内を活性化させる取り組みを当時の社長にプレゼンしに行き、それが社内で話題になったことです。というのも、社長に対するプレゼンで、パワーポイントとプロジェクターを使ったのは私が初めてだったようで、内容以上にその手法が印象的だったみたいです(笑)。

三菱地所ではいろいろなことを経験させてもらいましたが、私のようなある種トリッキーなやり方をする社員は少なかったです。大企業ということもあり、規律を守ることが非常に重視されますし、何よりも優秀な方がとても多くて「このままでは社長になれない」と思い、退職することしました。
はい。ソフトバンクに入社したのが1998年です。最初は孫社長の鞄持ちからスタートし、2000年からは社長室長を任せていただきました。そして、入社したばかりの頃の経験が、その後の起業に大きく関係します。
入社してすぐ、孫社長のシリコンバレーへの出張に同行するように言われました。ヤフーの創業者や初代CEOとの商談があり、そこに同席するというものでした。ただ、そのときの私は英語が話せなかったので、議論にまったく参加できなかったのです。置物のようにじっと座っていることしかできず、意見を求められても、何を聞かれているのかさえわかりませんでした。
孫社長にご迷惑をかけてしまった申し訳ない気持ち、それに恥ずかしい気持ちや悔しい気持ち、これらがごちゃ混ぜになり強烈な後悔が残りました。この経験を払拭するために、英語学習を徹底的にやり直す決心をしました。
そこからの1年間で英語学習に費やしたのは、1,000時間です。英語学習の方法を調べまくり、自分に合うものをどんどん取り込んでいきました。結果、1年で交渉で負けない英語力を身につけることができましたし、その過程で体系化した英語学習のポイントをベースに、世の中のビジネスパーソンの支援がしたいと2006年に創業したのが、トライオン株式会社(2023年にトライズ株式会社に商号変更)です。
2006年の創業時は個人向けにeラーニング形式で語学教育サービスを提供していました。これは、「インターネットは素晴らしい」という個人的な想いがあったからです。
自分で英語学習をしていたときもインターネットを活用していましたし、何よりも利便性が高い。インターネットを使えば、安く、いつでも、どこでも学ぶことができる。そのため、eラーニング形式でのサービス提供は、当時の私にとっては当たり前の選択でした。ただ、そんなeラーニングをやめてコーチングにシフトしたのには、大きく2つの理由があります。
1つは、事業としてあまり儲からなかったからです。コロナ禍こそ、自宅でできる学習方法として個人向けのeラーニングが伸びましたが、2000年代や2010年代はeラーニングによる英語学習市場は伸び悩んでいたと思います。

当時、私たちはYahoo! JAPANとも提携していました。学習のポータルがあり、教材が選べて個別に決済できる仕組みがあったんです。なかなか良い仕組みだと思っていましたが、そのポータルはなくなってしまいました。つまり、「学習ポータルを事業として伸ばすことは難しい」と判断したということです。あのヤフーですら難しいものを、私たちがやれるはずもなく、eラーニングからの方向転換を考え始めました。
同時に考えていたのが、「なぜ日本では個人向けのeラーニングが普及しないのか?」ということです。米国でも中国でも、だ��いたいeラーニングは急成長分野でした。しかし日本ではなかなか事業として大きくならない。これはなぜなのか。考えに考えて、自分なりにたどり着いた答えが、「日本人には合わないから」です。
これはあくまで個人的な考えですが、誤解を恐れずに言うと、明確な目的を持って生きている日本人ってそこまで多くはないのではないかと思っています。「人生をかけてこういうことがしたい」とか、強烈な目的意識を持っている人が少ない。だから、目的を実現するために学習する人が少ない。
さらに突き詰めていくと、日本人ってあまり自我を出さない傾向にあると思います。社会や集団の中で、強烈に「個」をアピールすることも少ないです。英語の学習をしているとすごくよくわかるのですが、英会話のレッスンなどで「何でも好きなことを話してみてください」と言っても、「何を話せばいいかわからない」と言う人が多いです。英語でどう話すかの前に、話したいことがない。
だからダメだと言うわけではなく、それが日本人という民族のひとつの特徴であり、そういう国民性なのだと思います。みんなが自分の考えを主張し始めたら収拾がつかなくなりますし、相手の状況や場の雰囲気を読むことでつくられる調和もあります�から。
会社での会話においても日本らしさが表れますよね。上司が部下に「新しくウェブサイトをつくりたいから制作会社に見積りを取ってくれ」と依頼したとします。後日、部下が上司のところに来るわけですが、「A社はクオリティが良いけど値段が高いです。B社は値段は安いですが、実績がまだ少ないです。C社は価格がちょうど良いですが、クオリティがいまいちです」とか言うわけです。
こういうシーンって、けっこうイメージできると思うのですが、部下は自分で結論を出さず、上司と相談しながら決めたい。だから、上司が「利益が出ているからお金のことは気にするな。高くても良いものをつくろう」と言えば、「そうですよね。A社が良いと思います」となります。逆に、「失敗はできないから、今回はバランスを重視しよう」と言えば、「わかりました。私もC社だと思います」となります。
このように、相手の考えやそのときの状況を踏まえて、いろんなものを共有しながら、意見をすり合わせて物事を前に進めていく。これが日本の文化であり、スタイルです。時間をかけて認識や価値観を揃えていき、みんなで足並みを合わせて、じっくりと成果を積み上げていく。このやり方を否定するつもりはありませんし、むしろこのやり方で日本経済は成長してきたとも言えると思います。
また、強烈な目的意識がなくても食べることに困らず暮らしていけるのは、ある意味で豊かな社会だからこそ可能なのだと思います。そのため、いまお伝えしたのは、あくまでも個人向けのeラーニング形式の語学学習がそこまで大きくならなかった理由を考えたときの私の見解です。
この見解にたどり着き、語学学習においては、自分の意思を持って取り組むかどうかが成果に大きな影響を与えると認識したので、eラーニングからコーチングにシフトしたというわけです。

ハングリーに努力しなくても、それなりに生きていけるからではないでしょうか。それはある意味で、社会が豊かであることの裏返しだと思います。
学習しなくても、生きていけますよね。大学を出るまでは勉強するかもしれませんが、就職をしたら、会社から求められることをしていれば良いですから。会社も、評価をするのはその人の業績だけで、普段どのような努力をしているのかは評価対象外というところが多いと思います。意欲を持って学ぶことに、スポットライトが当たりに��くい世の中だからというのは、理由のひとつかもしれないですよね。
パーソル総合研究所の「グローバル就業実態・成長意識調査(2022年)」によると、「社外の学習・自己啓発の活動状況」という設問に対して、日本のビジネスパーソンは「とくに何も行なっていない」が52.6%だそうです。これは、先進国だけではなく世界でみても群を抜いて高い数字で、データからも日本人は日頃から学習していないことがわかります。
『TORAIZ』のお客様は、簡単に言えば学ぶ意欲がある方です。「英語を学びたい」「学ばなきゃいけない理由がある」といった方に対して、専属のコンサルタントとネイティブのコーチがサービスを提供しています。
eラーニングには、簡単に学習教材にアクセスできる利便性がありました。しかし、個人の意欲に左右されるため、継続性が担保されていませんでした。また、教材が一般化されていて、個人のレベルや目的に合わせたカスタマイズが難しいという側面があり、人によっては高い学習効率を維持するのが難しいという課題がありました。そして、個人で取り組むため一方通行になりやすく、成果が出てもやり甲��斐を感じにくいという問題がありました。
コーチングに切り替えたことで、これらの課題をクリアできたと思っています。専属のコンサルタントが学習の目的や語学力を丁寧にヒアリングし、使用する教材をカスタマイズしながら個別最適化された学習プランをつくります。そして、ネイティブのコーチとの実践を通じて英語力を磨き、コンサルタントから定期的なフィードバックを受けながら学習プランを進めていきます。
個別最適化されたハイタッチなサービスを提供するので、受講料もそれなりの金額で設定しています。もちろん、「やってみたけど自分には合わない」という方もいらっしゃいますから受講開始から1ヶ月以内に退会された場合は無条件で全額返金しています。一方で、返金期間をすぎたら退会する方はほとんどいません。継続率は96.1%(※1)で、1,000時間学習時のVERSANTスコアは平均47.2点(※2)です。
(※1)2024年1月〜2024年12月に受講開始した方が途中退会しなかった率
(※2)VERSANTスコア:英語を聞いて理解し、英語で答える実践的なスピーキング・リスニング能力などを測定するテストのスコア。グローバル企業や政府機関で採用実績があり、世界標準の英語力指標であるGSEにも準拠。「英語が話せる」のはVERSANTスコア47点以上と言われている。同社の平均点は2019年〜2022年の全受講生3,431人を対象としたもの。
最初に本を書きました。自分が英語を学んだときのやり方をまとめて、『海外経験ゼロでも仕事が忙しくても「英語は1年」でマスターできる』という本を出したんです。三菱地所での広報経験から、できるだけ広告宣伝費を使わずに、パブリシティでがんばりたいという気持ちがあったからです。

その本が、ありがたいことにたくさん売れました。そんなある日、証券会社の部長の方が私の本を持って会社に来てくれました。そして、「英語が話せるようになりたいから、この本の通りに特訓してくれ」と言われました。
そこで、その方に向けてサービスを提供し、「広告もちょっとだけ出してみようかな」と思って広告を出したら、けっこうな反響が来ました。さらに新聞の取材を受けたら爆発的な反響があり、あっという間に売上がどんどん伸びていきました。
最初は、法人向けにサービスを提供しようと考えていました。でも、個人のお客様が自分から来てくださって、メディアにも取り上げてもらったので、流れで個人向けを先にスタートさせたという経緯になります。
法人向けのサービスを強化していこうと思っています。英語コーチングの『TORAIZ』や、英語シャドーイング添削サービスの『シャドーイングバディ』はすでに法人向けに提供していますが、これらに加えて、最近ではAI英語学習アプリ『TORAbit(トラビット)』の法人向けサービス提供を開始しました。

これは、個別最適化をさらに進め、ネイティブコーチとの会話をその人に合ったテーマで設定できたりします。簡単に言えば、個別の教材をAIが生成し、それをスマホを介して利用できるようになります。
業界や業種、職種や役職など、その人のパーソナル情報に沿って実務に直結するトレーニングメニューをつくってくれるので、成果を実感しやすいと思いますし、そのまま仕事に活かせます。また、法人の人事担当者向けに、社員の学習状況を可視化できる仕組みを導入する予定です。そうすることで、社員の日頃のがんばりが評価されるようになるかもしれないですし、そうなればさらに学習意欲が高まり、より大きな成果を出せるようになると思います。
個別最適化された学習メニューをつくるには、基本的にインプットとアウトプットが整合している必要があると思います。「こういうことを学びたいです。なぜならこうだからです。いまのレベルはこうです」というインプットに対して、それっぽいアウトプットを返すことは一般的なAIでも可能だと思いますが、高い精度で一貫させることは非常に難しいはずです。
そこにはヒアリングやカウンセリング、コーチングのノウハウが必要だからです。私たちはこれまで、専属のコンサルタントとネイティブのコーチを揃え、個別にカスタマイズされたサービスを提供し続けてきました。その延長線上にAIを活用したサービスがあるので、簡単には模倣できないと考えています。
ビジネスパーソンが英語を学習したい場合、所属する法人の�歴史や業界の状況なども踏まえてアウトプットを出すこともできます。リアルなシチュエーションでの学習メニューがつくれることもひとつの強みだと思います。
グローバル展開も視野に入れています。海外は、英語学習のマーケットが日本の30倍と言われています。それぞれの国に合わせた対応は必要ですが、基本的にはアプリがあるので多少カスタマイズした上でそのままリリースできるというのは良いですよね。
事業所を構えて、現地に社員を配置するやり方は考えておらず、まずはアプリで展開していくつもりです。というのも、このAIの時代には、「人を雇う」というのは、相当な必然性があってはじめてやることだと考えているからです。そのため、グローバル展開については、人を介してサービスを提供するのではなく、まずはアプリを広げていこうと考えています。
テクノロジーを上手に活用していくことが基本路線です。ただ、テクノロジーでカバーできないことは絶対にあります。それこそ、コンサルタントが「一緒に頑張りましょう」と励ましてくれたり、成果が出たときに喜んでくれたり。そういうのは人間じゃないと提供できない価値ですし、そのニーズは必ずあります。だから、テクノロジーをちゃんと使い、人間は人がやるべきことに集中できるようにする。これが大切なのだと思います。

一般的なところでは、資格試験の受験料負担、セミナーや研修の参加費用負担があります。あと、細かいところで言えば、MBO(※)があります。
(※)MBO:Management by Objectives(目標による管理)の略で、組織の目標と連動した個人目標を設定し、達成度に応じて評価を行なうマネジメント手法のこと。
現場のメンバーは上長との面談を通じて「今年はこれをできるようになりましょう」と自己研鑽の目標を立てます。たとえば資格の取得とかです。そして、メンバーの自己研鑽をサポートできているかが上司の評価になります。業務実績だけを評価する会社もあると思いますが、私たちは個人の研鑽やそのサポートがMBOに組み込まれています。
もともと、私たちの会社には共感性が高い社員が多いです。それはたとえば、誰かが喜んでいると、自分もハッピーな気持ちになるというタイプです。そういうベースを持っているので、コンサルタントとして受講生のサポートをするときにも前向きに取り組めますし、受講生の成長を自分のことのように嬉しく感じるんです。
マネージャーには、受講生にやっていることと同じことを部下にやりましょう、と伝えています。進捗確認をして、フィードバックをして、モチベートして、受講生へのサポートと同じように、部下の成長を支援する。すると、上司と部下の縦の関係性だけじゃなく、部下同士の横の関係性でもお互いに助け合うようになります。それが会社のカルチャーとして醸成されているところはありますね。
あと、ユニークなものだと『オープンポジション人事制度』があります。これは、すべてのポジションで求められる要件を明示した上で、毎年公募するものです。年度が変われば全ポジション洗い替えをするのが特徴で、自分がやりたい仕事を決めて、その仕事ができるポジションを目指すことができます。
コンサルタントであれば教育や研修分野における専門性が必要になりますから、該当する研修の受講や資格取得をMBOで設定します。本人のキャリアプランが実現しやすい環境をつくり、学習や自己研鑽を通じてその機会を手にできるようにした制度です。
この制度をつくった背景は、あるレイヤーまで行ったら満足してしまう人がいるということです。たとえばマネージャーまで昇格したら、「これ以上はいいや」と満足してしまい、途端に努力しなくなる。それだと本人にとっても良くないですし、会社や事業も活性化しません。

加えて、いまは変化が激しい時代です。状況が変わることを前提に、自分自身を変えていかなくてはいけません。大企業であれば、部長まで行けばそれなりのお給料がもらえて、よほどのことがない限り降格しないと思いますが、私たちのようなベンチャー企業は違います。状況の変化に合わせて学び、自分自身を変えていくことが、非常に重要だと思っています。
『オープンポジション人事制度』は、年齢はもちろん、入社年次も関係なく誰でも利用できます。公募なので、部下や同僚が自分のポジションに応募してくる可能性もありますから、役職者からしたら気が抜けないはずです。でも、だからこそ良い緊張感が生まれると思っています。いずれにせよ、各自に「学ぼう」という意欲�がわいていることは間違いないです。
2024年の春から、アメリカ・UCLAアンダーソン経営大学院とシンガポール国立大学(NUS)ビジネススクールが共同で提供するEMBA(※)プログラムに通い始めました。
(※)EMBA:Executive MBAの略。経験豊富なミドル層を対象にしたもの。経営者・経営幹部が多く集まり、豊富な経験を活かしながら互いに学び合うことができる。
社員や受講生の方に「学び続けることが大切」と言っている以上、私自身が行動で示すべきだと考え、参加を決めました。この機会を通じてさまざまな情報をインプットし、自分自身をアップデートしていきたいと思っています。
もともと、創業した当時は組織マネジメントについて、ほとんどわかっていませんでした。組織づくりとか、社員の育成とか、恥ずかしながらあまり考えたことがなかったんです。ただ、事業が大きくなり、社員が100人を超えたくらいのタイミングで、「何もわかっていない。このままじゃまずいぞ」と感じて学び始めました。
まずは自分で調べて、気になった本を読ん��で、どんどんインプットしていきました。あとは、ありがたいことに仕事でつながりをつくれた方がたくさんいらっしゃるので、相談に乗ってもらうことも多いです。
そういう意味では、「さらに自分を高めたい」という立派な動機ではなく、「わかるようにならないと」「できるようにならないと」という必要に迫られた感じが強いですね。
掲げている『学ぶことを通じて人と組織の可能性を拓く』という経営理念は、今後も変わらないと思います。
長期的には、英語学習に固執せず、いろんなことに挑戦していきたいと考えています。法人向けサービスの強化やさらなるAIの活用、グローバル展開など考えていることはいろいろありますが、経営理念に沿う方向性のなかで、いろいろと試していきたいです。
個人的に非常に関心があるのは、個別最適化された学習プログラムを極限まで追求することです。というのも、学力という観点で言えば、しっかりとパーソナライズされた仕組みで学ぶことで、誰でも東京大学に入れるだけの偏差値になるそうです。
これはベンジャミン・ブルームという教育心理学者の「2シグマ問題」というもので、簡単に言えば、一斉授業と個別授業の学習成果を比較した際に、個別指導を受けた生徒の成績は一斉授業を受けた生徒の平均よりも高いというものです。
ただし、ここでの個別指導は1対1の指導スタイルを指すのではなく、理解できるまで段階的に進めていく学習スタイルのことです。そして、この問題が提起された1984年当時では、大規模な教育環境に個別指導を組み込むには課題が残るという内容でした。しかしいまは、テクノロジーの活用によってこの課題をクリアできる可能性があります。
個別最適化した学習を究極まで高めていくと、試算では偏差値70ほどの学力が身につくそうです。東京大学の文科一類や二類が偏差値72くらいですから、理論上は誰でも東京大学に入れるだけの偏差値になるということです。
「みんなが賢くなったらどんな良いことがあるの?」と聞かれても、明確な回答ができないのですが、なんだかいまよりもちょっとは世の中が良くなるんじゃないかと考えています。
みんなが前向きに学ぶ社会になったら、景気が良くなるかもしれませんし、分断とかもなくなるかもしれないと思っています。現在のさまざまな社会問題について考えたときに、根っこには教育の課題があると思ってい�ます。この根本的な課題に対して、何かしらのソリューションを提供できたら最高ですね。
これはEMBAで学んだことのひとつなのですが、たとえば記憶というものの位置付けです。日本の教育は記憶することが非常に重視されると思います。でも、ベンジャミン・ブルームの「タキソノミー(※)」という学習分類法だと、6つの階層に分けられたなかで、記憶は最下層です。
(※)ブルームのタキソノミー:学習目標を分類する枠組み。目標の明確化と思考の段階を低次から高次に進めることを目的に、学習を6つの階層に分類した。階層は下から記憶→理解→応用→分析→評価→創造。
EMBAでの学びで興味深かったのは、テストのときにみんながチートシートをつくることです。これはいわゆるカンニングペーパーのようなもので、理解が浅いところだけをまとめておくものです。何がわかっていて、何がわかっていないのか。それを考えながらシートをつくるので、その行為自体に深い学びがあります。
「正確に覚えること」は求められておらず、必要があれば調べれば良い。むしろ、問題を解くためにはどんな情報が必要なのかを考えられることが��重要というものです。
日本の教育がすべて間違っているというつもりはありませんが、これまでとは違う学習方法を選ぶことで、これまでは想像できなかったような未来が来るかもしれませんよね。
学ぶことや、それによる成長を楽しく感じる人が増えれば、いまよりも良い世の中になると思っています。そのためのお手伝いができるように、がんばっていこうと思います。
.png)

株式会社ディプコア 代表取締役CEO
三木社長は、孫正義さんの下で働いていたときの大きな反省から、自ら英語を学ぶと決めて、やり切った経験をお持ちです。その経験が事業になり、現在の同社の礎になっていると考えると、「たとえ最初は個人の小さな努力だったとしても、それがひとつの会社に発展していくこともある」という、可能性の大きさを感じられたインタビューでした。 私自身、過去にオンラインのビジネス英会話を2年間継続したことがありました。1日25分でしたが、毎日続けることでTOEICのスコアが300点アップしました。中小企業診断士に挑戦した際も、5年かかりましたが無事に資格を取得できました。いずれも、「このままだとビジネスパーソンとして成長できない」という危機感からでした。 三木社長のように、強烈な危機感から事業や会社を生み出した経営者は少なくないのではないでしょうか。日々感じる「できない」や「くやしい」をそのままにせず、まずは行動を起こしてみる。そしてやり切ってみる。そうすることで、何か新しい景色が見えてくるかもしれないと思いました。

2025.08.01 公開
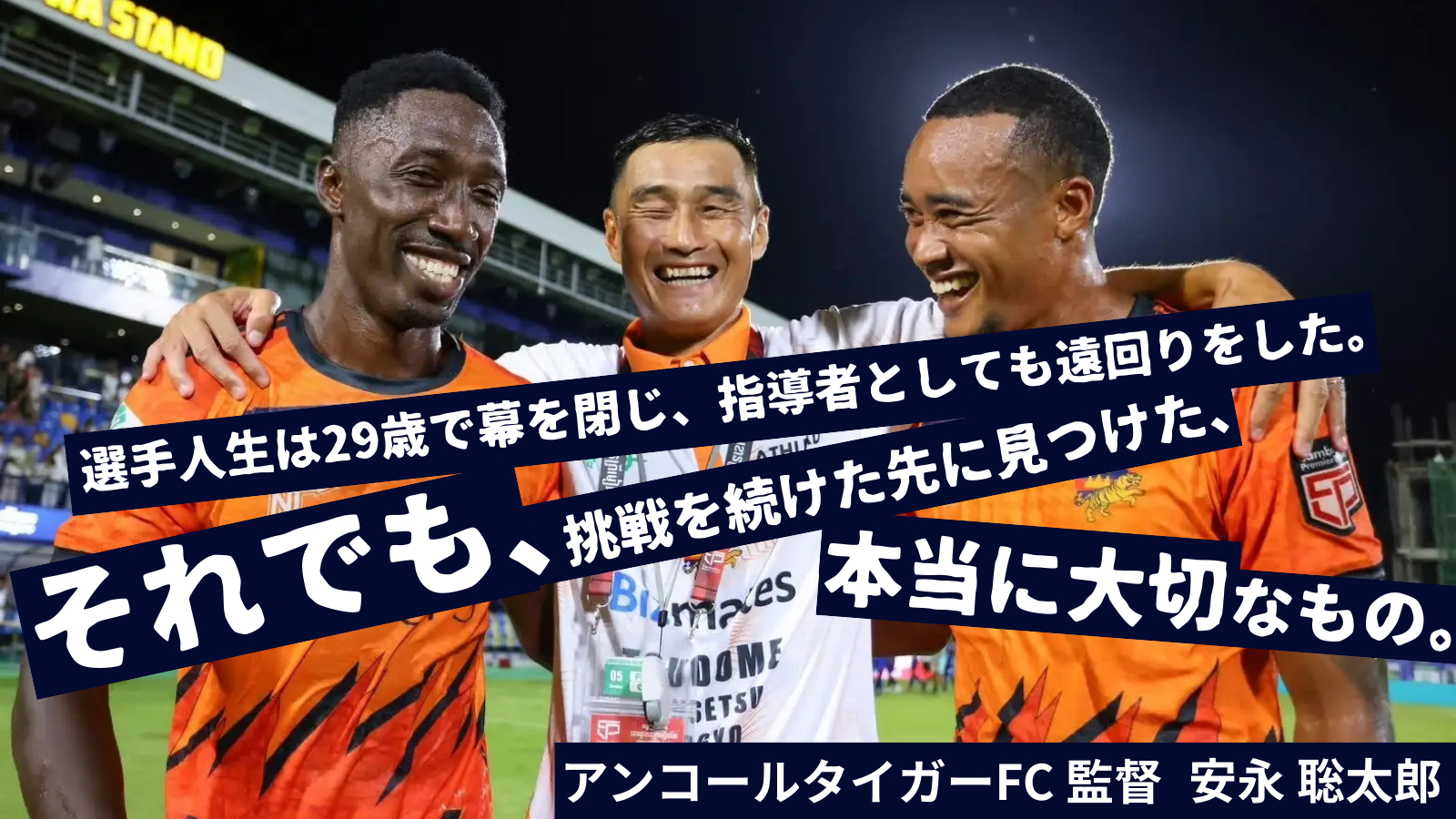
2026.01.14 公開
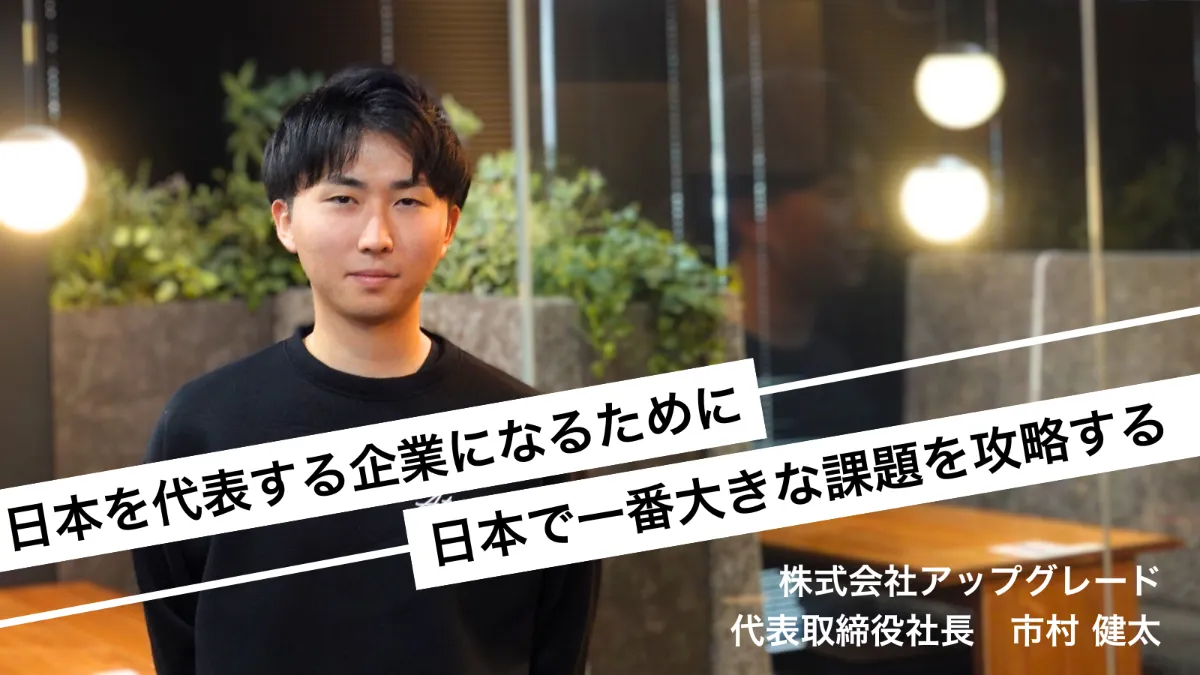
2025.02.06 公開
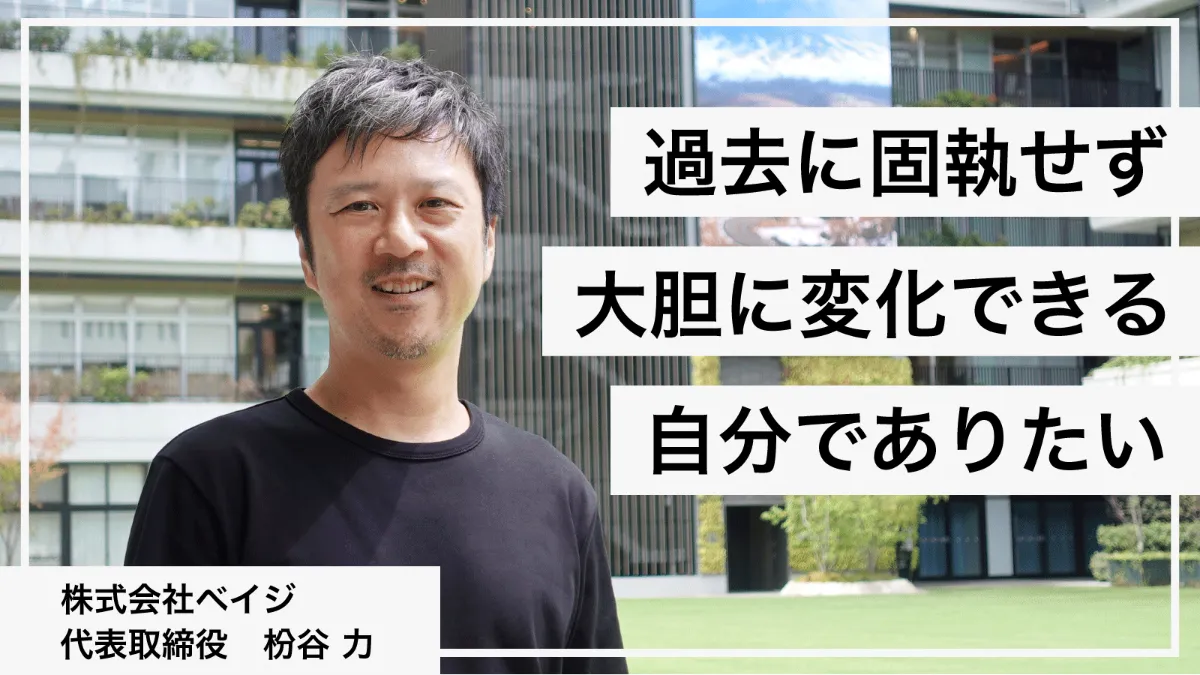
2024.09.19 公開

