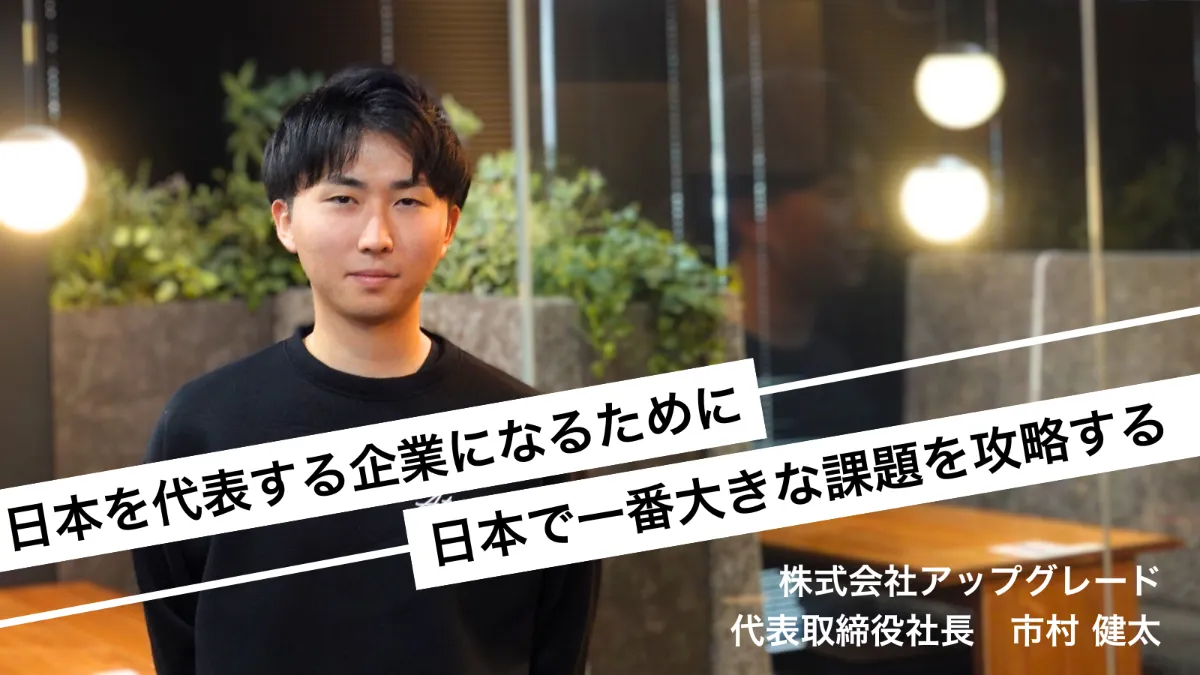
「労働生産性向上を実現するための武器はオペレーション」と言い切るアップグレード市村。頭の中にある戦略とは。
2025.02.06 公開
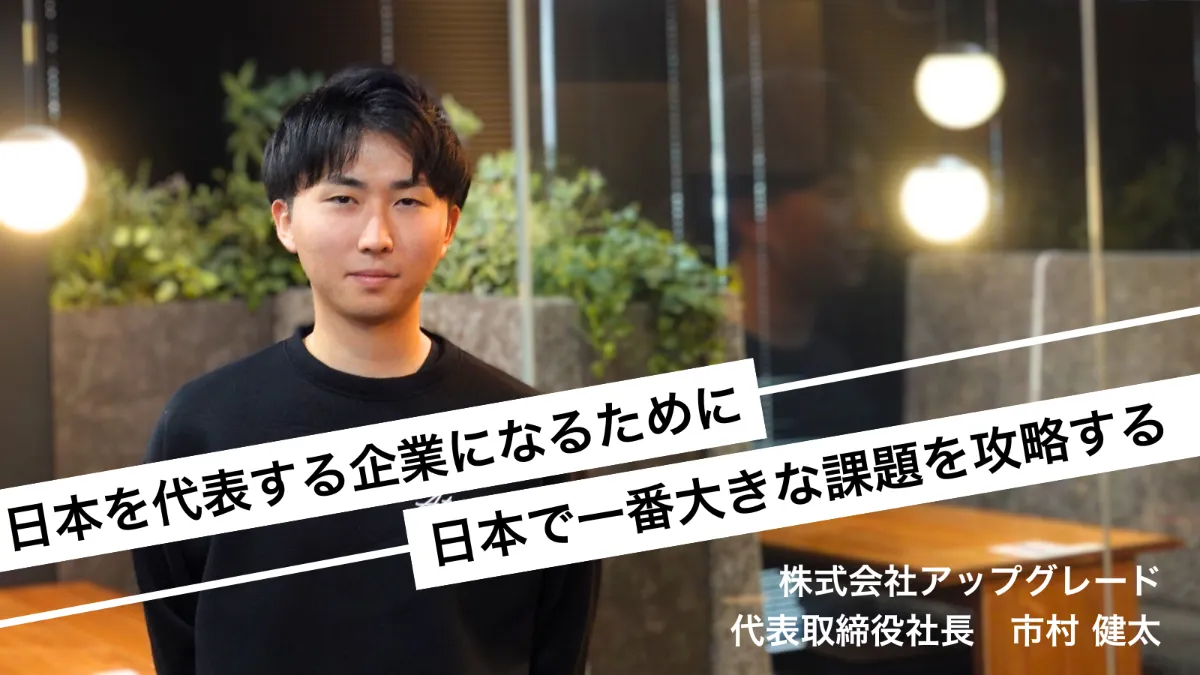
2025.02.06 公開
株式会社アップグレード 代表取締役社長 市村 健太
設立:2021年
事業内容:生成AIパートナー事業、リスキリング事業
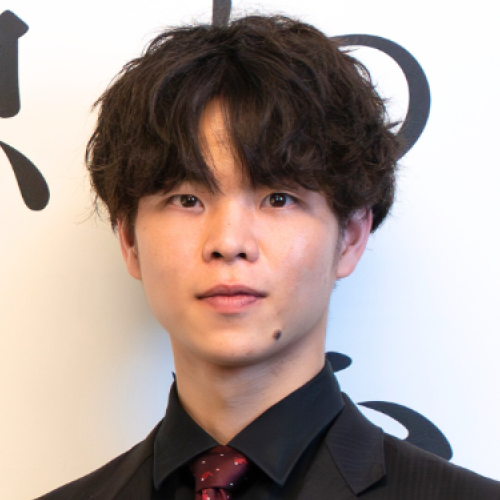
燈株式会社 代表取締役社長兼CEO
市村社長は私の高校時代のサッカー部の一つ上の先輩であり、住み込みで一緒に仕事もしたこともある戦友のような存在です。 彼自身のやり切り力と、それを組織に浸透させる力から多くのものを学ばせていただいています。生成AIの発展に伴い、事業ポートフォリオも変化し、生成AIコンサルティング×リスキリングというまさに時代のニーズを捉えているアップグレード社の発展にますます注目しています。
僕は他のみなさんと比べて、比較的自由な家庭で育ててもらったと思っています。父親は僕が小学生のときに仕事で海外に行き、それからずっと別々に暮らしていました。そのため、小学生のときから何も強制されないというか、「何をやるのか全部自分で決めて良いよ」という家��庭でした。
小さいころから、なんとなく「いつかは自分で会社をやってみたいな」という気持ちがあったのですが、大学生になってから本格的に行動し始めたんです。大学生になってすぐにいろんな本を読み始めて、2年生のときにはインターンに打ち込むために大学を休学しました。
アパレルのECをやったり、AI関連の受託開発をやったり、いろんなことをしている会社でインターンをしていたのですが、創業間もない会社で、メンバーが2〜3人くらいの規模でした。いろんなことをやらせてくれる会社で、そのときの僕の肩書きは「エンジニア 兼 EC事業責任者」でした。独学でプログラミングについて学んだり、オペレーションについて勉強したり、どうしたら事業が成長するのかをどんどんインプットしていきました。
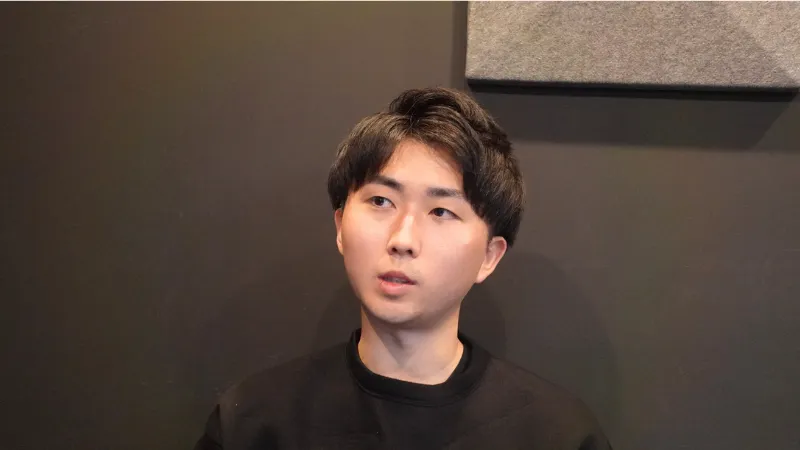
インプットしたものを実際の仕事でも試していって、うまくいったものはさらにやる、うまくいかなかったものは違う施策に切り替える。そのサイクルを回せば回すほど業績が伸びていき、数ヶ月で月商1,000万円を突破して「事業をやるって面白いな」ということを感じました。
基本的には、全部独学です。オンラインの学習サービスを使ったり、本で勉強したり。学ぶためのツールはたくさんあるので、短期集中でやっていました。「やるときには思い切り集中してやる」というタイプなので、月に300時間とか一気に勉強するんです。これはもう気合いですね(笑)。大学2年生のときは、遊びにも行かず、勉強ばかりしていました。
友人と一緒にアプリをつくってリリースしたこともありましたが、そのときは1〜2ヶ月でゼロからアプリのつくり方を勉強していきました。まずアプリをマスターして、次にシステムを学び、そのあとWebについても勉強していって、最終的には一通りインプットしたという感じです。
自分たちでアプリをリリースできたので、次は大手新聞社主催のビジネスコンテストに出場しました。全国の大学生を対象にしたコンテストで、そのときはAIを使ってヘルスケアの課題を解決するというアイデアでした。
結果的に�最優秀賞を受賞したのですが、特に評価されたのは実行力の部分でした。ほかの参加グループは、デスクトップリサーチというか、いろんな情報を集めてきて、分析して仮説を立てて、「こういう課題解決方法があると思います」というアウトプットでした。ただ、僕たちのグループはそこから一歩踏み込んで、仮説の精度を高めるためにいろんな大学の教授に話を聞きに行ったり、プロトタイプをつくって日本のトップメーカーを訪問して壁打ちに付き合っていただいたりしました。企業の方からは「事業化したら一緒にやりましょう」と言ってもらえて、それらも含めてコンテストでプレゼンしていました。
結局、このアイデアは事業化しなかったんですけど、「こういうものがあったらいいな」という仮説に対して、どんどん行動して形にしていく自分たちの姿勢を評価いただけたのはとても自信になりました。
その後、大学でアントレプレナーシッププログラムが始まったんです。当時、僕は東京大学の経済学部の柳川ゼミに在籍していたのですが、松尾研究室と合同のプログラムということでした。そこに僕も参加して、会社を設立しました。
いまもやって��いる個人向けのリスキリング事業です。でも、途中で事業運営をストップすることにしたんです。就職活動したいという人もいましたし、メンバーのなかでモチベーションのばらつきがあったことが理由です。
ただ、大学卒業が近づくにつれて、改めて「自分で事業をやりたい!」という気持ちが盛り上がってきました。自分でも理由が良くわからないのですが、大学4年生のときに完全にスイッチが入ってしまって、創業者や経営者の方が書いた本をものすごい数、読みまくっていきました。300冊以上あったと思うのですが、読めば読むほどやりたいことやあるべき会社の形、理想の組織の状態がどんどんクリアになっていきました。そこで、就職はするけれど、自分の会社も再び動かし始めることにしたんです。
その会社には1年弱しか在籍しなかったのですが、不動産業界向けのオペレーション改善プロジェクトや製造業の顧客に対するリサーチ業務などを担当していました。一番の学びは「コンサルティング」というビジネスモデルに対する理解が大きく進んだことでしょうか。顧客である大企業が、どういう論理で生きているのか、どういう力学で動いているのか。そういうことを近くで経験できたことは、いまの仕事にも活きている�と思います。

僕がコンサルティングファームで仕事をしている間も立ち上げた会社は動いていて、当時は他のメンバーが順調に伸ばしてくれていました。いろいろなプロジェクトを経験してみて、「やっぱり自分で事業がやりたい」と気持ちが明確になったので、2023年にコンサルティングファームを退職し、当時数十人くらいの規模だった自分の会社にフルコミットすることにしたんです。
組織規模は200人ほどです。正社員は少なく、業務委託やアルバイトの学生インターンが多いです。業務委託は日本全国のフリーランスの方々や副業の方々で、営業もいますし、マーケターやエンジニア、デザイナー、バックオフィスなど、職種はさまざまです。
事業としては、リスキリング事業と2023年からはじめた生成AI開発のコンサルティング事業が�あります。
リスキリング事業については、そもそもの部分で僕自身が学ぶことがすごく好きで、教育系の事業がやりたいという想いが昔からありました。何を教えるかを考えたときに、自分が学んできたこともありますし、世の中の需要もあるWebやITのスキルが良いだろうと考えました。けっこうシンプルな理由で始めた事業になります。
個人の方がお客様なのですが、新しいスキルを学び、別の業界や別の職種にキャリアチェンジしたいというニーズを持った方が多いです。WebデザインやWebマーケティングなど、Web系のスキル全般を学べるように幅広いカリキュラムを用意しています。
強みとしては、カリキュラムの幅広さ、そしてコーチングの質の高さだと思います。受講者にはフリーランスのコーチがマンツーマンでサポートするのですが、顧客満足度は90%以上を推移しています。途中で辞めてしまう方はほぼいなく、解約率は非常に低いですね。
リスキリング事業は、お客様にアプローチするマーケティング、サービスを提案して入会いただく営業、入会後にちゃんと満足いただくようにサポートするコーチングという��具合に、いくつかのフローに分解ができます。僕たちは各フローでKPIを置き、徹底して細かく数値を管理して、それぞれで高い数値を出すための改善を常にくり返しています。
ここまではどの会社さんも同じだと思いますが、特徴的なのはKPIの置き方かもしれません。というのも、僕たちは行動指針の中に「ナンバーワン」を掲げていて、日本一になるためのKPIを設定するんです。
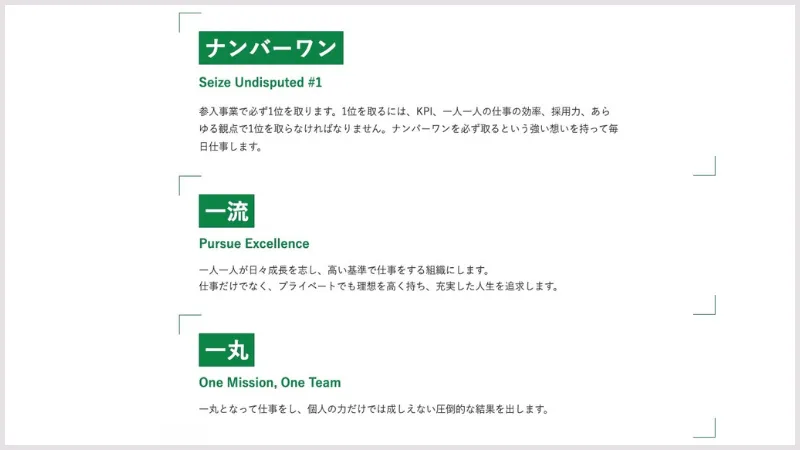
たとえばマーケティングの部署であれば、スキル習得に興味がある方に向けて広告を出す場合に、CPA(Cost per AcquisitionまたはCost per Actionの略。1件の成果獲得にかかるコストのこと)を日本で一番安く設定します。そして「日本で一番安いCPAってどれだ?」と調べに行きます。日本一をベンチマークして、なぜ日本一なのかを分析し、得られた学びを自分たちの部署や業務に当てはめていくんです。
この企業文化があることに加えて、僕たちは他者から得た学びを言語化して、仕組みとして自分たちに応用することが得意です。そのため事業基盤が強く、後発ではありますが伸びています。
カリキュラムについては、僕自身がWebのフリーランスに近い活動をしていたことがあるので、その経験を活かして監修にも参加しています。もちろん、僕の意見だけでは偏りが出るかもしれませんから、WebデザインやWebマーケティング、SEOやSNSなど、各領域でトップクラスのフリーランスの方々とどんどん契約して、一緒に内容をブラッシュアップし続けています。
コーチングの質という観点だと、採用率は6.5%以下で力量の高いコーチと契約しているという前提がありますが、顧客満足度の高いコーチング方法の型化、ナレッジシェアなどに取り組んでいます。採用後のコーチの定着率も高く、どんどんコーチングの質が上がっています。

��どの部署も、言語化や仕組み化のカルチャーがめちゃくちゃ強いのだと思います。一番すごい人のやり方を細かいところまで言語化し、そのナレッジを雇用形態に関係なくシェアしていく。そういう企業文化なんだと思います。
僕の好みかもしれないのですが、単純にこのやり方が好きなんです。最高の事例を参考にし、そこから学ぶ。それを言語化してまわりに共有する。そうすることで事業や組織がスピーディーに強くなると考えています。
この考え方は、当社と契約しているフリーランスの方から非常に好評です。最終的な成果だけでの評価ではなく、丁寧なナレッジシェアや業務へのフィードバックがもらえる仕組みがあるのがうれしいということです。いろんな経験を積んできたプロの方から、そういう声をいただきます。
業務委託だからとか正社員だからとか、雇用形態は関係なくて、やっぱり人間なので自分のやっていることについてのフィードバックをもらえるとうれしいと思うんです。とはいえ、何でもかんでもフィードバックしまくれば良いわけではなくて、タイミングや内容がポイントになると考えています。

僕たちはこの部分も仕組み化していて、たとえばKPIに基づいてどの値を割ったらどういうフィードバックをするのかまで決めているケースもあります。フィードバックをするマネージャーへの教育も力を入れており、マニュアルや動画教材の改善も絶え間なく行なっています。バラつきなく、できるだけ高いクオリティでメンバーへフィードバックできるようにすることで、組織全体のレベルを上げていけると思っています。
このやり方を徹底し続けてきた結果、リスキリング事業は成長を実現できています。
2023年から始めた事業で、現時点での僕の定義は「生成技術に強みを持ったDXコンサルティングファーム」というものです。
生成技術に精通したうえで、DXのコンサルティングから開発まで、伴走支援型で顧客に寄り添うサービスになります。このやり方で、すでに複数の企業様向けにサービスを提供しています。基本的には、売上1兆円を超えるような大企業が取引先です。
展示会に出展するなど、普通のことを地道にやりました。普通につながりを持たせていただき、そこからやり取りを重ねて行ったんです。やっていることは普通ですけど、そのかわり全部しっかりとやり切ります。
オペレーショナルエクセレンスの追求が競争優位性につながると考えています。お客様である大企業にとって、効率的で効果的に業務を行なうにはどうすればいいか。最終的にお客様自身で改善を進められるようにするにはどんな仕組みが必要か。とことん考えて、提案する。シンプルですが、ここに思い切り注力することが、競合企業との差別化にもつながりますし、お客様が求めていることだと考えています。リスキリング事業もこの考えがベースにあり、結果的に後発でしたが一気に成長させることができました。
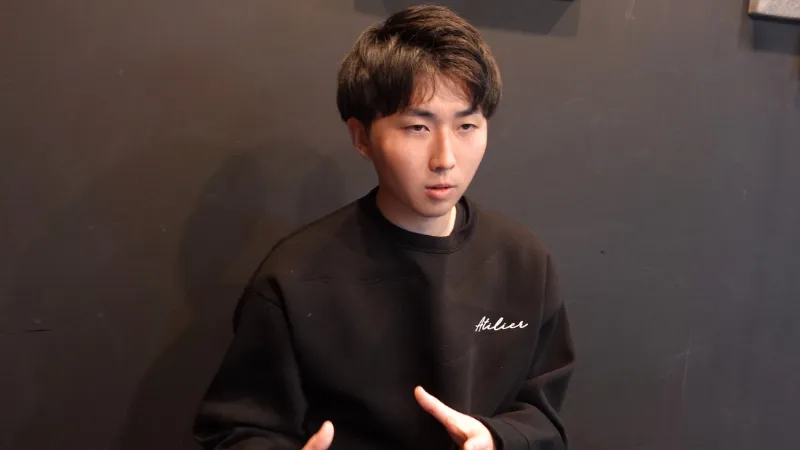
僕が語るのもおこがましいですが、コンサル業界で働いていた経験から、コンサル業界には多くのプレイヤーがいますが社内に非効率なことがたくさんあるんじゃないかと感じていました。組織が大きく、社内に複数のチームとプロジェク��トがあるので、お客様のためになり切れていない部分とか、本質的じゃないところに工数を使っているんじゃないかとか。ちょっと抽象的ですが、そういう仮説が僕の中にあったんです。そういったムダなものを全部なくすことができれば、コンサル領域への参入が遅かったとしても、一番コストパフォーマンスが高く、お客様に選ばれる会社になれると思っていますし、そうなれる自信があります。
お客様により深く入り込んでいくというのはすごく意識しています。自分たちで現場を訪問しますし、自分たちの目で仕事の進め方を確認します。そのうえで要件定義をして生成AI技術を活用して、実装していくということにかなりこだわっています。システムコンサルとかだとお客様から出てきた要件に沿って進めていくところもありますが、僕たちは「そもそもこの業務をこう変えると良いんじゃないでしょうか?」といった本質的な提案も多いです。
あとは「とりあえず全部見せてください」とか、「箇条書きでいいのでいま困っていることや面倒に感じていることをすべて書き出してください」と依頼することもあります。現場のみなさんの声を集めてメドをつけ、詳細をヒアリングしたう��えで、どんどん提案するという感じです。現場で一緒に要件を考えることもありますね。
根本的な違いは、僕たちはAIベンダーやコンサルティングファームから始まっていない、ということかもしれません。事業会社としてリスキリング事業をやってきて、自分たちの組織の中でいろんなムダ取りや改善を繰り返し、その積み重ねで業績に大きなプラスを出してきました。そのため、「手触り感」というか、現場のリアリティを持って事業成果につながる提案ができる。これが大きな違いなのだと思います。
生成AIという観点で言うと、実現したいあるべき姿に合わせてサービスを組み合わせて提供しています。そこまで難易度が高くないものは、最終的にお客様が自分たちでDXできるように支援していきます。たとえば、DifyというオープンソースでLLMのアプリケーションを構築できるプラットフォームがあるのですが、それを使って業務アプリを構築してお客様に提供する。アプリ構築や実装の過程で、Difyの使い方をマニュアル化し、今後お客様が自分たちで自走できるように教育支援を行なっていきます。並行して、Difyではカバーできない高度なLLMを用いた開発は僕たちが行います。こうすることで、課題の把握から解決策の提示、開発や実装、導入や教育の支援までを一気通貫でできるというのがひとつの特徴だと思っています。
これらは他社でもやっているところはあると思います。それでも僕たちが受注できているのは、考え方の違いやスタンスの違いがあるかもしれません。
コンサルティング会社には、徒弟制みたいなものがあるところが多いと感じています。上司や先輩から教えをうけ、脈々と受け継がれていくものです。そのため、同じ会社であっても、チームが違えば仕事をする際に大事にしている考え方が少し違う、みたいな。それが個性だと言うこともできますが、僕はそれは非効率だと思っていて、一番良いやり方を全員が徹底できればそれがベストだと考えているんです。
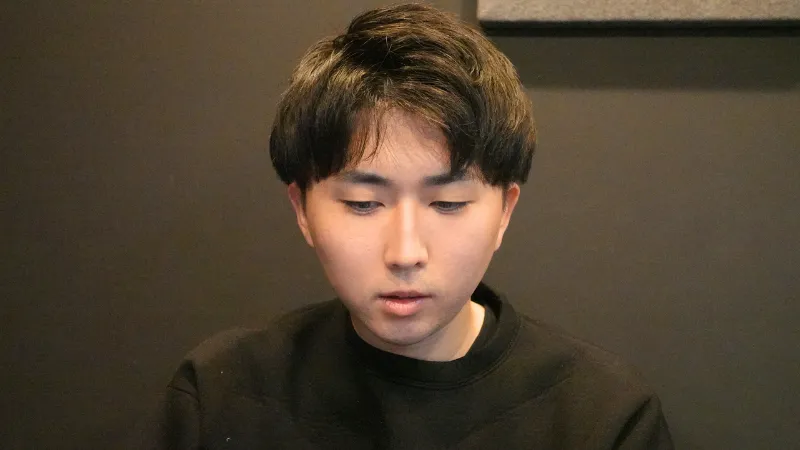
さまざまな学びを言語化し、仕組みに落とし込み、それを磨き続けてきた経験から、僕たちは可能な限り属人性を排除して物事を進めていきます。「排除」という言葉を使うと悪いことのように聞こえるかもしれませんが、品質のバラつきが出ないようにめちゃくちゃ気をつかっているということです。
極端ですが、議事録の書き方ひとつ取っても、人によって形式が違うと非効率ですし、読む方はストレスを感じるじゃないですか。そういう細かいところを、ひとつずつ丁寧になくしていくということに会社全体で取り組んでいます。
前提として、生成AIコンサルティングの対象になる業務は特に絞っていません。PCで行なうものであれば、ほぼすべての業務に改善の余地があると考えています。そのため、お客様の業種も特に限定していません。
守秘義務があるので社名は出せないのですが、一例として、ある大企業様と深くお付き合いしています。
日本全国の現場を実際に訪問して、業務上のさまざまな課題をヒアリングしたうえで、Difyを使って業務アプリを構築して現場に実装しています。出てきた課題は合計で数百個以上あり、つくったアプリケーションは数十個にのぼります。
テクノロジーで改善できるものもありますし、テクノロジーで無理なら「業務オペレーションのなかのこの部分を変えませんか?」とか「基幹システムをこのように変えるのはどうですか?」といった提案もします。
お客様には「生産性をあげたい」という大きなニーズがあるので、そのニーズにつながるのであれば、生成AIに軸足をおきながらもそれ以外の提案もどんどんしていく感じです。
僕たちの会社はまだ知名度がないですし、実績もこれからなので、今後も普通のことを高いレベルでやり切ろうと思っています。社内の教育を徹底しているので、展示会に出ているアルバイトのメンバーであってもお客様の課題をしっかりヒアリングできますし、僕たちが提供できる価値をちゃんと説明できます。商談になってもお客様のことを考えて、まずは無償でデモを用意したりします。そうやって少しずつ信頼を獲得していって、一つずつ、確実にハードルをクリアしていきます。僕も含めて愚直にやり切ることができるメンバーが揃っているので、今後もコンサルティング事業の取引先を増やしていけると思っています。
具体的にイメージしているのは、売上を短中期で100億円にもっていくことです。そのためには、オペレーションを追求していくことがすべてだと思っています。
いまはまだ多くの従業員が20代ですが、生成AI領域においては提案やサービスデリバ�リーの質、マネージャーやメンバーのパフォーマンスの質、すべてにおいて大手コンサルティング会社にも負けていないと考えています。
なぜかと言うと、僕たちは教育領域の事業会社からスタートしており、学ぶことに大きな強みを持っているからです。そして、学んだことを人に教えたり組織に浸透させることにも自信があり、カルチャーになっています。リスキリング事業を成長させてきたという事実にも自信を持っています。コンサルビジネスは労働集約型のビジネスです。それはつまり関わる人たちの教育がもっとも重要なポイントだということです。その教育に強みを持っているので、知名度や事業の規模はこれからですが、十分にスケールできると思っています。
SaaSは当面やらない方針です。というのも、僕自身が事業会社を経営する中で、SaaSを導入するよりもカスタムで自社にあったシステムを開発したときの方が事業成果に結びついたからです。
リスキリング事業では、業務管理システムをほぼすべて内製化しています。自分たちの業務のやり方にできるだけ合わせてシステムをつくっているから、ちゃんと効率化が進むと思うんです。たとえばSaaSを導入すると、そのワークフローにあわせて業務プロセスを変えなきゃいけないじゃないですか。それによってかえって効率が悪くなったり、自社に最適化しきれないので十分な強みにならなかったりというのを経験しました。もちろん、SaaSをすべて否定するわけではなくて、たまたま僕たちのやり方にはあわないということなのですが。
この方針は自分の中ではけっこう強固なもので、当面は僕たちはSaaSではなく、お客様の個別の課題をしっかり解決することで業績を伸ばしていきたいと思っています。生成AI技術の登場によって開発コストも以前より落とせますし、カスタムソリューションでお客様の事業成果にコミットできるDXコンサルティングを追求します。
売上を伸ばすための具体策ですが、コンサルティング事業の型化を進めることです。いまはまだ僕や役員が現場に行っているので、言語化し、ナレッジを型化することで担い手を増やしていきたいと考えています。

お客様とどういうメールのやり取りをしてきたか、電話でどんなやり取りをしたか、これらをファクトを取って可視化できるようにする。そして、出てきたファクトに対して効果的なタイミングで的確にフィードバックする。これらを内製化している社内システムですべて確認できるようにしていく。リスキリング事業でつくってきた仕組みを、コンサルティング事業でもつくりあげようと思っています。
そのように思われることもあるかもしれません。ただ、実際に社内からはそういう声は聞こえてこないです。というのも、どれだけ型化や仕組み化を進めても、絶対にオリジナリティを出さなきゃいけない部分が残るからです。そこに集中して各自が工夫してくれればいいですし、現場のみんなもそれを楽しんでいる感じがあります。
ちょっとドライな言い方になるかもしれませんが、僕としては無駄なところでオリジナリティを出して欲しくないんです。たとえば資料をつくるときに、「このスライドのデザイン、個性的でかっこいいでしょ?」とか本当に意味がないと思っています。
スライドに個性を出すために使う時間があれば、もっと本質的なところにこだわって欲しい。具体的にお客様に何を提案するのか、どうやって最高品質でデリバリー��をするのか。そういうことを考えるために時間を使って欲しいですね。
本質的な部分で工夫をして、成果につながればそれを言語化して共有しますし、すでに型化されている部分でも、現場で違和感があればすぐに修正が必要かを精査します。そういう意味では、「毎日何かを良くしていく」というスタンスです。
僕たちは「ナンバーワン」という行動指針を掲げているので、「これは本当に日本一なの?」「いまのやり方で本当に日本一になれるの?」という問いを自分たちに向け続けています。しんどいし、プレッシャーに感じることもありますが、それよりも日本一に向かって前進していることを楽しんでいますね。
ちなみに、行動指針の中には「一丸」というのもあるのですが、お互いに支えあい、刺激しあう組織でありたいという想いを込めています。オンライン、オフラインを問わずけっこう飲み会もやっていて、みんなで仲良くなることにもすごく力を入れています。僕たちは機械じゃないので、影響を与え合うことで個人では出せないパフォーマンスが出せることもあると思うんです。そういった人間的なつながりも、会社としては大切にしたいと考えています。
自分で事業をやるのなら、偉大なスタートアップになりたいという想いは創業時からありました。そして実際に会社をやってみて、名もない会社にみんなが人生の多くの時間をかけてくれています。そうなると、一番を目指さないとみんなに失礼だなと思ったんです。優秀な人が多いので、会社が中途半端になってしまうと「大企業に行ったほうが良かった」と思われるかもしれない。それは絶対に嫌だという気持ちがありました。
中途半端にならないためにも、「日本一を目指さなきゃいけない」という行動指針が必要で、そうなると日本で一番大きな課題の解決にチャレンジしていきたい。じゃあ、日本の一番の課題は何かというと、労働生産性だと思うんです。今後人口が減っていくことは確定しているので、労働生産性を上げていかないと日本は沈んでしまうと思っています。そのため、一番の課題にストレートに挑戦しようと考えました。
リスキリング事業を通じて受講者の方のスキルアップを支援したことで、個人の生産性向上に寄与できている自負はあります。次は組織ということで、まずは改善インパクトが大きい大企業向けに、生成AIを活用した生産性向上のコンサルティングを広げていきます。
この二軸は今後も変わらないと思っています。労働生産性をあげるための手段のひとつは、個人のスキルアップを実現すること。そして、いくら個人のスキルが高くても職場の業務プロセスが非効率のままだと組織の生産性があがらないので、そこを改善すること。どちらもナンバーワンを獲るぞ!という気概を持ってがんばっていこうと思います。


株式会社ディプコア 代表取締役CEO
市村社長にお話をお聞きして、感じたことはオペレーションの大切さと難しさです。多くの書籍でも明らかになっていますが、日本の大手完成車メーカーも、強みの本質は徹底的に磨き上げたオペレーションだとよく言われるのは周知のことかと思います。日々の業務の流れはもちろん、業務の品質要件を満たしているかをどのようにチェックしフィードバックするか。これらのオペレーションを磨き続けることで、企業の競争力は確実に向上していくことは歴史が証明しています。 ですが一方で、あるべきオペレーションを徹底し続けることは、非常に難易度が高く、継続すること自体が難しく、オペレーショナル・エクセレンスに到達する前に形骸化し、頓挫することがほとんどだと思います。同社のように、遠方在宅の方や、業務委託の方が多い場合はなおさらだと思います。 そういった状況下でのマネジメントは難しいと一般的に言われている中で、同社は全国各地のメンバーをまとめ、順調に業績を伸ばしているそうです。まだ20代という若さで、「オペレーションを磨き続けることで事業を拡大していく」という市村社長の言葉には自信と説得力を感じました。
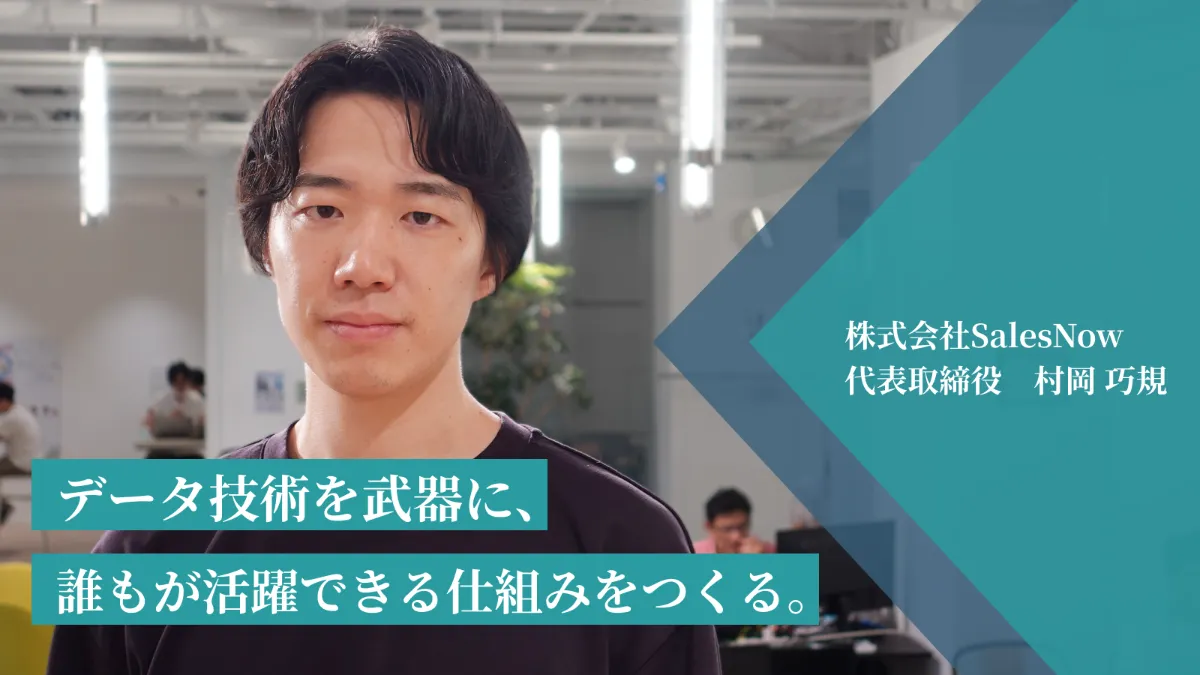
2024.08.01 公開
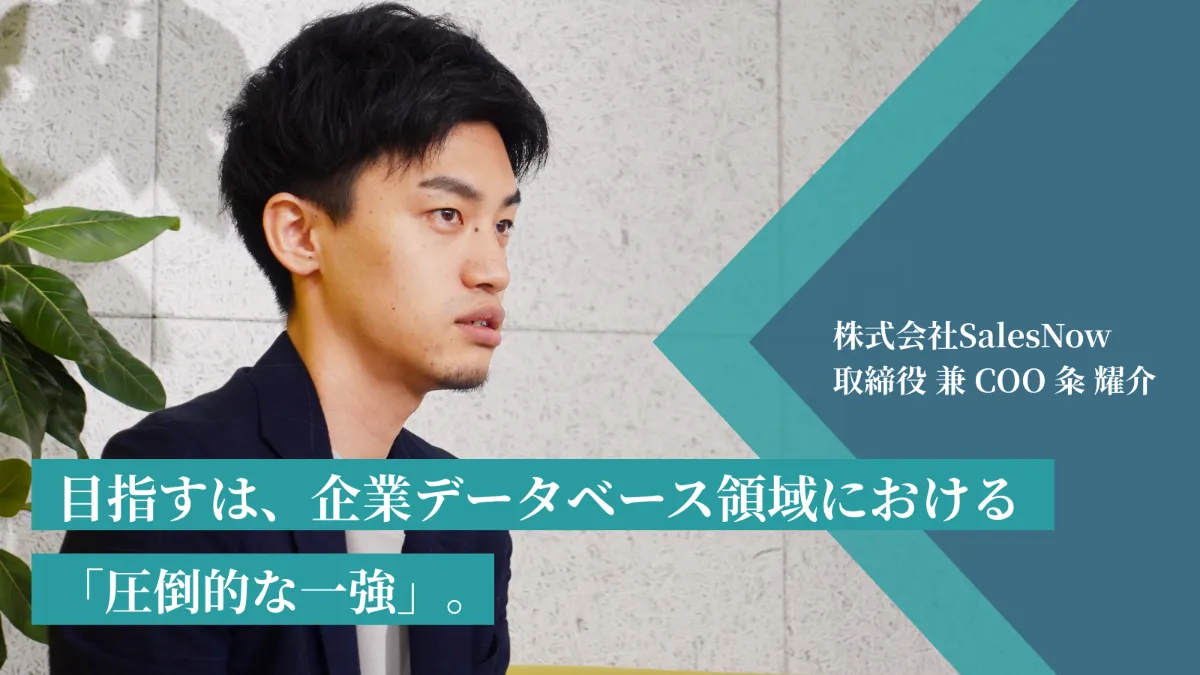
2024.08.09 公開
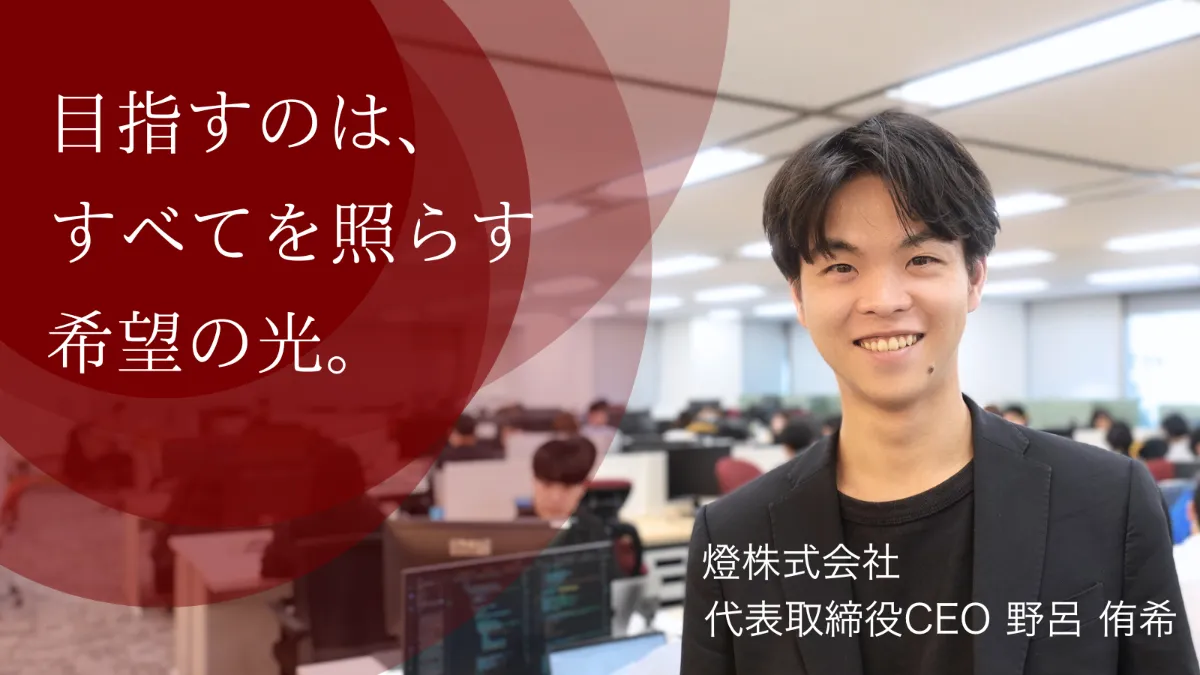
2024.12.18 公開
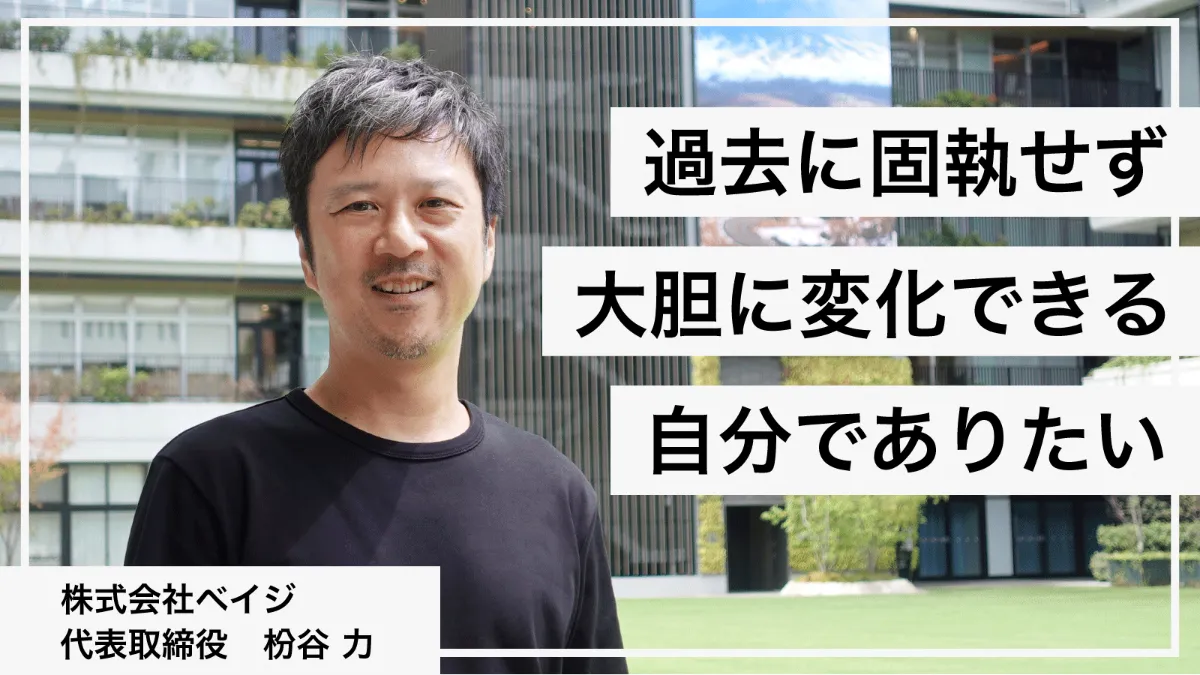
2024.09.19 公開
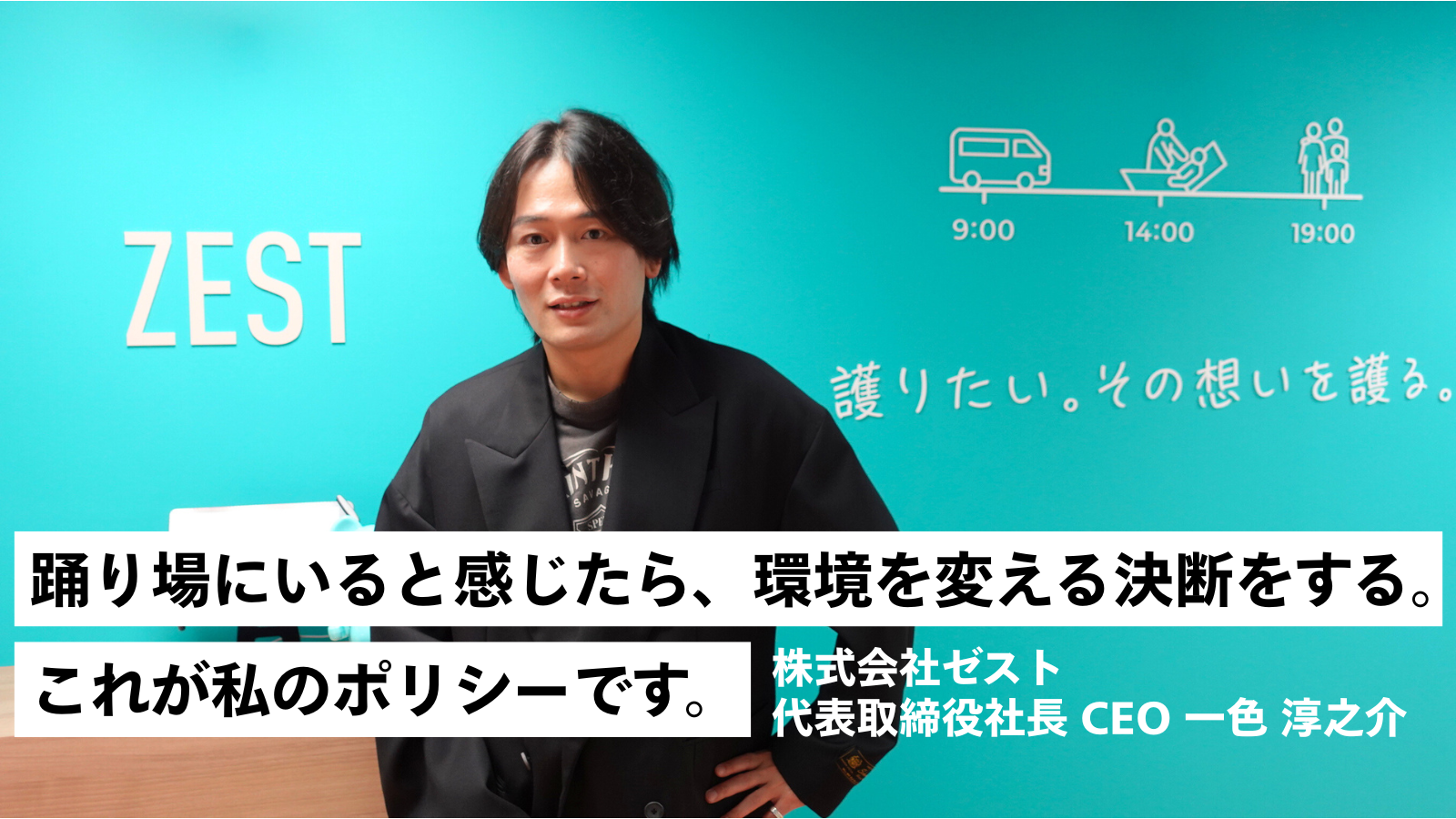
2025.08.29 公開

2025.11.10 公開

